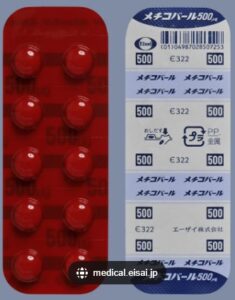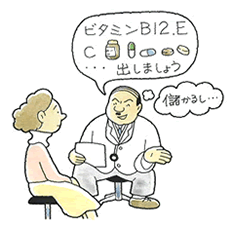ロキソニン、リリカにつづきトラムセットについて。トラムセットも痛みをおさえるお薬です。慢性疼痛や抜歯後の痛みに用います。私はこの3薬を勝手に「痛み止め御三家」と呼んでいます。
【適用】
ロキソニン、リリカにつづきトラムセットについて。トラムセットも痛みをおさえるお薬です。慢性疼痛や抜歯後の痛みに用います。私はこの3薬を勝手に「痛み止め御三家」と呼んでいます。
【適用】
一般的な鎮痛薬では十分な効果が望めない痛み、たとえば しつこい腰痛症や変形性関節症関節リウマチ、帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害性疼痛、線維筋痛症、あるいは骨削除を必要とするような難治な抜歯後などです。
交通事故の治療では最初から服用されることは少なく、ロキソニンやリリカで効き目がない、副作用がある場合などに、交代して登場します。医師によってはその副作用から、やや敬遠される薬でもあります。
【薬理】
2種類の有効成分からできている鎮痛薬です。第一の成分はトラマドール(トラマール)。オピオイドと呼ばれる特殊な鎮痛薬で、ふつうの鎮痛薬が効きにくい神経痛などによい効果を示すのが特徴です。麻薬系オピオイドの代表はモルヒネです。モルヒネに比べれば作用がおだやかで副作用も少ないと言われています。
もう一つの配合成分は、昔からあるアニリン系解熱鎮痛薬のアセトアミノフェン。こちらは、痛みの神経に働きかけ、痛みに対する感受性を低下させて痛みをしずめます。必ずしも強力とはいえませんが、安全性が高く、各種の痛みに汎用される良薬です。処方薬としてはもちろん、一般薬の多くにも採用されています。
これら2成分がいっしょに作用することで、鎮痛効果の早期発現、効果増強、作用時間の持続がはかれます。
【副作用】
通常、1日4回、1回1錠です。服用間隔は4時間以上空ける必要があります。アスピリン喘息(鎮痛薬や解熱薬で喘息発作を誘発)のある人は使用できません。てんかん、胃潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、喘息など、その病状により使用できない場合があります。市販のカゼ薬や解熱鎮痛薬の多くにアセトアミノフェンが配合されています。この薬と重複することになりますので、これらとの併用は危険です。
また、抗うつ薬と飲み合わせると、セロトニン症候群やけいれんを起こしやすくなる可能性があります。当然ですが飲酒は控えます。多量のアルコールにより、めまいや眠気、肝障害、呼吸抑制などの副作用がでやすくなります。重い副作用として、けいれんと意識消失が報告されています。めったにないと思いますが、もともと てんかんや脳に病気のある人はより注意が必要です。
また、長期服用中に急に中止すると、イライラ、興奮、不安、不眠、震え、吐き気や嘔吐など反発的な症状が現れることがあります。モルヒネのような依存性も指摘されています。したがって、トラムセットを「麻薬系?」と呼ぶことがあります。もっとも鎮痛剤の多くは麻薬と成分が同じなのですが。
続きを読む »
 【効果】
【効果】


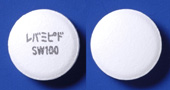
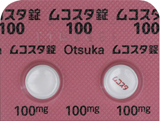
 ロキソニン、リリカにつづきトラムセットについて。トラムセットも痛みをおさえるお薬です。慢性疼痛や抜歯後の痛みに用います。私はこの3薬を勝手に「痛み止め御三家」と呼んでいます。
【適用】
ロキソニン、リリカにつづきトラムセットについて。トラムセットも痛みをおさえるお薬です。慢性疼痛や抜歯後の痛みに用います。私はこの3薬を勝手に「痛み止め御三家」と呼んでいます。
【適用】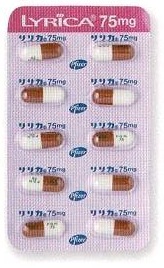
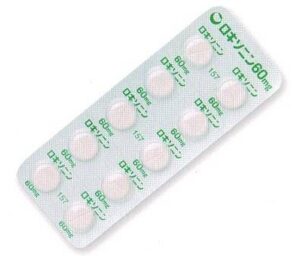 もはや、痛み止めの定番となりました。当然に交通事故外傷でも処方されることが多い薬です。解熱鎮痛消炎剤で、第一三共や後発医薬品として各社から発売されています。かつては劇薬で医師の処方箋を要したが、現在は劇薬指定を解除され、処方箋がなくとも後述のようにドラッグストアなどでも入手できるようになりました。一般用医薬品としてはロキソニンS錠が第一類医薬品として発売されています。
もはや、痛み止めの定番となりました。当然に交通事故外傷でも処方されることが多い薬です。解熱鎮痛消炎剤で、第一三共や後発医薬品として各社から発売されています。かつては劇薬で医師の処方箋を要したが、現在は劇薬指定を解除され、処方箋がなくとも後述のようにドラッグストアなどでも入手できるようになりました。一般用医薬品としてはロキソニンS錠が第一類医薬品として発売されています。