本日は、打ち合わせを兼ねて社労士先生と昼食でした。場所は六義園近くのカフェ、緑の中庭がある都心のオアシスです。接待の席もコロナ以降は激減しましたが、ランチミーティングも少なくなったと思います。
六義園は都営三田線の千石駅から徒歩5分位ですが、巣鴨駅から何度か訪れています。高校は巣鴨駅からすぐでしたので、高校時代はこのあたりがランニングコースだったり、3年間、周囲をうろうろしていました。当時と比べて、周囲に高層ビルが増えました。それでも、都心でありながら、どこかのんびりしたとした街の雰囲気は変わってませんでした。
 33°の酷暑、園内を散策する気分にはなれません。涼しくなったら寄ってみたいと思います。
33°の酷暑、園内を散策する気分にはなれません。涼しくなったら寄ってみたいと思います。
社会保障制度の問題は今後も注目、取り上げていきたいと思います。 解説は昨日の通りなのですが、一言所感を述べたいと思います。 今回は行政側の生活保護費の削減が、憲法に照らして違法と判断されました。これから削減分の補填を行うことになります。裁判の負担と時間を奪われた原告(申請者)に対して、迅速に進めて頂きたいと思います。間違いを認め、それを正すことが大事です。
しかし、原告側の一部からの物言いが、ちょっと気になりました。今回の判決を受けて、「行政側に謝罪してほしい」との意見です。単に謝罪の言葉を欲しているだけかと思いますが、民事の世界では謝罪はただではありません。謝罪=慰謝料なのです。もちろん、本件で慰謝料が発生するとは考えづらい・・せめて追加の支給分について利息分の加算はあるかもしれません。これらは実務的な問題かと思います。
私が引っかかるのは、謝罪を求める意識です。そもそも、生活困窮者へ皆の税金から援助をする制度です。司るのは行政ですが、助け合いの制度であることは間違いありません。誰もが、いつ何時、病気や不慮の事故で、生活に困窮するかわかりません。利用者は、感謝を持って制度を享受するものです。だからこそ、行政側に対して、謝罪を要求する気持ちに少し引っかかるのです。
確かに、裁判の負担を強いられた請求者の苦労や憤慨はわかります。わかりはしますが、行政側は意地悪で支給削減をしたわけではなく、また横領などの犯罪をしたわけではありません。生活保護法に従って、正しいと思って削減を決定したものです。その決定が間違っていたのですが、法解釈、言わば手続きが間違っていたことが、どれだけの悪なのか、考えてしまいます。
税金を公平に運用することが行政側の務めです。そこに間違いがあったからと言って、全面的な謝罪をするべき悪行だったのでしょうか。繰り返しますが、請求者側の苦難、その気持ちは分かりますし、行政側も誠意をもって追加支給を急ぐこと、間違った運用をしたことへの言葉はあってしかるべきと思います。ただし、助けてもらっている側が謝罪を!と憤る姿に、日本人の美徳は感じられません。受給者としての権利意識が欧米並み?と思ってしまうのです。これを言うと、生活保護受給者に対して、受給の遠慮や委縮となり、制度の利用をためらう問題に繋がるかもしれません。しかし、受給者=助けてもらう立場からの発言には、もっと適切な言葉があるように思います。 交通事故はじめ、あらゆるもめごとに立ち会った者としては、言葉は大事に思います。間違ったことをしたら謝ることが基本です。一方、被害者側からの謝罪の要求は、その言葉や込められた感情を伝えるに、実はとても難しいと思っています。
先週末、判決がでました。生活保護費の減額は違法か適法かが争われた注目の裁判でしたが、最高裁は27日午後、減額は違法とする判決を下し、国側の敗訴が確定しました。
これまでも、全国で31件、原告の数およそ1000人に上る生活保護引き下げの取り消しを求める訴訟となっていました。高等裁判所の判決が言い渡されたのは12件。「違法」が7件、「違法ではない」が5件と判断が分かれるなか、最高裁は27日「違法」とする統一的な判断を示しました。今後、類似の裁判において、指標になると思います。 憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
日本国憲法第25条の「生存権」とは・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした法律です。 この精神から、国の財政(の悪化)に関わらず、一旦決まった金額は下げてはいけない・・ことになります。 憲法25条から、優しい日本が実現できていると思います。しかしながら一方で、ろくに納税していない外国人にまで支給するケースは問題視されています。私もネパールの方で、生活保護の支給を目当てに一族が続々と来日しているケースを目にしました。また、計画的に離婚してシングルマザーとなり、生活保護を受けている方もいました。実態としては、分かれた夫と夫婦同然の生活をしているのです。
このような、制度の悪用を防ぐ手立てを強化する必要があると思います。また、度々議論される、「国民年金との逆転現象」は喫緊の問題です。真面目に年金を払ってきた人への年金支給額に、生活保護の支給額が接近しています。これは、年金など払わずに老後は生活保護を受給した方が得である・・とんでもない不公平を構成するのです。現在、年金を支払っていない層が、次々と老後になって生活保護を受給することになれば・・もう、支給額の減額は避けられない事態になります。”途中から下げられないのであれば、最初から下げる” 運用になりかねません。
将来の支給額はどうなるのか、対して憲法の精神をどこまで守るのか・・・実は、この問題は始まったばかりと思っています。
本日は久々の病院同行ダブルヘッダーでした。以前はそう珍しいことではなかったと思います。いよいよ、人手不足に戻ってきた感があります。まだ、売上の回復にはもう少しかかると思いますが・・。

朝晩、通勤・通学の時間帯に被って、電車に座れないことも・・今日は早く寝よう。
交通事故の被害者さんによく見かけることの一つに、「甘え」があります。この甘えは、事故に遭った気の毒な自分を、周囲が好意的に助けてくれるはず・・との期待です。それは、多くの場面で裏切られることになります。 1、救急車
自分の希望する病院へ運んでくれません。ケガの症状に対応できる、至近の病院を目指してくれますが、患者の希望はまず通りません。重傷者にとっては、病院を選ぶほどの余裕がないものですが、仮に希望する病院を言っても、希望通りになることは稀です。救急車はタクシーではないのです。 2、警察
被害者の力になってくれることを期待したいところです。しかし、原則、警察は民事不介入です。加害者に刑罰を問う場合、刑事事件として、その第一次調査を担っているに過ぎません。民事に絡む、過失割合など警察が決めることではありません。どちらの肩を持つことはありません。
また、ケガをしているにも関わらず、「物件事故扱い」を勧められることも珍しくありません。「人身事故扱い」となれば、司法警察官の現場検証と、より精密な実況見分調書の作成、双方へ供述調書を作成する必要があります。物件事故の何倍も面倒なのです。よく、被害者側にも過失がある場合、「あなたも刑罰に問われる可能性がありすよ(だから物件のままにしよう)」と、まるで脅し文句のように迫ってきます。実際は、加害者に相当のケガがない限り、被害者が刑罰に問われることはほとんどありません。ただし、その可能性としては0ではないことを根拠に、「物件事故扱い」を迫る脅しが常套句になっています。 3、病院
病院はお金をもらって治療する場所です。そこまでは救済機関と言えます。しかし、事故との因果関係が問われる症状について、責任をもって証明する立場ではありません。具体的には、”その症状は事故によって起きたかどうか”など、保険会社の支払いに関して疑義が生じた場合、その問題には立ち入りたくないのです。病院は淡々と治療するだけ、事故との因果関係など知ったこっちゃないのです。その証明は患者自身で動かなければならないのです。 4、加害者
詫びの電話でも一本入れば良い方で、保険会社に対応を任せ、それっきり消えてしまうのが加害者です。当初、「物件事故扱いにして」と泣きつくときは、それはそれは謝罪・反省の態度です。ところが、刑事処分が決まったら、梨のつぶてとなり・・多くの被害者さんは憤慨することになります。
交通事故での加害者は、しばらくすれば外野になります。1年後の解決時期には、事故のことすら忘れていることでしょう。 5、そして保険会社
加害者側・保険会社の対応に、激怒している被害者さんをよく見かけます。もちろん、態度の悪い担当者もいないわけではありませんが、多くの場合、被害者さんの「俺は被害者なんだぞ!」との態度に原因があります。保険会社は加害者に代わって、事故対応の代行をしているに過ぎません。被害者に対して贖罪する立場ではないのです。被害者の態度から、担当者は写し鏡の対応になっているのです。
淡々と保険会社の決めた基準額で解決を迫ってきますが、それは当然の姿勢です。被害者さんは紳士的な態度で、理路整然と損害を主張し、その証拠となる資料を丁寧に提出する必要があります。よく、これら書類提出に際して、「そんなの加害者がやるべきだ!」と言う被害者さんがいますが、それは逆です。法律上、被害者が証拠を集めて突きつける立場なのです。それが社会・大人のルールです。自分(被害者)は相手保険会社の契約者=お客様ではないのです。よくよく自身の立場を理解をして、対応していかなくてはなりません。 このように、皆、それぞれの立場で仕事をしているだけです。被害者だけの為に働く味方はいません。被害者さんは、自動的に救われる理想郷を夢見ている場合ではありません。自ら動くしかないのです。それが困難であれば、弁護士や秋葉を雇うことになります。お金を頂く私達だけが味方になりうるのです。
アイドルの世界は別世界、選ばれた者のみが至る場所ですから、庶民にとっては文字通り憧れの対象です。ジャニーズ含め、なんら関心ない芸能会のことですが、それでも「ダッシュ村」は好きでよく観ていました。何より、TOKIOはバンドです。出来る事ならキーボードの国分さんにとって代わって、キーボードで参加したかった。そして、週末はダッシュ村で米を育て、カモの有機栽培をやりたかった。山口さんに代わって、ダッシュ島で家を作りたかった。私など、到底無理ですが・・。 事務所自体、その代表者が亡くなってから、やっと数々の問題が報道されました。さらに、人気筆頭のSMAPは5人中3人が警察の厄介になったり、問題行動で引退したり・・(すごい比率です)。そして、TOKIOも同じ道を辿っています。
ジャニーズのアイドルグループで、唯一メンバーになりたいと思ったのはTOKIOでした。恵まれた境遇に感謝して誠実に生きていくか、図に乗って周囲に迷惑をかけるか・・・その人の人間性に左右されると思います。夢の存在が悪夢となり、残念でなりません。
若宮橋。 美しい橋脚の眺めに、思わず写メを残しました。

若宮公園にかかる橋です。これを渡ると、森の里の住宅街を経て七沢に通じます。七沢は神奈川リハビリテーション病院行で何度か足を運んでいますが、未だ温泉には未湯です。 さて、本日は紹介状の依頼で病院同行でしたが、医師にうっかり、「セカンドオピニオンのような・・」と言ってしまいました。紹介状の依頼とは、別院への転院を意味します。セカンドオピニオンは現在の病院にかかりつつ、別院での診察を受けて意見を伺うものです。これは似て非なるもの、医師からも念を押された次第です。
本日は酷暑の中、ご参加の皆様、誠にありがとうございました。
灼熱の埼玉セミナー、10年前の埼玉代協・総会のセミナー講師を拝命した日を思い出しました。その日は37°超えの危険な暑さでした。本日は35°なので、それよりましですが・・。

さて、今年注力しております過失相殺、ある損保代理店さまからご質問がありました。 Q:「自転車通行OKの歩道があるにもかかわらず。車道を走っている自転車と事故を起こした場合、わざわざ車道を走っていることへの過失を問えるものでしょうか?」 A:「自転車は道路交通法上、軽車両になります。原則、車道走行となります。自転車通行できる歩道は、単に自転車もOKとしているに過ぎません。したがって、その道路の規制により例外はあるかもしれませんが、車道の走行自体に過失は生じません。」となります。 この問答に直接答える記事は見当たりませんが、自転車の歩道走行は例外規定であることが伺われます。以下、警察庁のHPから引用します。 <警察庁HP> 自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)から 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
高次脳機能障害は主に精神面の障害にスポットが当たりますが、身体に麻痺を残すことも珍しくありません。よく、クモ膜下出血で倒れた高齢者が、その後遺症で半身麻痺に陥るケースがあります。これら脳性麻痺は、手足の一部に残ることもあります。本件では、上肢、とくに手指の麻痺についての立証が勝負を決めました。
医師に任せっきりですと、審査側に正確な障害が伝わらないことがあります。本例は、身体麻痺の立証について参考になる実績と思います。7級と5級では、自賠責保険で約523万円の差額となり、その後の賠償金では1千万円以上も差がつくことがあるのです。その重大さを予見した弁護士は、秋葉へ依頼したのです。
 私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
5級2号:高次脳機能障害(20代女性・埼玉県)
【事案】
自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。 【問題点】
高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・
・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。
・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。
・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。
・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。 続きを読む »
当たり前のことですが、後遺症などなく治ることが一番です。それでも、事故で損失した時間と痛み、その代償はお金に他なりません。本件、ご依頼者様の希望は完全回復です。それでも、必ずなんらかの支障は残るケガです。ご希望を尊重しつつ、等級認定も取るミッションとなりました。
 いやぁ、根性のある被害者さんでした
いやぁ、根性のある被害者さんでした
14級9号:橈骨遠位端骨折(50代女性・埼玉県)
【事案】
信号のない交差点を自転車で直進中、左方より走行してきた自動車に衝突し、負傷した。直後から右手の痛み、神経症状に悩まされる。 【問題点】
当初、保存療法で問題ないということだったが、3回目の診察にて「骨折部にズレが生じたため、急遽3日後にプレート固定の手術を受けることとなったが、術後に痺れが出現したため、抜釘時に手根管開放術を同時に実施する方針となり、症状固定予定日が更に遅れることとなった。 【立証ポイント】
ご本人・ご家族の意向としては、後遺障害の認定を受けることよりも完治を目指す(症状が少しでも回復するのであれば、治療期間や金額は関係ない)ということだったため、症状固定日の設定に苦労した。今回のようなケガであれば、事故から1年が妥当だが、ご本人・ご家族と医師の意見を勘案し、1年半で症状固定することとなった。ご本人が外国籍だったため、自覚症状については、ご家族とともに箇条書きしたメモを作成し、病院窓口へ渡した。
骨癒合も良好なため、自覚症状メインの申請であったが、1ヶ月で14級9号の認定を受けることができた。ご本人・ご家族が望む治療期間を確保し、後遺障害等級認定を受けるという2つのミッションをなんとかやり遂げることができた。
毎度、セミナーでは参加者様からも、進んでエピソードを伺うようにしています。今回のテーマは過失相殺Q&Aです。問題の中、路上横臥者をひいてしまった場合の過失割合です。
 昼間は、横臥者30:自動車70 が基本割合です。自動車の前方注意義務が強く取られている印象です。
夜間は、横臥者50:自動車50 と自動車の過失が減ります。
夜、道路に寝ている・・多くは酔っ払いと思います。これまで、弊所の受任例でも数件ありました。いずれも重傷事故になっています。道路で寝ていれば、その人へ過失が取られることは言うまでもありません。対人賠償からの支払いより、寝ていた方に適用される人身傷害での解決となったケースもありました。
その例 👉 8級1号:視神経管骨折・失明(30代男性・千葉県)
やはり、酔って寝ている状態は危ないのです。夜間で人通りがなければ、そのまま逃げられて、加害者が捕まらない可能性も高いと思います。悲惨な事故になりますが、自業自得の側面から50:50となるのでしょう。
本日ご参加の損保代理店さまでも、同様のエピソードを伺いました。夜間の酔っ払いの交通事故被害は、そう珍しい事故ではないようです。
昼間は、横臥者30:自動車70 が基本割合です。自動車の前方注意義務が強く取られている印象です。
夜間は、横臥者50:自動車50 と自動車の過失が減ります。
夜、道路に寝ている・・多くは酔っ払いと思います。これまで、弊所の受任例でも数件ありました。いずれも重傷事故になっています。道路で寝ていれば、その人へ過失が取られることは言うまでもありません。対人賠償からの支払いより、寝ていた方に適用される人身傷害での解決となったケースもありました。
その例 👉 8級1号:視神経管骨折・失明(30代男性・千葉県)
やはり、酔って寝ている状態は危ないのです。夜間で人通りがなければ、そのまま逃げられて、加害者が捕まらない可能性も高いと思います。悲惨な事故になりますが、自業自得の側面から50:50となるのでしょう。
本日ご参加の損保代理店さまでも、同様のエピソードを伺いました。夜間の酔っ払いの交通事故被害は、そう珍しい事故ではないようです。
 続きを読む »
続きを読む »
毎月のように、弊所の依頼者様が労災の顧問医の診察を受けています。純粋な業務災害の依頼は少ないものですが、通勤災害は数多く、交通事故の解決に労災請求が被ってきます。そして、自賠責保険で後遺障害の認定を得ますが、前後して労災の障害給付の請求もすることになります。両者は9割がた同じ審査基準と言えますが、部位・症状によって違いがあります。これは、毎度のテーマでもありますが、最大の違いは、文章審査を原則とする自賠責に対し、労災は顧問医の診察があることです。 違いの一例 👉 労災は半袖、自賠責はノースリーブ、裁判はタンクトップ以上!? よく違いが生じる障害 👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い 障害給付の申請を提出すると、担当者から顧問医の診察するよう要請が入ります。およそ月1~2回、各地の労基署の第〇曜日に顧問医がまとめて診察をしているようです。診察者が多い場合や、予定が合わないと翌月になりますので、その分審査が遅れます。この診察には弁護士でも同席できませんので、事前に症状を文章にしておき、持参します。もちろん、労災側に専用の用紙にて記載を求められることもあります。先に自賠責で妥当な等級がついている場合、その認定票や診断書・検査サマリーなどを提出することも多いものです。労基の職員によると、それらは審査書類に当たらないものの、それなりに参考になるそうです。
さて、被災者さんが診察に臨む前に、諸々のアドバイスをしています。多くの場合、認定されるべき等級は固まっています。その等級に合致するよう、穏当に済めば良いと思います。ところが、顧問医によって、それが大きくぶれる経験もありました。たいていの顧問医は、労災の認定基準に照らして診断内容をまとめますが、やはり、診断権という権力を持った医師、勝手な診断を下すこともあるのです。労基の職員によると、はっきり言いませんが、”個性的すぎる”医師もいるそうです。そのような先生に当たってしまうと・・結果が読めません。医師の判断は、つまり、人間の判断ですので、医師の独自見解が入ってしまうことがあるのです。その点、画像審査を主眼とする自賠責保険の方が、ぶれを感じません。
被災者さんに最後のアドバイスとして、顧問医の当たり外れを説明することになります。文字通り、最後は「GOOD LUCK」を祈ることになります。
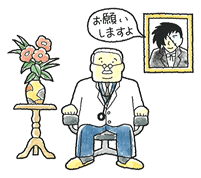
交通事故の交渉場面の多くは、保険会社VS被害者の構図です。被害者が弁護士を雇って、交渉にあたることがありますが、逆に保険会社が弁護士を雇って、(いえ、契約上は加害者が雇うことになりますが、たいてい保険会社から紹介された弁護士です)交渉にあたることがあります。 この保険会社から紹介された弁護士は、保険会社の顧問弁護士、あるいは正式名称ではありませんが、協力弁護士と呼ばれています。保険会社は賠償金を支払うにあたり、保険会社の基準内で、できれば低額に収めたい立場です。協力弁護士はそれを擁護する事がミッションになります。加害者側が代理人となる協力弁護士を立てる場面は、被害者の交渉態度に問題があるケースや、被害者側の希望する賠償金に折り合いがつかない場合でしょうか。
この協力弁護士は保険会社の擁護者ですが、逆に被害者側の代理人になれば保険会社と戦うことにもなり得ます。 長年、議論になっていることは・・これって双方代理?、ダブルスタンダード? 節操がない? などの意見です。硬派な弁護士は、立場上、旗色を鮮明にするため、どちらかに専念しているようです。一方、代理人ですから、依頼者がどちらであっても、受任すればその立場で、誠実に業務遂行することになる・・これに、何ら問題はないとも言えます。弁護士は法律上の代理権を持った「依頼者の代理人」ですので。同一の事故で、双方から依頼を受けること(双方代理)はできませんが、別の事件であれば違法になりません。あくまで一方からの依頼に専念するかどうか、これは弁護士事務所の方針に過ぎないことで、どちらの考えが正しいかを問うているわけではありません。 さて、被害者さんが弁護士を選ぶ場合、どちらの弁護士を選びたいと思いますか? やはり、弁護士の立場が心配です。この先生は、平素から仕事をもらっている保険会社に対して、「ガチで戦ってくれるのか?」です。保険会社は民間企業・営利企業です。弁護士事務所も同じです。つまり、被害者の相手が協力先の保険会社となれば、取引先に弓引く構図になってしまいます。もちろん、顧問や協力先の保険会社なら、その被害者の依頼は引き受けないことになるはずです。逆に、取引のない保険会社が相手なら、引受OKとなりますでしょうか。ただし、将来、この保険会社からの顧問契約や、仕事の依頼に繋がらないことにはなると思います。保険会社からの顧問料や依頼は、弁護士事務所の経営上、安定収入になります。言わば有力な顧問契約先になります。これらの判断も、弁護士事務所の経営方針次第となります。
かつて、ある弁護士に、この問題について見解を聞いたことがありました。協力関係にある保険会社であっても、被害者から依頼を受ければ正々堂々戦うそうです。なんでも、その保険会社の担当者から「先生、敵対する被害者からの依頼でも忖度せずビシビシ来て下さい。弊社は弁護士の立場を尊重しています」と言われたそうです。一見、フェアなやり取りに聞こえます。この弁護士先生はそれを受けて安心、双方の依頼を受けることに胸を張っています。しかし、長年、保険会社勤務&代理店経営をした秋葉は、この保険会社担当者のセリフが、「(熱湯風呂を前に)押すなよ、いいか、押すなよ」と聞こえてしまいます。これは、ひねくれた勘ぐりではなく、民間企業には”(元請・御店には逆らわない)=商売の仁義”が根底にあると思うからです。

長年、交通事故業界、それも被害者様のご相談を担当していますと、本当に助けるべき被害者なのか迷うことがあります。相手保険会社の塩対応、あるいは横暴な対応に憤慨して、時には相手側に弁護士を入れられた被害者さんが、救済を求めて相談にいらっしゃいます。もちろん、丁寧に拝聴した上で、対応策を検討します。しかし、時には、道徳的に助けられないケースもあります。
立場上、被害者様の窮状を救うことが前提です。弁護士のみならず私共も、被害者様の言い分を信じる事からスタートすべきです。それが士業者としての基本だと思います。しかし、残念ながら被害者の中には不道徳な方も含まれています。例えば、事実と違う損害を訴える不正請求、嘘の症状を装う詐病、暴力的な言動・態度をする方も含まれます。このような不道徳が明らかである場合、ご依頼を受けることはできません。職業倫理として当然なことです。
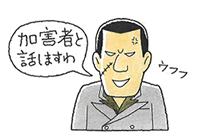 ただし、問題ある依頼者か否か、容易にわからないことの方が多いと思います。神経質になり最初から疑ってかかる姿勢、これも職業倫理に反するものですが、盲目的にご依頼を引き受ける事も罪なのです。不正な請求者を擁護する事務所は、保険会社から悪徳のレッテルを張られます。それこそ、今後にわたって正当な被害を訴える被害者さんを受任しても、「あの何でも引き受ける事務所の依頼者」として色眼鏡、疑られてしまう結果になるのです。
ただし、問題ある依頼者か否か、容易にわからないことの方が多いと思います。神経質になり最初から疑ってかかる姿勢、これも職業倫理に反するものですが、盲目的にご依頼を引き受ける事も罪なのです。不正な請求者を擁護する事務所は、保険会社から悪徳のレッテルを張られます。それこそ、今後にわたって正当な被害を訴える被害者さんを受任しても、「あの何でも引き受ける事務所の依頼者」として色眼鏡、疑られてしまう結果になるのです。
ご相談を受けて、訴えの正当性を検討するに悩ましいことは多々あります。これも士業事務所の宿命と思っています。
少し古い統計ですが、身体障害者手帳を取得した方の世代別の統計です。当然に年齢に応じて増加しており、70歳以上では全体の6割を超えています。外的なケガと対比すると、内部的疾患の割合が増加傾向のようです。それは、慢性疾患と、それに加えて高齢化が影響していることを示しています。 <LIFE&MONEYさま記事より引用>
「所持者はどのくらい?」 ~ 「身体障害者手帳」の所持者数と傾向を確認
厚生労働省が公表している「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」をみていきましょう。
※ この調査は、前回2016年に行われて以来6年ぶりの実施であるため、2022年と2016年との比較である調査結果となります。 【2022年】障がいの種類別にみた身体障害者手帳所持者数について ※( )内は全体の割合
・総数:415万9000人(100.0%) ・視覚障がい:27万3000人(6.6%) ・聴覚・言語障がい:37万9000人(9.1%) ・肢体不自由:158万1000人(38.0%) ・内部障がい:136万5000人(32.8%) ・不詳:56万2000人(13.5%) 障がいの種類別にみた身体障害者手帳所持者数について、ポイントを2つにしぼって解説します。 続きを読む »
自賠責保険の後遺障害審査で必須となる画像、主にレントゲン、CT、MRIなどですが、これを集めるのに一苦労があります。病院によっては、患者自らの請求ですら、快く応じてくれません。提出先や理由を聞かれ、申請書を書くこともあります。ただ、フィルムの時代から比べれば、現在はCDやDVD-ROM化していますので、病院側の手間は減ったと思います。
また、別の問題として、その価格があります。パソコン操作でソフトに焼くだけの手間、それも15分もあれば完了するものです。手間賃に等しいものと思います。およそ500円~2000円が多かったと思います。クリニックですと、純粋にソフト代として10円~100円だけ、中には0円もありました。一方、医療情報の開示にあたるので、カルテ開示同様、厳密なルールのもと、開示費用に扱いで5000円~数万円がありました。それなりの規模の病院で、費用名目や価格も決まっている印象です。
 前置きが長くなりましたが、私共のような業者、もちろん保険会社からの請求も多いと思いますが、それらに対して異常に高額な請求をする病院が存在します。確かに昔はレントゲンフィルムをコピーする手間があり、フィルム代も安くはないので、画像1枚=1000円程度は普通でした。しかし、現在はディスクに焼くだけ、パソコンのひと操作で完了するのです。それを、未だに画像1枚当たり=〇〇円で計算する院が残っています。レントゲン数枚ならまだしも、CTやMRIは言わば連続写真のようなもので、一部位の画像が数十枚になるのです。数度にわたり検査したとすれば、100枚を超えることは珍しくありません。
前置きが長くなりましたが、私共のような業者、もちろん保険会社からの請求も多いと思いますが、それらに対して異常に高額な請求をする病院が存在します。確かに昔はレントゲンフィルムをコピーする手間があり、フィルム代も安くはないので、画像1枚=1000円程度は普通でした。しかし、現在はディスクに焼くだけ、パソコンのひと操作で完了するのです。それを、未だに画像1枚当たり=〇〇円で計算する院が残っています。レントゲン数枚ならまだしも、CTやMRIは言わば連続写真のようなもので、一部位の画像が数十枚になるのです。数度にわたり検査したとすれば、100枚を超えることは珍しくありません。
かつて、フィルムが廃れつつある中、ある大学病院に画像を依頼したところ、「1枚あたり1000円ですので、フィルムコピー代は、えーと合計246000円ですが、払えますか?」との回答でした。ほとんどの患者は諦めるはずで、それを期待したような物言いでした。数年前まで、この有名大学病院はディスクに焼かず、(CTやMRIまでも、わざわざ観ずらい)フィルムの対応で、その高額な費用で困っていました。現在はそのような意地悪はしなくなり、ディスク1枚=2000円位で焼いてくれるようになりました。弊所では、この医事課の責任者に、さんざん苦言し続けたかいがあったと思っています。
最近になっても、個人経営のクリニックで、このようなフィルム時代の名残のような1枚=〇〇円対応がありました。ディスクに焼くだけの手間で、例えば18枚のレントゲンを(おそらくワンクリックの手間なのに)、1枚=2000円+消費税、さらにディスク作成費用加算と言った、ひどい請求がありました。画像検査専門の病院では、放射線科の読影報告書付ながら、ディスク1枚のコピー代は2~3千円です。ただディスクに焼くだけを、いくら自由診療だからと言って、病院側の悪意すら感じます。 このように、自由診療扱いをいい事に、めちゃくちゃに価格幅があることは、業界全体の不審になるものと思いま。つまり、健保治療のようなガチガチの点数制限はないまでも、ある程度の価格相場、推奨金額を決めて頂けないものか、医師会に対して切に願っているのです。
私共の業界では、当たり前に使用する専門用語で「ROM」があります。これは医療、とくに整形外科において、医師はもちろん理学療法士・作業療法士などを含め、日常用語レベルです。また、介護関係者にも通じます。 改めて、説明をしておきましょう。 関節可動域をROMと略します(Range of Motion)。これは、体の関節が痛みや傷害などが起きないで運動できる範囲のことです。関節可動域は、どれだけ動くかを角度で表記します。関節可動域は、患者に必要なケアやリハビリ計画を立てるために重要な計測数値です。関節を中心とした身体機能を評価することで、障害の程度や困難となる生活を把握し、改善目標を立てるために役立ちます。

計測する分度器をゴニオメーターと呼びます。秋葉事務所では4種のゴニオメーターを常備しています。









