頚部神経症状と言っても、その症状は多肢に渡り、単なる頚部痛に留まらず、上肢のしびれ、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感、不眠・・人によって違います。ひとたび、それらの症状に陥れば、半年や1年では収まらず、ぐずぐずと続きます。そして、不安から、様々な診療科を回ることになり、つまり、病院からはプシコ扱い(心療内科へ紹介)されてしまいます。
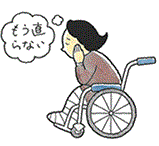
そうなると、症状の一貫性と信憑性を重視する14級9号の認定は遠のくばかりです。そうならないよう、適切に誘導することが秋葉の仕事ですが・・本件は、迷走状態からのスタートでした。初回申請で等級が取れたら良いのですが、再請求(異議申立)での認定を覚悟で進めました。顛末は以下の通り。

二度手間ですが、再請求での勝負を覚悟することもあります
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・千葉県)
【事案】
自動車にて直進中、交差点で信号無視の自動車の側突を受けたもの。半回転してポールに衝突・停止した。脳震盪で朦朧とする中、救急搬送されたが、以降、頭痛はじめ上肢しびれなど神経症状が続いた。
【問題点】
治療が長引く中、相手保険会社から半年で治療費が打ち切られ、健保で治療継続中であった。本来、半年経っていたので打ち切りのタイミングで後遺障害の申請をすべきところ、症状に合わせて複数の病院へ通っていた。ドクターショッピング扱いされるような迷走案件となってしまった。
それでも、治療経緯の説明書を加え、丁寧に診断書類を揃えて申請したが・・「初回=非該当」の嫌な予感は当たり、再請求での勝負となった。
【立証ポイント】
救急先とリハビリ先に追加書類をお願いした。記載にあたり、なるべく頚部由来の神経症状に絞って、症状の一貫性と信憑性を示した。
二度手間覚悟の申請によって、時間はかかったが14級を確保して弁護士に引き継いだ。







