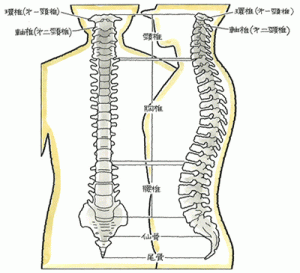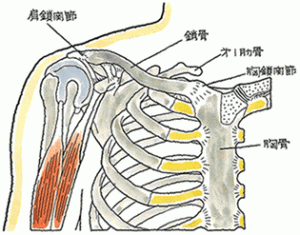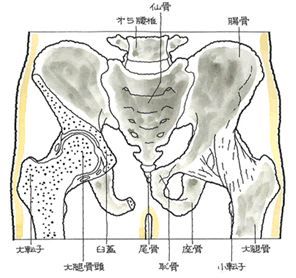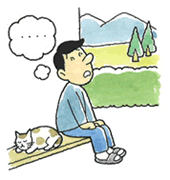優遇措置 を続けます。
<公共交通機関>
① 東京都精神障害者都営交通乗車証の交付
東京都では、都内在住の手帳の所持者を対象に東京都精神障害者都営交通乗車証を発行しています。24区地域は都電、都営バス、都営地下鉄、舎人ライナーの乗車が無料となります。
この乗車証の発券は特定の駅でできます。市町村地域は各市町村窓口へ問い合わせます。
② 路線バスの運賃半額割引
(1) 対 象 者
東京都が発行する、写真が貼付された手帳をお持ちの方(ご本人のみ)介護人は、割引対象になりません。 他の道府県から交付された手帳をお持ちの方は、対象になりません。
(2) 適用範囲
東京都内を運行する一般路線バスの都内区間。東京都内で乗車し、かつ東京都内で降車(下車)する場合にのみ適用されます。 高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス等は除きます。
(3) 割引運賃
運賃が半額になります(10円未満四捨五入)。定期券は割引になりません。 小児運賃が適用される方で手帳をお持ちの方は、小児運賃が半額となります。(例)運賃210円の場合 → 110円(小児60円)
(4) 利用方法
運賃支払の際に、手帳の写真が貼付されたページを開いて、乗務員に提示します。
<生活補助>
① 生活保護の障害者加算(1級及び2級のみ)
生活保護を既に受給している方のうち、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診療を受けてから1年6か月以上過ぎている方で、1級又は2級の手帳をお持ちの方は、障害者加算がつくことがあります。
申請はお住まいの地域を所管する福祉事務所です。
② 都営住宅の優先入居、使用承継制度及び特別減額(特別減額は1級及び2級のみ)
(1) 優先入居
5月及び11月の募集は、一部の地区で優遇抽選制度があり、一般世帯に比べて当選倍率が5倍(3級の方)又は7倍(1級又は2級の方)になります。8月及び2月の募集は、ひとり親、高齢者、障害者等の限定募集となっています。
窓口は東京都住宅供給公社募集センターです。
(2) 使用承継制度
都営住宅の使用承継は原則として名義人の配偶者のみですが、承継しようとする方又は同居者が手帳をお持ちの場合、名義人の三親等親族まで承継することができます。ただし、収入基準等、一定の条件があります。
窓口は東京都住宅供給公社お客さまセンターです。
(3) 特別減額
既に入居している1級又は2級の方で、所得が一定額以下の場合は、使用料の特別減額が受けられます。
窓口は各地区を管轄する窓口センターです。
続きを読む »