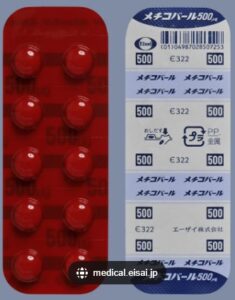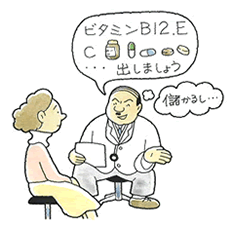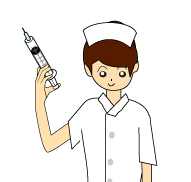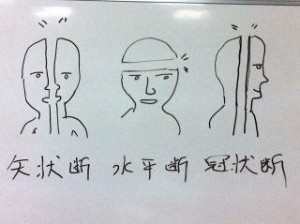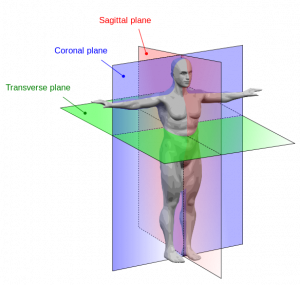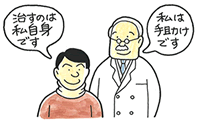交通事故外傷で回復の進行を阻むものに「浮腫」があります。浮腫とは簡単に言うと「むくみ」です。原因はリンパの滞りで、一般的にはさまざまな内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍)の兆候と言われています。また局所性浮腫の原因には深部静脈血栓症等があります。
交通事故外傷で回復の進行を阻むものに「浮腫」があります。浮腫とは簡単に言うと「むくみ」です。原因はリンパの滞りで、一般的にはさまざまな内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍)の兆候と言われています。また局所性浮腫の原因には深部静脈血栓症等があります。
リンパ液の流れは、筋肉のポンプ作用と外部からの刺激に委ねられています。重力にまかせて下肢には流れていきますが、下肢から上に戻りにくいのがリンパの特徴です。交通事故で下肢を骨折して長期間ギブス固定を続けた、骨癒合が得られるまで動かさず安静にした・・・すると下肢の筋肉を使う頻度が減るのでリンパの流れが悪くなり、浮腫を併発します。
浮腫が受傷後も長く残存する場合、痛みからリハビリの進行を妨げてしまいます。その結果、筋肉が減ってしまうと、さらにむくみやすくなるという悪循環に陥ります。浮腫は男性より女性に多くみられます。これは筋肉量の差がある為です。早期のリハビリで下肢の筋肉を鍛える必要があります。またむくみのある部位は冷えますので、血液循環も悪くなり、ますますむくみがひどくなります。これを防ぐには冷やさないこと、具体的にはお風呂で温めることが推奨されています。
浮腫が直接、後遺障害と認められることはありませんが、リハビリを阻害するものとしてやっかいな存在です。骨折後の関節可動域制限の残存にも一定の影響、原因となるはずです。しかしながらら自賠責保険は関節可動域制限の原因を「本人のリハビリ不足」とばっさり切り捨てます。骨癒合が良好であるにも関わらず、高齢や浮腫の併発でリハビリが十分にできなかったために、関節可動域制限が残存した・・・このような原因であっても自賠責の審査基準に阻まれます。浮腫の併発で障害がより残存した場合、これは個別具体的な症状として評価されるべきと思います。現状では訴訟上での主張になるかと思います。



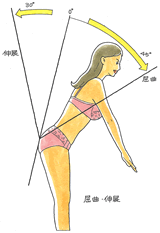

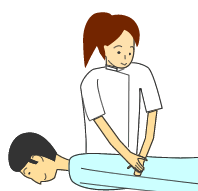
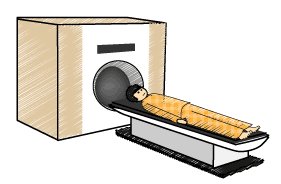
 ロキソニン、リリカにつづきトラムセットについて。トラムセットも痛みをおさえるお薬です。慢性疼痛や抜歯後の痛みに用います。私はこの3薬を勝手に「痛み止め御三家」と呼んでいます。
【適用】
ロキソニン、リリカにつづきトラムセットについて。トラムセットも痛みをおさえるお薬です。慢性疼痛や抜歯後の痛みに用います。私はこの3薬を勝手に「痛み止め御三家」と呼んでいます。
【適用】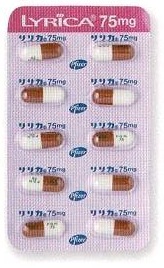
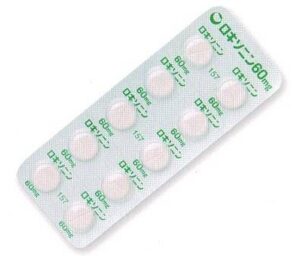 もはや、痛み止めの定番となりました。当然に交通事故外傷でも処方されることが多い薬です。解熱鎮痛消炎剤で、第一三共や後発医薬品として各社から発売されています。かつては劇薬で医師の処方箋を要したが、現在は劇薬指定を解除され、処方箋がなくとも後述のようにドラッグストアなどでも入手できるようになりました。一般用医薬品としてはロキソニンS錠が第一類医薬品として発売されています。
もはや、痛み止めの定番となりました。当然に交通事故外傷でも処方されることが多い薬です。解熱鎮痛消炎剤で、第一三共や後発医薬品として各社から発売されています。かつては劇薬で医師の処方箋を要したが、現在は劇薬指定を解除され、処方箋がなくとも後述のようにドラッグストアなどでも入手できるようになりました。一般用医薬品としてはロキソニンS錠が第一類医薬品として発売されています。