A君は早速、会社の事務に「自損事故保険が出るそうなので、手続きお願いします」と願い出ました。しかし事務の担当者も、「それ何ですか?良くわからないので・・・」困ったようです。そこで上司に同じようにお願いしても、「上に言っておくよ」と言いましたがそれっきり。会社はなんだかよくわからない保険だし、労災でA君を補償したのだし、障害で会社を辞めるようだし、・・・親身になってくれないのです。
仕方ないので私が会社の担当者に説明を申し出ました。まずは会社の事務、続いてその上司に説明、すると会社の弁護士がでてきて、「労災で十分でしょ」と頓珍漢な対応、まったく自動車保険を知らないようです。まるでA君が会社相手に訴訟を起こそうとしているとでも思っているのか、変に力が入っています。
弁護士を相手にしていてもダメなので、会社の保険を担当している代理店さんに話を通しました。自損事故保険については、さすがに代理店、多少(多少では困りますが・・)知っています。「早速保険会社に聞いてみます」と返答、そしてN保険会社も「出る可能性があります」との返答になりました。
しかしさらに障壁、会社の部長が「会社に許可もなく勝手に保険を使っては困る!」そして「掛け金が上がるのでは?」と横槍です。会社には再三請求のお願いをしています。そしてすでに対人・対物賠償の適用・支払となっており、追加請求が出ても来年の等級ダウン、掛け金UPは決まっています。
この部長にしっかり説明し、「会社には一切迷惑がかかりません」と約束し、理解を得ました。これでようやく保険の請求手続きです。 保険金請求書と後遺障害診断書を提出しました。
障害の内容から後遺障害保険金10級280万円、入院1か月で18万円、通院40日で16万円、合計314万円となるはずです。しかしここに至ってもすんなり支払ってくれません。
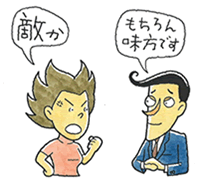 N保険会社 担当者:「自損事故保険は相手の自賠責保険からの支払のない場合に支払われます。したがって相手にも過失の可能性があるので、ごにょごにょ・・・」
N保険会社 担当者:「自損事故保険は相手の自賠責保険からの支払のない場合に支払われます。したがって相手にも過失の可能性があるので、ごにょごにょ・・・」
続きを読む »



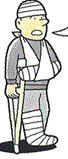


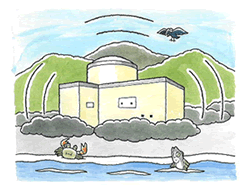 {A4}
{A4} 
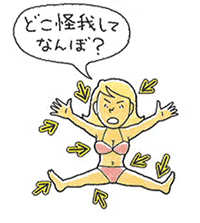 事故後、まず請求したい保険です。明日は肝心の②後遺障害保険金を解説します。
事故後、まず請求したい保険です。明日は肝心の②後遺障害保険金を解説します。





