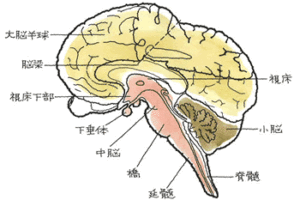
頭部を受傷、脳にダメージを負った結果、認知障害や記憶障害、性格変化、身体の麻痺などの後遺障害をもたらすのが「高次脳機能障害」です。10年前までは、その後遺障害等級の基準が整理されていませんでした。今でこそ知られるようになったこの障害ですが、裁判の実例にかなりバラつきのある分野です。それは、画像や計測値だけではなく、日常生活の変化を正確に観察・申告するといった要素も加わるからです。そして、立証も様々なハードルに直面します。
① 事故直後の意識障害の様子がしっかり記録されているか?
意識不明、昏睡状態と記録されていれば問題ないですが、記録が空欄もしくは、混濁程度に書かれると、障害そのものが認定されなくなります。ここで「意識清明」と書かれたら高次脳機能障害は「非該当」濃厚となります。これを覆すのは絶望的です。
② 運ばれた病院が高次脳機能障害に対応できているか?主治医の知識・理解があるか?
急性硬膜下血腫等で手術を行えば、主治医も後遺症の可能性を認識します。しかし、レントゲンだけ撮って「骨には異常ないですね」、CTでも「脳挫傷はないです」、もしくは「わずかです」となると、1週間で退院?なんて例もありました。その場合は、主治医も(外来で何度も診察を重れば別ですが)後遺症の認識を持ちません。
何より、脳のダメージは、経過的に画像診断しなければいけません。ダメージを受けた脳の特徴である脳委縮や脳室拡大は、徐々に進行して、3か月後に顕著になるケースもあります。当然、この病院での検査は無理です。設備のある病院での検査のやり直しが必要となります。
③ そして、検査だけやってくれる、都合の良い病院はほんとんどありません。
事故後1年。家族は、回復の願いを込めて被害者に接していますが、忘れっぽい、外出すると迷子になる、家電の操作ができない、会話が成り立たない、キレやすい、趣味に興味を示さなくなった、無気力・・・そして多くの場合、本人に障害の自覚がない。
この段階で等級認定に入るのですが、① ②のつまづきがあると、立証作業は困難を極めます。何故なら、十分な検査設備・人員を備える病院は日本に数えるほどで、設備があったとしても、「治療した病院の検査が不足していましたらから、検査だけやって下さい」では、ほとんどの病院が嫌がります。強力なコネでもない限り、遠まわしに断ります。その理由は、単に治療での収入がないのに検査だけは損、保険適用の問題、様々な裏事情が絡みます。
上記は実際に経験した例です。いかに早めにご相談頂かなければならないか、おわかりと思います。回復への希望、主治医への気遣い、保険会社担当者への過ぎる期待・・・ご家族の方は、これらから距離を置いて冷静に考えることが必要です。
次回 ⇒ 後遺障害認定への道






