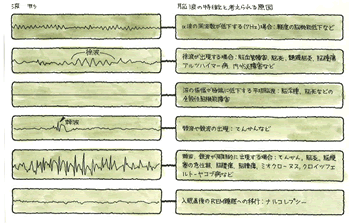今回は、少し面白い治療の話をしていきます。普通に今日の内容でお金を取りセミナーを開ける位のお話だと思います。お金を取るなら相当深いところまで掘り下げますが、今回は分かりやすくを目標に!治療といっても、柔整師の施術ですけどね!内容としては、精神的疾患に対して手技によるアプローチ。整骨院で働いていると色々な患者さんを診る事になります。よく観察をすればするほど、深い所まで診る事になります。
今回のテーマなのですが、実際整骨院に長く通う患者さんの半数以上は精神的な疾患を抱えている方と感じます。(あくまで私の感覚であり、残り半数弱は普通です。)程度は様々ですが、完全に鬱の患者さんもいれば、躁鬱の方もいます。整骨院に長く通う傾向にあるのは、精神的に弱い方が多い傾向にあると感じます。一見は普通そうだけれど目に元気が無い。もう心身ともに疲れが限界。と言う人が集まります。
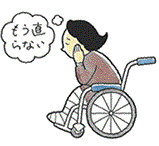
完全に鬱の方に対しては毎日マイナスの発言を聞いたり、弱音を聞いたりしているとこちらの精神も疲労しますので、半分は聞き流したりと工夫が必要です。約5年現場で患者さんを診てきましたが、気持ちが落ち込んでしまっている患者さん・精神的疲労。慢性疲労がひどい人。全員に共通点があります。それは、ほぼ全員呼吸が浅いことです。極端な例えですが、普通なら一呼吸で肺に入る空気が100だとすると、大体60かそれ以下と言う方がほとんどです。呼吸が浅いと、身体の酸素濃度が薄くなります。酸素濃度が薄いと倦怠感も出ますし、頭の回転も落ち、ぼーっとします。細胞の活性も低くなり、身体の回復力も落ち疲れが一向にとれません。これが続くと、気持ちが滅入ってきて色々な事が重なると、心の中の何かが崩れてしまうのだと思います。
ただ問題なのが、呼吸を深くしようとしても、肺を包む肋骨が動かず、膨らまなくなってしまっていることが多いです。肋骨の間に肋間筋と言う筋肉があり、これが作用しないと肋骨も動かなくなります。この肋骨の動きをよくするために、肋間筋の治療・肋骨のモビリゼーション手技を用いる事で、肋骨の動きが良くなります。そうすると肺が膨らむスペースが出来ます。体内の酸素濃度が上がり、自己回復力が向上するのです。この治療+胸椎アジャストをしっかり決める事ができると、胸椎から出る肋骨のROMがさらに広がり、さらに胸椎に付着する交感神経幹のストレスを一気に取り除き、身体を一瞬で副交感神経優位に転換させることが出来るのです!
上記治療に+αで行うとしたら、実際に、呼吸に使う筋肉、主に横隔膜をはじめとした筋肉を治療します。これだけで相当呼吸が深くなり、患者さんの身体の負担を取り回復力を上げる事ができるのです。勿論、横隔膜の機能が徐々に低下していく場合もありますが、交通事故被害者の患者さんも大半がそのような状態になっている印象でした。
以前、参加した医師との勉強会での内容なのですが、交通事故・スポーツ外傷などの高エネルギー外傷が起こると一瞬で横隔膜・肋間筋が強縮し、肋間のROMが悪くなり呼吸が浅くなる。ついでに交通事故だと胸椎にまでムチウチが及び、胸椎から発生する肋骨の可動が落ちると習った事があります。あくまでも一つの考え方として参考程度ですが、施術の視野が広がる一つだと思います。
このように、簡単な治療一つでも非常に有効な効果が期待できるので、いつか整骨院と精神科医の連携が来る日があってもいいのにと思っています。精神科のお医者さんは、精神疾患は薬で治すもの、と言う固定概念があり、肋間筋やら胸椎やらに関心が無い方が多いと聞きました。また柔整師は柔整師で、相変わらず薬なんか使ったら余計悪くなる!等と頑固に主張します。そんなことよりお互いの関心が深まり、良いとこ取りをした治療の方が必ず患者さんは救われると思うんですが、いつか連携が訪れる事を願うばかりですし、そんな橋渡しができたらなとも思います。
勿論このような治療も正解の無い世界。私が交通事故被害者様に対し安易な口出し等することは有りませんし、そこばかり見ると他を見落としますので、少しでも観察する視野を広げる一つとしていきたいと思います。もし柔整師が読んでたら、必ず治療の幅が広がる良い記事だと思うんですが、いかんせん柔整師はプライドが高く素直じゃないからなー。
では、長くなりましたが終わりです。ありがとうございました。
なかなか、病院と整骨院の連携はうまくいきません。 →整形外科Vs接骨院・整骨院 医師と柔整師が少しでも歩み寄れる環境になるためにも、柔整師がきちんとする必要がありますよね~



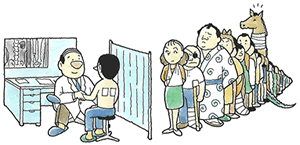


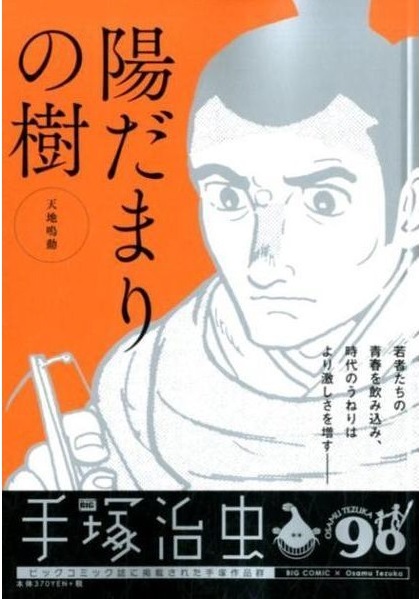 話を戻しますが、現代であっても、親が医師であれば、若手医師にとって家にベテラン医師がいる恵まれた境遇となります。あらゆる職業で、世襲そのものは決して悪い事ではないと思います。私の解釈では、不正をしてでも(つまり、能力が担保されない子に)無理に世襲させることが諸悪の根源であり、機会均等は原則、ルールは常にフェアであるべきと思います。能力が担保されない医師に苦労させられるのは患者です。私達も仕事柄、問題のあるドクターを何度も目にしています。では、一切の不正を廃し、跡継ぎが医師試験に受からない院は廃業させるべきでしょうか・・。
話を戻しますが、現代であっても、親が医師であれば、若手医師にとって家にベテラン医師がいる恵まれた境遇となります。あらゆる職業で、世襲そのものは決して悪い事ではないと思います。私の解釈では、不正をしてでも(つまり、能力が担保されない子に)無理に世襲させることが諸悪の根源であり、機会均等は原則、ルールは常にフェアであるべきと思います。能力が担保されない医師に苦労させられるのは患者です。私達も仕事柄、問題のあるドクターを何度も目にしています。では、一切の不正を廃し、跡継ぎが医師試験に受からない院は廃業させるべきでしょうか・・。
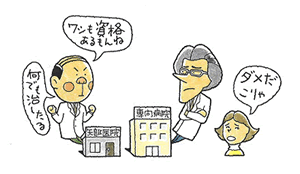
 続きを読む »
続きを読む » 続きを読む »
続きを読む » 続きを読む »
続きを読む »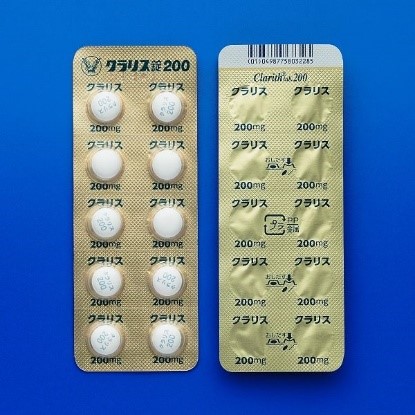 続きを読む »
続きを読む » 続きを読む »
続きを読む »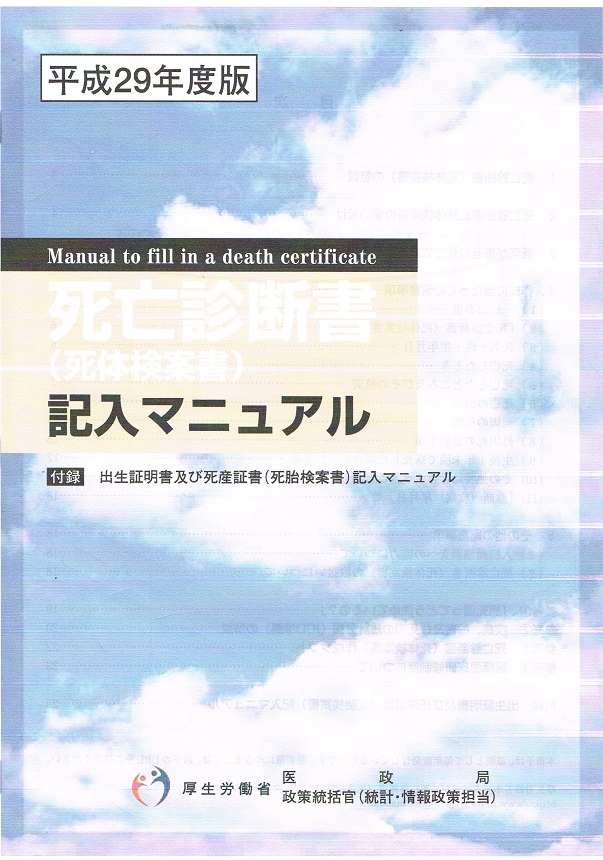 (1)死亡診断書、2つの意義
(1)死亡診断書、2つの意義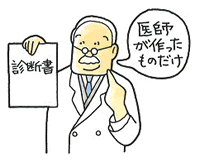


 【薬理】
【薬理】