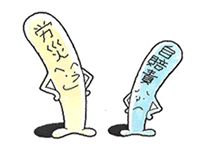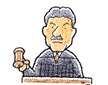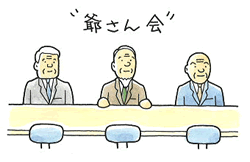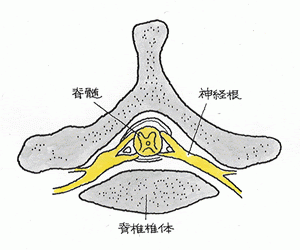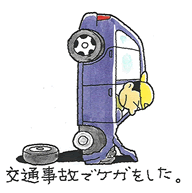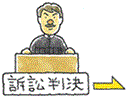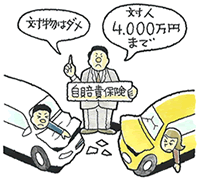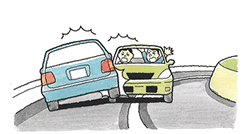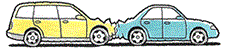交通事故の発生件数は、警視庁の発表によれば、平成24年は66万5,138件、25年は62万9,021件、26年は57万3,842件、と減少傾向にあります。
そして、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、交通事故による死亡者、それによる自賠責保険死亡支払件、が年々減少してきています。また、交通事故の負傷者も年々減少しています。これらのことから、交通事故の発生だけではなく、交通事故による重傷者及び重傷になるレベルの大きな交通事故が減少してきているといえます。
しかし、支払われる保険金は、平成23年度では8,054億円、24年度では8,000億円、25年度では8075億円、とほぼ変化がありません。また、これに対し、自賠責保険傷害支払件数は、平成23年度では1,155,536件、24年度では1,154,370件と若干減少しましたが、25年度では1,185,334と増加しております。なお、平成21年度では1,117,373件、22年度では1,136,876件であったことから、全体的にみて年々増加傾向にあるといえます。
交通事故発生数と交通事故による死亡者・重傷者が減少しているにもかかわらず、他方で保険金の支払件数が増加し、支払保険金に変化がありません。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。
(1)後遺障害認定の増加について
上記した自賠責保険傷害支払件数には、後遺障害が含まれています。
この点、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)の後遺障害支払件数の推移によれば、後遺障害支払件数は年々減少しております。また、年間の後遺障害認定件数は、全体の傷害交通事故のうち約5%であり、この数値に大きな変化はありません。
したがって、後遺障害認定が原因で支払保険金が増加したわけではなさそうです。
(2)治療費や施術費の増加について
損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、総治療費及び総施術費の増加及び件数が増加しております。ただ一方で、平均治療費、施術費の変化はほぼありません。 よって、治療費・施術費の値上げは起きていないようです。
※ 平均施術費については、平成24年度では315,683円なのに対し、平成25年度では311,168円と減少しておりますが、平成21年度から全体的にみてあまり変化がないと考えます。
上記した通り、交通事故の負傷者が減少しているにもかかわらず、総治療費及び総施術費の増加及び件数が増加しているのは、交通事故負傷者の内、多くの病院や接骨院等へ通院する者の数が増加していると考えます。
※ なお、治療期間・施術期間が少しずつ増加しており、通院慰謝料等の支払数が多くなるともいえますが、平均して1日ずつしか増加しておらず、少数といえるので、これが直接的な原因と解することは出来ません。
交通事故の負傷者は、多く通院する必要のある者から、軽傷で、数回通院すればいいような者まで様々です。昔では、交通事故負傷者は後遺障害の申請をする以前に、多くの通院をしていませんでした。通院する者が増加しているのは、本来多く通院する必要のない者まで多く通院するようになってきているといえます。何故なら、交通事故の負傷者数そのものが減少すれば、その分通院が必要な者も減少するはずなのに、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、上記した通り交通事故の負傷者数が減少しているにもかかわらず、病院や施術所へ通う人数が増加しているからです。
なお、最近になって、交通事故の負傷者のすべてが多く通院する必要のある者であった可能性が全くないわけではありませんが、非常に低く、現実的ではありません。では、なぜ交通事故負傷者が全体的に多く通院するようになったのでしょうか。
結論として、交通事故の負傷者が後遺障害の申請の方法をインターネットや書籍等で簡単に知ることが出来たことにあるとみています。
特に、交通事故負傷者の診断名のうち、約60%がムチウチであり、ムチウチの後遺障害申請について調べた者は、大抵、通院日数を増やそうと考えます。この点、ここ最近の相談会でもそのような者が増加しているようにみえます。
しかし、本来後遺障害というのは生涯にわたって治らないレベルの者に認められるのであって、軽傷者に認められるものではありません。上記した通り、交通事故による重傷者は減少しています。このことから、軽傷者があえて後遺障害を狙っているようなケースが増加しているようにみえます。
私達(連携しているNPO法人や弁護士事務所を含む)は、すべての交通事故被害者に対して、後遺障害の申請をアドバイスしておりません。後遺障害が認められる者とそうでない者とを見分けた上で、それぞれの被害者に対して最もよいと思われる交通事故の解決の道筋を模索し、アドバイスをさせて頂いております。そして、後遺障害が残存しないような者については、契約を結ぶことは原則致しません。何故なら、必要ないからです。
無駄に契約を締結して無駄にお金の支払わせて無駄に保険金を使うようなことは、個人レベルでも、社会レベルでも損失にしかなりません。
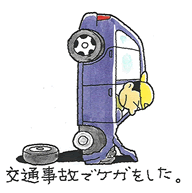
続きを読む »
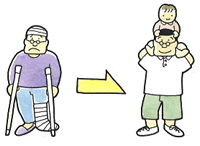 常識的には、後遺障害といえば、植物人間や手足の切断を連想しますが、保険のプロである皆様は、「一生を棒に振ってしまうモノだけが後遺障害でない」ことに、認識を新たにする必要があります。
常識的には、後遺障害といえば、植物人間や手足の切断を連想しますが、保険のプロである皆様は、「一生を棒に振ってしまうモノだけが後遺障害でない」ことに、認識を新たにする必要があります。



 ←誰だ?
TFCC損傷は、どんだけ~?
←誰だ?
TFCC損傷は、どんだけ~?