【事案】
自動車で走行中、交差点で信号無視の自動車と出合い頭衝突、自動車は横転した。頚部から右上肢の痛みや頭痛が続いた。
 【問題点】
【問題点】
このような受傷機転であれば、後は治療経緯から認定は容易に感じた。しかし、検査の都合や病院が合わない為に転院を繰り返し、結局8か所の通院となった。つまり、書類・画像収集が大変でした。
【立証ポイント】
最終的な治療先の医師の協力を得て、的確に後遺障害診断書を記載頂いた。問題なく初回申請で通った。
(令和6年7月)
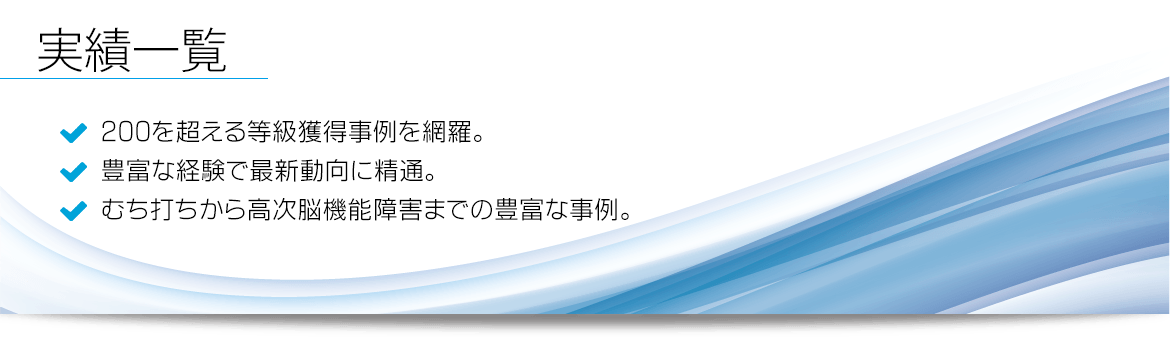
【事案】
自動車で走行中、交差点で信号無視の自動車と出合い頭衝突、自動車は横転した。頚部から右上肢の痛みや頭痛が続いた。
 【問題点】
【問題点】
このような受傷機転であれば、後は治療経緯から認定は容易に感じた。しかし、検査の都合や病院が合わない為に転院を繰り返し、結局8か所の通院となった。つまり、書類・画像収集が大変でした。
【立証ポイント】
最終的な治療先の医師の協力を得て、的確に後遺障害診断書を記載頂いた。問題なく初回申請で通った。
(令和6年7月)
【事案】
自転車で走行中、左方から右折してきた車に衝突され受傷。初回申請で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。 【問題点】
骨癒合は良好であったが、抜釘後も疼痛と肩の可動域が回復せず、屈曲・外転ともに12級レベルの数値となった。ひどい骨折であったため、可動域制限も認定される可能性があると踏んで、初回申請を実施したが、わずか2週間ほどで門前払いの非該当となった。
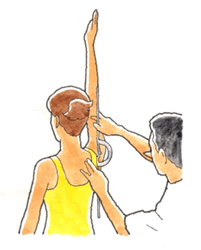 【立証ポイント】
【立証ポイント】
疼痛の残存に申請を切り替え、主治医に新たな診断書を郵送依頼したが、細かいニュアンスまでは伝わらなかったのか不完全な診断書が返却された。これでは勝負できないと判断したため、ご本人と日程を調整し、医師面談にて追記を依頼、なんとか勝負できる診断書に仕上がった。腕部の残存する症状について後遺障害診断書に記載していただいた。ご本人の困窮点を丁寧に述べた資料を作成し、異議申立手続きに付したところ、40日で14級9号認定となった。
以前は鎖骨骨幹部骨折に伴う可動域制限での認定が散見されたようにも思うが、近年ではその例をほとんどみない。医学的には、「鎖骨骨幹部骨折が肩の可動域を阻害することはほとんどなく、曲がらない理由は筋拘縮にすぎない。」という理由から「非該当」が頻発しているのではないかと思われる。遠位端骨折や肩鎖関節脱臼のような傷病名では12級6号にチャレンジしてもいいが、癒合具合や部位(骨幹部)次第では慎重にならざるを得ない。
(令和6年6月)
【事案】
自転車で歩道を走行中、駐車場から発進してきた自動車に衝突され、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
こちら側にも過失が出るため労災の適用を促したが、職場の理解が得られなかった。また、ひどい骨折だったため再生治療を勧められるが、どこまでを交通事故として面倒みてもらうのかについての線引きも重要な項目であった。 【立証ポイント】
治療費について確認したところ、なんと自由診療報の方が労災治療よりも安い?という珍事が判明したため、自由診療での一括対応とした。
抜釘後にMRI検査を依頼し、関節面の欠損及び外側半月板損傷が明確に立証できたため、ご本人・主治医と相談し、症状固定とすることとなった。主治医から「今回の手術は土台作りであって、将来的には人工関節になるだろう。」という説明もあったため、後遺障害診断書の見通し欄にその旨を記載していただき、万全な診断書が完成した。今回は画像所見が明らかであるため、わずか1ヶ月で12級13号が認定された。
(令和6年4月)
【事案】
小型自動二輪車で交差点の一番前に停止中、後続車の追突を受けて負傷。直後から頚部痛と右上肢しびれ等を訴える。 【問題点】
整形外科と接骨院を併用しており、整形外科では週1回診察で、リハビリは接骨院で行っていた。接骨院の併用をやめさせ、整形外科1本にしてほしいところだが、そもそも接骨院から紹介された整形外科であり、院長も「ウチでリハビリすると、接骨院に行く意味がなくなってしまうから。」と切り替えに難色を示していたため、併用のまま勝負せざるを得なかった。
その後、事故後5ヶ月で治療費を打ち切られてしまい、医師もその時点で後遺障害診断書を記載するとのこと。 【立証ポイント】
医師面談にてなんとか説得し、事故半年後の症状固定・後遺障害診断作成にご協力いただけることとなった。最終的に整形外科19回、接骨院70回という通院実績で審査に付したところ、14級9号が認定された。
依頼者には「認定の可能性は低い。」と説明し、覚悟の上での後遺障害申請だったが、諦めずに申請した結果であった。「諦めたらそこで試合終了ですよ。」という名言が脳裏に浮かんだが、今回のケースは特殊であり、なにがなんでも後遺障害申請すべきとはならないだろう。このような認定結果が一筋縄ではいかない14級9号を体現しているように思う。
(令和6年5月)
【事案】
自転車で交差点に進入したところ、自動車に衝突される。頭部を強打し、軽度意識障害がある中で救急搬送され、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、後頭骨骨折の診断が下された。
【問題点】
依頼者の過失が大きく、相手方保険会社からの一括対応が見込めなかったため、健康保険での治療が必須であった。過失や年齢のことも踏まえると、自賠責への請求で終わる可能性が極めて高く、救急搬送先からも早期の転院を迫られていた。 【立証ポイント】
事故2日後にご相談をいただき、今後のプランを説明。その後、弊所での面談を経て、入院先への訪問や医師面談を実施した。医師面談後、ご家族と2手に分かれ、1組はご本人と転院先へ、一方と弊所は市役所へ出向き、健康保険の手続きや破損したベンチ(市管理)の補償手続き等を済ませた。
高次脳機能障害の立証では、画像所見・診断名はクリアしていたが、意識障害が微妙なラインであった。しかし、性格変化や遂行能力、記憶力の低下等が出現していたため、国内最高峰の病院を紹介し、紆余曲折を経てなんとか受診できることとなった。検査の結果、知的機能が全般的に低下しており、中程度の高次脳機能障害であることは立証できたが、家族が一番困っている「幼児退行」については検査で立証することができない。そこで、日々の様子を写真や動画で残していただき、そのデータをUSBに収録し、添付資料として提出した。
こちらとしては、5級が認定されてくれれば勝利ラインと思っていたところ、自賠責窓口会社より「3級3号認定」の連絡があり、一同大喜びだったのだが、ここから思いもよらない事態が発生した。それは、自賠責の規定が変更となり、3級以上の認定では、後見人設定をしなければ自賠責保険金を送金することができないというものだった(事理弁識能力の問題であるため、脳に異常がなければ後見人は関係ないと思われる)。確かに中程度の高次脳機能障害ではあるものの、後見人を選定するほどの状態になく、裁判所の判断は「保佐人」とのこと。そこで、自賠責窓口の担当者に保佐人選定でも保険金を支払ってもらえるよう談判し、保佐人の手続きを進めることとなった。依頼人のご家族は、稀に見る優秀且つ円満だったため、保佐人設定の手続きはスムーズに終了し、保佐人からの再請求によって保険金がすんなり支払われた。
今回は依頼者の過失が大きいため、全てこちら側で行わなければならないという事態はあったものの、初動対応と早期の道筋作りによってご家族から大変感謝される解決となった。
(令和6年5月)
【事案】
自動車で走行中、右方から信号無視で交差点に進入してきた自動車に衝突され、横転。直後から腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
受傷後2ヶ月頃にご相談を頂いたが、整形外科と整骨院を併用して治療をしていた。そのためか保険会社から「4ヶ月での打切り」を仄めかされていた。
また、現在通院中の整形外科に以前腰痛で通っていたことがあるということも分かった。 【立証ポイント】
整形外科と整骨院の併用をやめさせ、整骨院に行っていた分を整形外科にするようアドバイスした。また、保険会社の対応が強硬ということなので、直ちに弁護士に介入していただき、なんとか6ヶ月間の通院期間を確保した。既往症については、10年以上前に通院していただけのようなので、後遺障害診断書に記載されても全く問題ないと判断し、医師に委ねた。診断書の内容は可もなく不可もなくといったものだったが、受傷機転と通院実績はバッチリだったため、シンプルな申請書類に仕上げて審査に付した。
提出から2か月後に受理通知が届いたため、あまりにも遅い対応に驚いたが、その直後に調査事務所から既往症について問い合わせがあり、10年以上前であることを伝えたところ、医療照会等もなくそのまま審査が進み、受理日から40日で14級9号認定の知らせが届いた。本件は頚部が主訴だったはずが、腰部が認定され、頚部が非該当という逆転現象も起こったが、結果が同じなら言うことはない。
(令和6年6月)
【事案】
右折待ち停車中、後方から追突を受けた。直後から、頚部、腰部とも神経性の痛みが生じ、治療が長引く事に。 【問題点】
初期からの相談であったので、物損交渉から始まった。被害者・加害者共に同じ損保であったので、相手損保が提示するであろう低い査定額をけん制する為、車両保険の先行請求をほのめかしたところ、値切られることなくスムーズに対物の交渉は済んだ。

本丸と言うべき、後遺障害申請だが、初回申請は非該当。又しても、2回の申請を強いられた。 【立証ポイント】
主治医はじめ、「認定は難しいよ」との見解に意気消沈だったが、秋葉だけは「二度目で認定を取ります」と再び病院同行、追加書類を揃えた。
程なく、認定通知が返ってきた。後は、弁護士が強交渉するのみ。 (令和6年5月)
【事案】
原付バイクで信号のある交差点を直進中、対向車線の右折車に衝突される。直後から耳鳴りが発症した。
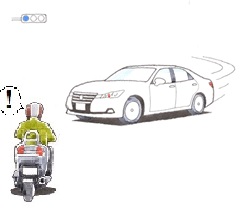 【問題点】
【問題点】
受傷初期から発症しているものの、骨折などの器質的損傷がないため、事故による症状と信じてもらえるかどうかがカギとなる。 【立証ポイント】
事故から1か月足らずに紹介され、直ちにweb面談を実施した。早期の相談となったおかげで、今後の治療と障害の立証方針を計画できた。通院先の耳鼻科でピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査を早期に実施することができたことも大きかった。
 症状の改善はみられなかったため、半年後に後遺障害診断書を依頼した。医師が後遺障害診断書の記載に不慣れだったため、添付資料も含め記載内容を打合せし、盤石な体制を整えた。審査に3ヶ月程度かかったため依頼者から不安の声も頂いたが、無事に12級相当が認定された。今か今かと結果を待ち望んでいた依頼者に報告した際の反応は、弊所の予想を超える喜びようであった。それだけ、事故による耳鳴りを信じて頂くこと・・難易度の高い作業なのです。
症状の改善はみられなかったため、半年後に後遺障害診断書を依頼した。医師が後遺障害診断書の記載に不慣れだったため、添付資料も含め記載内容を打合せし、盤石な体制を整えた。審査に3ヶ月程度かかったため依頼者から不安の声も頂いたが、無事に12級相当が認定された。今か今かと結果を待ち望んでいた依頼者に報告した際の反応は、弊所の予想を超える喜びようであった。それだけ、事故による耳鳴りを信じて頂くこと・・難易度の高い作業なのです。
※ 併合の為、分離しています
(令和5年12月)
【事案】
原付バイクで信号のある交差点を直進中、対向車線の右折車に衝突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
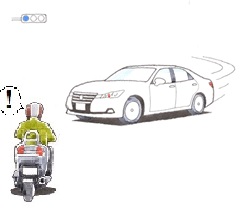
【問題点】
特になし。 【立証ポイント】
医師面談ができない病院であるため、依頼者と入念な打合せと診察のシュミレーションを行い、後遺障害診断に臨んでいただいた。こちらの病院は患者に専用用紙を渡し、自覚症状をまとめてくるよう指示し、自覚症状欄にその用紙を貼り付けるという独自のスタイルを貫いているため、その点も問題はなく、診断書の仕上がりも完璧に近かった。
別の症状でも後遺障害診断書を作成していたため、ムチウチのみの申請とは違い、審査期間が長期に及んだが、予想通り14級9号認定となった。
(令和5年12月)
【事案】
バイクで走行中、減速したところ、後続の自動車に追突され負傷した。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
事前認定で非該当、次いで既に相手方から賠償額の提示が出ている状況からのご相談であった。症状固定日後、3ヶ月は通院していたが、相談時は既に通院を止めており、再申請を急ぐことに。 【立証ポイント】
資料を精査すると、整形外科と鍼灸を併行受診していたが、「整形外科と鍼灸が連携している」ことが判明したため、異議申立手続きで認定の可能性を感じた。急ぎ、面談の2日後に病院同行した。後遺障害申請に理解ある主治医だったため、記載内容について踏み込んだ打合せをすることができ、勝負できる医証が仕上がった。
面談から40日あまりで提出、結果を待つばかりだったが、調査事務所から「救急搬送先(最初にたった1回しか通院していない)治療先」に医療照会をかけたいとの連絡があったた。先回りして、主治医の記載した資料をそれぞれの病院に提出し、やれるだけのことをして結果を待った。
受理日から3ヶ月の審査期間を経て、無事に14級9号が認定された。1回だけ通院の病院に対して、経緯書を確認したところで、新たな発見や経過について分かるはずないと思うが、最近は全ての病院に医療照会がかかる傾向にある気がする。14級9号の認定には、通院先をなるべく少なくすることも留意すべきか・・。 (令和6年3月)
【事案】
自転車で交差点を横断中、後方から右折してきた自動車に衝突され負傷。直後から全身の痛みに悩まされる。受傷初期にご相談を頂いた際、「事故から10日後に病院に通院しました。肩の痛みがあります。」との事だった。頚肩腕症候群かな?後遺障害は難しいかな?と思い、対応を急がなかった。 【問題点】
その後、委任を受けた弁護士から、診断書・診療報酬明細書の精査の為、同書類一式が届いた。確認したところ、救急搬送されていることと、なんと「肩鎖関節脱臼」の診断名を目にした。もしや・・肩鎖関節脱臼を見逃していた?
急ぎ、ご本人との面談を設定した。肩の可動域制限は回復していたものの、鎖骨遠位をみると軽度のピアノキーサインがみられた。ここで、肩鎖関節脱臼の立証に切り替えた。ただし、治療終了までの4ヵ所の病院で、「肩鎖関節脱臼」と診断している医師は1人しかおらず、その病院への通院はわずか2回、確定診断を得られるかが勝負とみた。
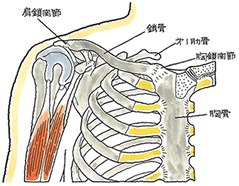 【立証ポイント】
【立証ポイント】
全ての画像を取得し、その画像とピアノキーサインが分かる写真打出しを持参して、最終通院先の医師に後遺障害診断書を依頼した。物腰の柔らかい先生で、今回の経緯を説明したところ、快くご協力頂けた。この先生も同意見で、「肩鎖関節脱臼(TypeⅡ)」の診断名を加えて下さった。
その後の申請手続きは順調に進み、3週間の審査期間で12級5号が認定された。後遺障害の申請はせずに示談交渉に進む予定であったものが、最後に12級5号認定となり、賠償金は4倍に跳ねがった。
被害者さんにとっては、初めての事故で余裕がないため、症状を詳しく説明しきれないことがあります。慎重に症状を聞き取らなければならないと、改めて反省する件となった。
(令和6年3月)
【事案】
自転車で歩道を走行中、車道から急に歩道へ乗り上げてきた自転車に衝突される。直後から頚部痛、右上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。
 【問題点】
【問題点】
本件は、加害者が加入している個人賠責保険への請求となった。 【立証ポイント】
やることは変わらないが、他にも請求できる保険がないか精査すると、ご自身加入の共済が見つかったため、まずは共済に後遺障害申請をかけ、その結果をもとに個人賠社へ申請する方針とした。
受傷機転や通院実績、症状等を鑑みると、自賠責でも14級が認定されると想定、資料を整えて共済へ申請すると、わずか2週間で14級準用(自賠責でいう14級)が認定された。その通知を参考資料として添付し、申請をかけたところ、個人賠償でも14級を認めてきた(自賠責保険調査事務所に諮問したよう)。
(令和6年3月)
【事案】
何でもない郊外の交差点を自動車で通過する際、右方から信号無視の自動車と出合い頭衝突、乗っていた奥さんと一緒に受傷した。 【問題点】
仕事をしながらの通院で、症状の改善が進まなかった。半年後に夫婦共々、後遺障害申請したが、何故か奥様だけ14級9号が認定され、ご主人は非該当となった。同じ事故で、同じような症状で、同じような治療をして、同じ程度に通院したが、結果が違う。認定基準に照らした結果ではあるが、後遺障害審査がAIでなく、最後は人の感性で決まるからか・・。 【立証ポイント】
早速、医師に奥様と同じように追加の意見書をご記載頂き、提出した。程なく、ご主人にも14級9号が付いた。
(令和6年3月)
【事案】
自転車で退勤途上、交差点で自動車と出合い頭衝突したもの。一早く労災治療となっていた。
診断名は、脳挫傷に加え、左頬骨、骨盤の寛骨臼など骨折した。身体の骨折は順調に癒合が進み、14級程度に回復する見込みである一方、高次脳機能障害は必至の件となった。 【問題点】
自転車側に一時停止があり、相当の過失減額から、賠償請求の余地は低い件であった。また、本件被害者さんは、元々の障害があり、1人暮らしの為、ご職場と遠方のご家族の協力が立証作業の生命線となった。
最大の問題は相手損保であった。治療費が労災であることから、相手損保の積極的な介入はないと思われたが、なんと、3か月で症状固定、後遺障害診断書を病院に記載させてしまった。確かに、ご家族はよくわからないままに同意書を差し出していたが、担当者の考え=「障害者は面倒だから早く終わらせよう」としたのか、単に高次脳機能障害の知識(通常、症状固定は1年後)が無かっただけか、いずれにしても、この担当者からすべて取り上げる必要がある。 【立証ポイント】
必要な検査も欠いたまま、わずか3か月後の後遺障害診断書など、破り捨てるしかない。この時点は、骨折の治療でぐったりしたまま退院したばかり、高次脳機能障害の症状が顕在化する前の状態なのです。しかしながら、そこは、丁重に「書類を補充してお返しします」と言って、相保の担当者に書類一式を返して頂いた。
その後、経過的に症状を観察、案の定、3か月後から情動障害を発露、幻聴や幻覚も加わり、以後、進行していった。ついには介護状態となり、施設入居を余儀なくされた。これこそ、高次脳機能障害の症状、そのクライマックスとなった。いつも通り、可能な検査を的を絞って実施、後遺障害診断書は新たに書き直し、すでに書かれた診断書も遡って修正を加えた。症状と事故前後の変化を職場から精密に聴き取り、9か月後、万全に提出書類を揃えた。
担当者とはここで決別。「書類をお返しする」との約束など反故、連携弁護士を介入させて被害者請求へ。問題なく自賠責保険は3級3号、労災は1級-5級の加重障害の判定となった。自賠責に関しては、元々の障害を”加重障害として差し引かれずに済んだ”点が大きい。それぞれの入金(労災は年金支給、7年支給停止だが一時金あり)をもって、これ以上の賠償余地は無きに等しくなった。 それでも、連携弁護士は損害賠償を模索、担当者から譲歩を引き出し、わずかに追加の賠償金を貰って矛を収めた。仮に裁判で介護費用を請求しても、元々、精神障害者手帳をもち、障害年金の受給者であることから、実質審議にはなじまないと判断したからである。 断言します。相手損保に任せていたら、半年で7級4号で終わらされたと思います。 (令和5年7月)
【事案】
自動車で渋滞中、後方から走行してきた自動車に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
受傷初期からご相談を頂き、順調に通院実績を重ねていたが、受傷機転を理由に5ヶ月間で一括対応を打ち切られてしまった。また、通院先の院長が個性的な医師で、独自の解釈「一括対応終了日=症状固定日」と患者に説明していた。 【立証ポイント】
医師面談ができない病院であるため、依頼者と入念な打合せを行い、あと1ヶ月間だけ事故として健康保険で通院を継続したい旨を医師に伝えていただき、了承を得ることができた。ところが、完成した後遺障害診断書を確認すると、症状固定日=打切り日、追加の診断書も通院期間が空白となっていたため、文書+電話にて修正を依頼し、なんとか当初の目的を果たすことができた。
受傷機転が軽微であったため、非該当を覚悟していたが、2ヶ月に及ぶ審査期間を経て、14級認定となった。
(令和6年3月)
【事案】
ゴルフ場で無人カートの衝突を受けて受傷、膝部のプラトー骨折となった。プレート固定後、リハビリを続けた。膝関節の可動域は回復傾向。
 【問題点】
【問題点】
ゴルフ場は責任を認めるのか否か曖昧であったが、傷害保険での支払いを約束した。具体的な後遺症や賠償金の話はなく、入院・通院の保険金での解決を提示してきた段階で、弊所に相談が入った。
この傷害保険は受け取るとして、後遺障害の評価がされていないこと、休業損害や慰謝料、逸失利益など実額損害の評価がされないまま、定額の保険金での解決は飲めない。懸念点は傷害保険金が賠償金の一部とされることか。 【立証ポイント】
病院同行の上、後遺障害診断書を記載頂き、痛みや不具合の14級9号の提示とした。連携弁護士から改めて、損害賠償金の積算を行い、ゴルフ場に提示した。ようやく、ゴルフ場が契約しているであろう、施設賠償責任保険と、相手の代理人弁護士が登場、ここで初めて示談交渉となった。
賠償保険と傷害保険を切り分ける為に、先に傷害保険の入院・通院、そして後遺障害保険金を受け取った。次いで、賠償交渉の結果、14級9号の慰謝料は承諾、その他損害項目も出揃った。ただし、過失減額はシビアな回答、それでも、傷害保険金とは”別枠で”多額の賠償金の獲得に至った。このような施設での事故では、傷害保険金のみで、なんとなく解決している例が多いと思う。
(令和6年2月)
【事案】
自転車を押して歩いていたところ、左折してきた自動車に巻き込まれ転倒した。直後から腰背部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
この事故から1ヶ月も経たないうちに、今度は歩行中に自転車にひかれてしまい負傷した。1回目の保険会社としては、連続事故として2回目事故の保険会社に引継対応してもらいたいようであった。2回目事故の担当者も危うく応じそうであった。
また、高齢なため、MRIなどの検査を受けることが困難であった。 【立証ポイント】
まずは1回目と2回目での負傷部位をそれぞれ確認。「頭部打撲傷」という、一部の診断名が重なっているとはいえ、それぞれ負傷した主要の部位が異なり、救急搬送先や治療・リハビリ先も異なるため、連続事故とはせず、それぞれ治療を継続していく方針とした。治療部位・内容については、各病院に事情を説明し、切り分けて頂いた。
受傷機転と症状の一貫性、通院実績を根拠に打撲傷で後遺障害申請を実施したが、MRI検査未実施でも14級9号が認定された。MRI検査の重要度は年々下がっているように感じてはいたが、検査を受けることができるのであれば、それに越したことはない。誤解なきよう追申します。
(令和5年12月)
【事案】
道路を横断中、右方から走行してきた自動車に衝突され、受傷した。脛骨(すね)の膝下部分を骨折し、プレート固定とした。直後から強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
骨の欠損がひどく、骨折箇所に人工骨を埋めるなど、骨癒合に時間がかかり1年を要した。また、元々の体質としてX脚であり、そこへ今回の事故によって軟骨が欠損したため、将来膝関節症になることが予見されるとの説明を受け、交通事故としてX脚矯正手術と併行して軟骨培養術を勧められた。とにかく膝がボロボロであった。
コロナが落ち着いた段階でようやく医師面談が可能となったため、現状把握や今後の方針について医師から説明を受けた。X脚矯正の骨切術や軟骨培養については、保険会社が交通事故としては支払ってくれない旨、ご本人が再度長期の休みを取ることができない職業であり、ご本人もそれを望んでいない旨を医師に説明し、なんとか手術前に症状固定とする流れへ持っていくことができた。
可動域制限では等級を逃しており、軽度な動揺性は自覚症状レベルであるものの、靭帯に異常がないため、軟骨の欠損を証明して12級13号を目指すこととなった。抜釘手術時に、内視鏡で関節面を確認するとの事だったため、後遺障害診断書作成時に内視鏡検査の画像打出しを添付していただき、審査に付して40日、速やかに12級13号が認定された。 (令和5年12月)
【事案】
バイクで直進中、急な車線変更をしてきた自動車に衝突され受傷する。直後から腰と膝の痛みに悩まされた。
【問題点】
自動車と接触したものの転倒せず、踏ん張った際に痛めたとの事で、バイクの損傷箇所も言われなければ分からない程度であった。これは小破=軽微な事故に分類される。およそ、14級の認定すら困難に感じた。 【立証ポイント】
痛みの残存はあるが、歩行や可動域、正座・胡坐など問題なく行うことができるため、MRI検査の実施は諦め、腰椎での14級9号のついでに膝を狙う方針とした。ご本人の意向により整形外科と整骨院を併用したため、整形外科単独での通院回数はそこまで多くはなかったが、1ヶ月程度で腰と両膝にそれぞれ14級が認定された。とくに、膝の認定は、大甘に感じた。
後遺障害に理解のある主治医だったため、今回の結果に繋がったように思われる。骨折なく、画像所見が乏しい被害者さんにとって、受傷機転や症状の一貫性・通院回数もさることながら、「病院選び」が1番重要なのではないだろうか。
(令和5年11月)
【事案】
交差点で信号待ち停車中、後続車の玉突き衝突で前車にも衝突したもの。 【問題点】
救急搬送先の病院は1回だけ、その後、自宅近く整形外科に通院を始めた。2カ月後、職場の異動により、通院の便から職場近くの病院に転院することになった。
いつも通り、病院同行後、丁寧に書類を揃えて申請したが、治療先の変遷が不自然に思われたのか、初回請求は非該当の結果が返ってきた。 【立証ポイント】
いつも通り、2院に対して意見書の記載を頂き、再請求した。それでも、医療照会がかかり、その度に病院の不興をかいつつ4か月経過、ようやく14級の回答となった。
すんなり1回で認定されない案件も度々です。むち打ちの14級認定は、(症状を)疑われることが前提の審査・・そんな気分にさせられます。
(令和5年11月)