【事案】
原付バイクで交差点内で右折待ちをしていたところ、後方から自動車に追突されたもの。
【問題点】
脊柱の変形についていかに画像所見と後遺障害診断書に落とし込むか?
可動域については機能障害としては認定されないところまで回復していた。
【立証のポイント】
椎体の圧潰が25%を上回っているかどうか?またご年配の被害者様であるため、骨折の状態はどうか?これらを丁寧に追いかけていく必要があった。
3DCT等を駆使し、医師に後遺障害診断書に所見を落とし込んでいただく。さらに、骨折が陳旧性の物ではなく、新鮮な骨折であることもMRIから補足的に立証。脊柱の変形が認められ、11級7号が認定される。
(平成26年11月)

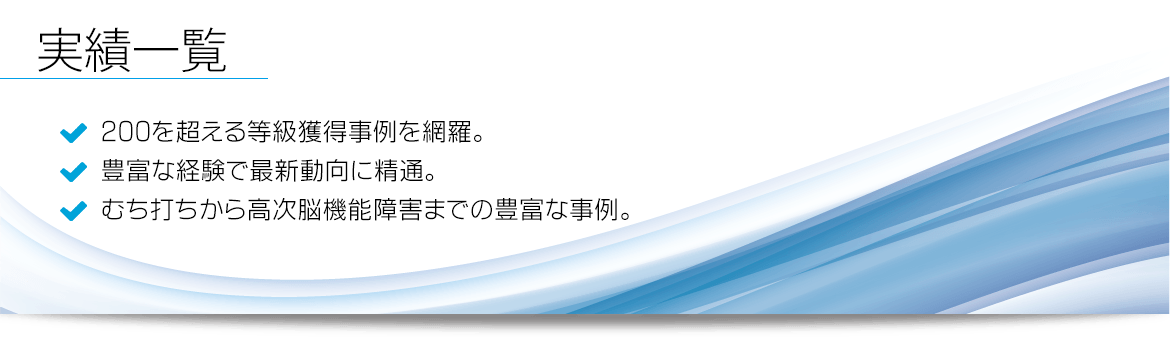
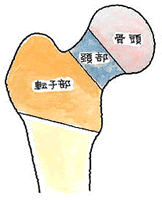
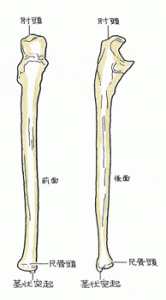 【立証のポイント】
【立証のポイント】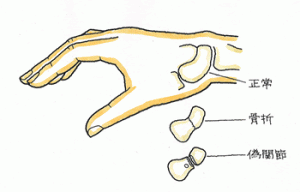 【立証のポイント】
【立証のポイント】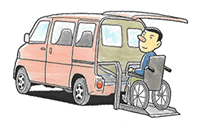 【立証のポイント】
【立証のポイント】




