本日は事務所へ依頼者様のご来所が二件、とくに重傷の方については、今後の過失割合の交渉について、弁護士から刑事記録の開示の指示がありました。刑事記録とは、一般に警察が調べた交通事故の記録です。主に現場検証をまとめた実況見分調書と、取り調べでの供述調書で構成されます。これが客観的な事故の記録、1級の証拠となるわけです。 おおらかだった時代 👉 刑事記録の取得について 今まではなんとなく、「送致番号と装置日を警察に聞いて下さい」としていましたが、弁護士によると正確には、以下の項目を交通課の警官に聞いて、その検察庁に請求を行います。 ① 送致日 ② 送致先(の検察庁、支部) ③ 送致番号 ④ 罪名(主に自動車運転過失致傷罪) 被害者本人に限らず、むしろ代理人弁護士からの請求が多くなります。ちなみに、行政書士の私も何度か請求しましたが、現在は行政書士からの請求は余程の事情がない限りダメのようです。 15年前のやり取り 👉 刑事記録と検察庁の対応 検察庁へのコピーの請求は弁護士ができますが、上記の①~④は当事者から聞いて頂く必要があります。以前は当事者が電話で尋ねたものですが、本人確認の為に警察署の窓口に身分証明書を持って来るよう言われます。
通常、何か買い物をすれば、その受取証書=領収書・レシート等が引き換えで発行されるものです。これを常識と思っていましたが、常識が通らない場合があります。それは、私共にとって病院です。
患者に代わり、診断書や画像ディスクを請求して代金を支払った後、その代金を保険会社に請求する必要から、領収書の発行を文章科・医事課にお願いします。もちろん、ほとんどの病院では、常識通り発行して下さいます。しかし、何故か「発行できません」と返答してきた病院が数件ありました。「患者さんが窓口で支払った場合のみ」との説明でしょうか。そのような独自ルールはおかしいと思います。これは全体のおよそ2~3%程度の希少種ではあります。また、残りの97%の病院の内1/3程度は、発行を拒否しないまでも、面倒がったり、遅くて何度も催促したり・・病院は常識の外にあるものと痛感させられます。 改めて、民法の条文から。領収書の発行義務をみてみましょう。 民法第486条「受取証書の交付請求権」 1.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。 2.弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。 ここでいう「弁済」とは代金の支払いを指し、「受取証書」が一般的にいう領収書に該当します。つまり、顧客がお金を支払う際、その対価として、代金を受け取った者に対して領収書の発行を求める権利があることになります。請求を受けた者は、原則として発行を拒否することはできません。
この権利は、支払いを行った事実を客観的に証明するために買主に認められた重要な権利です。後日「まだ支払いを受けていない」といったトラブルが発生した場合、領収証がなければ、支払った側が不利な立場に置かれる可能性があります。領収書は、このような二重払いのリスクを防ぐための重要な証明書となります。 ↑ となりますので、やはり、商慣習としての必要性は、法律に根拠があったのです。したがって、病院の発行拒否は法律違反になります。では、拒否する病院に法律を盾に食って掛かるか・・そんなことはしません。病院側の反感を買うだけではなく、何より時間の無駄です。振込控等を代用して、請求先の保険会社に理解を求めています。まぁ、保険会社も「仕方ないですね」と支払って下さるものです。
ただ、このような変な病院(の医事課、あるいは窓口)は、いずれバチが当たると思います。トラブルを起こす要因を自ら作り出しているのですから、何かと面倒事が返ってくるものと思います。
(5)紹介料を収入とすることに行きつくことは・・自然かもしれません 参入者が増えるほど価格競争は激しくなり、単価が下がり続けることは世の常です。まして、資格や特別な技術・知識なしにできそうですから(すみません、そう思っているだけです)、過当競争は目に見えていたと思います。そして、会社と折衝が生じれば、依頼者は自分でやるしかありませんから、先に退職を伝えてもらう依頼だけで数万円払ったら、ほぼ無駄となります。さらに、会社と紛争に発展すれば、改めて弁護士を雇うことになり、やはり代行会社に払ったお金は無駄になります。
代行会社が、代理行為に手を染めずに真面目に仕事をすれば、かなりの薄利、受任件数の割に利益乏しい仕事になります。そして、依頼者のニーズと共に利益性の高い交渉業務は、弁護士の仕事と収益に流れます。したがって、仕事を紹介した弁護士から何等かのバックが欲しいと思う事は、経営上むしろ自然と思います。
メッセージを伝えるだけの軽易かつ薄利の業務ですから、紹介料をあてにしなければならないほど逼迫した現場だったのかもしれません。それでも、法律順守の中で弁護士と仕事をしていかなければならない・・これは弁護士と提携している業者共通のコンプライアンスなのです。 (6)話を戻します。そもそも、退職代行業は必要か・・ やはり、一言辞めると言って済むならまだしも、会社ともめる場合は最初から自分で折衝するか、案件が難しいものであれば弁護士に任せることになります。仮に折衝がなく簡単に退職できるケースでも、お金を払ってまでも代わりに言って欲しい・・なんとも弱気というか、自分で自分のケツもふけない(下品な言い方ですみません)、とても心配な人に思えます。私の結論ですが、このような業務があることは仕方ないと思う一方、想像以上に大勢が利用する風潮に不安を覚えるのです。日本中、そんなに弱っちい人、いえ、繊細な人が多いのか・・と。
数カ月前、ある懇意にしている社労士先生に、退職代行業について質問しました。やはり、顧問先でも、代行業による退職の申し出がぽつぽつあったそうです。顧問先の社長に対して、その先生は言うそうです。「良かったじゃないですか、自分でけじめをつけられない、そんな奴さっさと代行業を介して辞めてもらった方が良いですよ」と。
厳しい物言いですが、代行業社を利用するしかない事情の方も存在すると思います。退職代行業に社会的な必要性がないとは言いません。ただし、今回の警察沙汰によって、紹介料は厳しく監視されると思います。薄利が続く中、少なからず代行業は撤退、あるいは縮小すると予想します。また、もし私が会社の人事担当であれば、転職者の面接で「前職を辞めた理由と共に、退職代行業を利用したか否か」を必ず質問すると思います。
すでに報道でご存知と思いますが、退職代行会社に警察の調査が入りました。まだ、捜査段階ですので、あくまで「某退職代行会社に嫌疑がかかっている」と言う前提で書きます。
何が問題だったのか・・早々に弁護士会から見解が発表されています。それを元に私なりにまとめてみました。
 (1)退職代行業って流行っていたんだ・・
退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。
(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?
ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ちなみに、会社へ「辞職届」を代書して通知する場合は、行政書士の代書権の侵害にやや当たるかと思います(非行政書士行為)。まぁ、行政書士会はそう騒ぎませんが・・。
(3)では、警察沙汰となったことは?
会社に辞めますと伝えて業務完了なら、上記の通り問題はありません。しかし、退職にあたっては、社会保険の手続き、退職金の合意、業務の引継はじめ諸事務が残るはずです。何より会わずに退職するなど、労使間が険悪化してる状態も多く、もめるケースが多いと思います。それで会社と折衝する場合や、交渉に発展すれば、代行会社の業務を逸脱します。あくまで、退職の意思を伝えるだけで留めなければなりません。面倒な交渉を頼みたい場合は、今度は弁護士に依頼することになります。
(1)退職代行業って流行っていたんだ・・
退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。
(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?
ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ちなみに、会社へ「辞職届」を代書して通知する場合は、行政書士の代書権の侵害にやや当たるかと思います(非行政書士行為)。まぁ、行政書士会はそう騒ぎませんが・・。
(3)では、警察沙汰となったことは?
会社に辞めますと伝えて業務完了なら、上記の通り問題はありません。しかし、退職にあたっては、社会保険の手続き、退職金の合意、業務の引継はじめ諸事務が残るはずです。何より会わずに退職するなど、労使間が険悪化してる状態も多く、もめるケースが多いと思います。それで会社と折衝する場合や、交渉に発展すれば、代行会社の業務を逸脱します。あくまで、退職の意思を伝えるだけで留めなければなりません。面倒な交渉を頼みたい場合は、今度は弁護士に依頼することになります。
今回の違法性の対象となったことは、依頼者の退職に伴い交渉が必要となった場合に、同社が有償(報酬目的)で弁護士にあっせんしていた疑いが生じたからです。現在、押収資料を分析し、全容解明を進めていくそうです。 (4)つまり、弁護士から紹介料は違法 弁護士職務基本規程13条:弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 他の士業を含めどの業界でも、仕事の紹介・斡旋で、キックバックや何らかの見返りがあることは当たり前の商行為と言えます。しかし、紹介料のやり取りについて、弁護士は厳しく禁止されているのです。違反すれば、懲戒処分の対象となります。刑事罰まで及ぶかは、事案の深刻度で判断されると思います。 ◆ 弁護士程の緊張感はないかもしれませんが、司法書士や行政書士も規定されてます。行政書士を例にとると、令和6年4月1日施行「行政書士職務基本規則 第15条 (不当誘致行為の禁止)」に抵触します。これまでは紹介料の禁止について、「倫理綱領」にぼんやり触れられる程度でした。昨年から、はっきり条文化したと言えます。今までは、紹介料のやり取りだけの事例から、刑事罰にまで及ぶ例はほとんどなかったと思います。しょせん内部規定だから・・と軽視されたのでしょうか。しかし、具体的に明文化された以上、はっきりと違法の対象になったと思います。
司法書士では、その行動規範13条「不当誘致」が該当します。今後、直接的な禁止規定の見当たらない税理士はじめ、他の士業も追従するのでは?と予想します。 長くなるので つづく 👉 モームリはもう無理なのか? Ⅱ
どうしても、取り上げなければならないニュースが入ってきました。妊婦の死亡事故ですが、直後に胎児だけは帝王切開で出産できました。胎児に、事故の影響と思われる障害が残ってしまった痛ましい事故です。

まず、お母さんは普通に死亡事故による賠償請求の対象として、問題はお腹の赤ちゃんへの損害をどう見るか・・です。民法では以下の通り。 第721条 : 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 法律通りに解釈すると、赤ちゃんの慰謝料や逸失利益を請求する余地は、生きて生まれれば、その障害が”事故によるもの”であるなら、認められることになります。
 ◆ 「胎児を既に生まれたものとしてみなす」ということについては、解釈として法定停止条件説と法定解除条件説という2つの説があります。
◆ 「胎児を既に生まれたものとしてみなす」ということについては、解釈として法定停止条件説と法定解除条件説という2つの説があります。
① ...
弊所にも様々な被害事故の相談が入ってきます。交通事故は、加害者vs被害者の構図となり、その責任関係も過失相殺と言う相場がある程度確立したものです。しかし、交通事故以外の事件については、確固たる相場がありません。もちろん、類似事件の裁判判例を参考に判断します。実際は、裁判まで至らない事件がほとんどで、双方の話し合いで解決することになります。
近年、被害事故の相談では、富士急のドドンパがありました。ジェットコースターのような遊具には、確かに一定の危険があります。実際、ジェットコースターでむち打ちになる人は多いのです。かつての常識では、「自分の意志でジェットコースターに乗って、首を痛めて、富士急に賠償金を要求する?」なんてことはなかったと思います。富士急は相次ぐ被害申告に対し、お見舞い金5万円などで対応していました。このように、施設側に責任を求める主張が多くなった・・権利意識の変化を感じます。
例えば、道で転倒してケガをした場合、その責任は転んだ本人であることが常識であるとします。ところが、段差があった、道路の整備が不十分だった、そのせいで転倒した・・道路を管理する市町村の過失はないのか? との言い分です。昭和生まれの私に、そのような権利意識はなく、単に転んだ自身の過失としか考えません。しかし、他者に賠償責任を問う相談が増加しており、相談を受けた弁護士は個々に施設側の過失を検討することになります。もちろん、道路管理者の責任を考えることは、再発防止の観点からも大事です。それを別として、ほとんどは転倒者の責任である・・これはわりと世界の常識と思います。。
一方、訴訟社会であるアメリカでは、常識とは裁判で勝った方になります。その代表例が、有名な「マクドナルド訴訟」です。ドライブスルーで買ったコーヒーを膝にこぼし、火傷の損害をマクドナルドに訴訟を起こして、原告が勝った件です。当時のCNNのニュース報道を覚えています。CNN実施による世界の意識調査では、日本含め他の欧米諸国、ロシア、中国、インドでも、「それ、こぼした奴が悪いんじゃね?」が主流でした。アメリカだけが、「コーヒーが熱すぎるマクドナルドのせい」になったのです。 「マクドナルド訴訟」、アメリカの訴訟社会を印象付けた代表的な判例です。改めて振り返ってみたいと思います。事件から30余年、アメリカの悪影響か?日本人の権利意識も、アメリカ化が進んでいるように思えます。 <ウェキペディアさまから引用>
(1)事件の概要
1992年2月、ニューメキシコ州アルバカーキのマクドナルドで、ステラ・リーベック(当時79歳)さんとその孫がドライブ・スルーでテイクアウト用の朝食を購入した。その後、マクドナルドの駐車場で停車しているときにコーヒーを膝の間に挟み、ミルクとシュガーを入れるためにコーヒーの蓋を開けようとしたが、誤ってカップが傾いてしまい、コーヒーがすべてステラの膝にこぼれてしまった。コーヒーは服にしみて火傷となり、近くの病院で治療し、第3度の火傷であると診察された。 (2)司法判断
ステラさんは、火傷の直接的な原因が自分の行動にあることは認識していました。しかし、火傷の一因となったコーヒーの熱さは異常であり、この点についてマクドナルドは是正すべき義務があり、また治療費の一部を補償するべきであるとして訴訟を起こしたのです。当初のステラさんの要求は、治療費1万1千ドルに対する3万ドルだけでした。これに対して、マクドナルドは800ドルの支払いを申し出たが、ステラはこれを断って弁護士を雇い、裁判を起こしました。
陪審員による評議の結果、次の理由でステラ・リーベックに20%、マクドナルドに80%の過失があるとした。実は、訴訟と同様の苦情が過去10年間に700件あったこと、マクドナルドのコーヒーが客に提供される際の温度は華氏180〜190度(摂氏約85度)だが、家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは華氏158〜168度(摂氏約72度)であったことから、コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見にくいことその上で、填補賠償認定額20万ドルの80%にあたる16万ドルを本来の填補賠償額として、またマクドナルドのコーヒー売上高の2日間分に相当する270万ドルを懲罰的損害賠償額として、それぞれ支払いを命じる評決が下された。
損害の内訳ですが、ステラさんには皮膚移植手術を含む7日間の入院と、その後2年間の通院が必要であり、娘はそのため仕事を辞めて介護にあたった。そして、治療費は1万1千ドルにも上り、治療が終わっても火傷は完全には癒えず、その痕が残った(おそらく後遺障害の醜状痕、日本のルールでは14か12級)。また、マクドナルドは裁判中に「10年間で700件というのは0に等しい」と発言するなど、裁判において陪審員の心証を損ねたことが影響したと言われている。
スコット判事は評決後の手続で懲罰賠償額を「填補賠償額の3倍」に当たる48万ドルに減額を命じ、最終的にはマクドナルドが合計64万ドルの賠償金支払いを命じる判決が下された。その後、和解が成立し、マクドナルドは60万ドル未満(非公開)の和解金をステラに支払った。 (3)事件の余波
10年間に販売するコーヒーの数は、1日の売上が135万ドルという認定が正しいとすれば25億を超えるため、リスクマネジメントから考えれば25億分の700は0に等しいというのはあながち間違いではない。その上、他のコーヒーの温度に関する訴訟において「コーヒーの温度が高いほどドライブ中の保持温度が高くなり、ドライブ・スルーの本来の意義から言えば、温度が高い場合の利点が大きい」という結論も出ている。
この事件の後、米国マクドナルドはコーヒーカップに「HOT(熱い)!
社会保障制度の問題は今後も注目、取り上げていきたいと思います。 解説は昨日の通りなのですが、一言所感を述べたいと思います。 今回は行政側の生活保護費の削減が、憲法に照らして違法と判断されました。これから削減分の補填を行うことになります。裁判の負担と時間を奪われた原告(申請者)に対して、迅速に進めて頂きたいと思います。間違いを認め、それを正すことが大事です。
しかし、原告側の一部からの物言いが、ちょっと気になりました。今回の判決を受けて、「行政側に謝罪してほしい」との意見です。単に謝罪の言葉を欲しているだけかと思いますが、民事の世界では謝罪はただではありません。謝罪=慰謝料なのです。もちろん、本件で慰謝料が発生するとは考えづらい・・せめて追加の支給分について利息分の加算はあるかもしれません。これらは実務的な問題かと思います。
私が引っかかるのは、謝罪を求める意識です。そもそも、生活困窮者へ皆の税金から援助をする制度です。司るのは行政ですが、助け合いの制度であることは間違いありません。誰もが、いつ何時、病気や不慮の事故で、生活に困窮するかわかりません。利用者は、感謝を持って制度を享受するものです。だからこそ、行政側に対して、謝罪を要求する気持ちに少し引っかかるのです。
確かに、裁判の負担を強いられた請求者の苦労や憤慨はわかります。わかりはしますが、行政側は意地悪で支給削減をしたわけではなく、また横領などの犯罪をしたわけではありません。生活保護法に従って、正しいと思って削減を決定したものです。その決定が間違っていたのですが、法解釈、言わば手続きが間違っていたことが、どれだけの悪なのか、考えてしまいます。
税金を公平に運用することが行政側の務めです。そこに間違いがあったからと言って、全面的な謝罪をするべき悪行だったのでしょうか。繰り返しますが、請求者側の苦難、その気持ちは分かりますし、行政側も誠意をもって追加支給を急ぐこと、間違った運用をしたことへの言葉はあってしかるべきと思います。ただし、助けてもらっている側が謝罪を!と憤る姿に、日本人の美徳は感じられません。受給者としての権利意識が欧米並み?と思ってしまうのです。これを言うと、生活保護受給者に対して、受給の遠慮や委縮となり、制度の利用をためらう問題に繋がるかもしれません。しかし、受給者=助けてもらう立場からの発言には、もっと適切な言葉があるように思います。 交通事故はじめ、あらゆるもめごとに立ち会った者としては、言葉は大事に思います。間違ったことをしたら謝ることが基本です。一方、被害者側からの謝罪の要求は、その言葉や込められた感情を伝えるに、実はとても難しいと思っています。そして、謝罪の要求に応じて謝罪がなされたとして・・・多少、留飲は下がるかもしれませんが(それでも下がらない人が多数のような?)、賠償金が増えることはありません。土下座はタダなのです。
本日は酷暑の中、ご参加の皆様、誠にありがとうございました。
灼熱の埼玉セミナー、10年前の埼玉代協・総会のセミナー講師を拝命した日を思い出しました。その日は37°超えの危険な暑さでした。本日は35°なので、それよりましですが・・。

さて、今年注力しております過失相殺、ある損保代理店さまからご質問がありました。 Q:「自転車通行OKの歩道があるにもかかわらず。車道を走っている自転車と事故を起こした場合、わざわざ車道を走っていることへの過失を問えるものでしょうか?」 A:「自転車は道路交通法上、軽車両になります。原則、車道走行となります。自転車通行できる歩道は、単に自転車もOKとしているに過ぎません。したがって、その道路の規制により例外はあるかもしれませんが、車道の走行自体に過失は生じません。」となります。 この問答に直接答える記事は見当たりませんが、自転車の歩道走行は例外規定であることが伺われます。以下、警察庁のHPから引用します。 <警察庁HP> 自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)から 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の逸失利益ですが、地裁での相場は5年がMAXで、交通事故紛争処理センターでも5年が限度のようです。これは、弁護士が相手保険会社に5年MAXで請求した結果です。それ以前に、相手保険会社はまず2~3年での提示をしてくるものです。被害者自らの相対交渉では、なかなか5年に及びません。そこで、裁判あるいは弁護士を介しての交渉か、紛争処理センターの斡旋に付すわけです。
もちろん交渉事ですから、相手との交渉で年数が決定されるものです。その交渉において、”5年が相場”を厳格に捉え過ぎている弁護士がみられるので、「逸失利益を〇年まで伸ばせないか」一提案をすることがあります。個別具体的な事情に沿って逸失利益を算定する必要があるからに他なりません。
個別に症状をみて、それが重い場合ですが、痛みの程度はなかなか数値化できません。「すごく痛いから10年です」との物言いでは通りません。10年は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の相場です。そもそも12級は、画像や検査数値の基準を満たさねば認定されません。しかし、複数の14級の場合はいかがでしょうか? 頚椎捻挫で14級、膝の痛みで14級、これらは併合14級となります。複数の等級から合わせ技一本!で繰り上がるのは13級以上の場合で、14級はいくつ認定されても、14級のままなのです。これは自賠責保険のルールです。しかし、首も足も痛い、これでは苦しみが2倍ではないですか!
繰り返しますが、個別具体的な事情を鑑み、民事上の損害賠償を請求する場合、やはり、個別の事情から年数を主張すべきと思います。弁護士であれば、その交渉ができるはずです。今までも、連携弁護士の粘り強い交渉から、5年を超える逸失利益を取ったことが何度かありました。秋葉事務所としては、綿密な医療調査から14級9号を複数取る為の後遺障害診断書を仕上げます。それはそれは丁寧な作業です。一つの実例を以下、掲載します。少し古い実績ですが。
14級9号:右足母指剥離骨折(30代男性・千葉県)
【事案】
バイクで直進中、交差点で対向右折自動車と衝突。転倒し右足の親指を骨折する。 【問題点】
母指の癒合状態は良好であるが、剥離骨折は何かと不具合が残る。幸い可動域に障害は残らなかったが、鈍痛や違和感が残存する。それを訴えた診断書が望まれるが、医師は面談を頑なに拒否する。癒合が良好で、何も自覚症状を訴えなければこの障害は非該当となってしまう。 【立証ポイント】
主治医に手紙を書く。数度の手紙で自覚症状を丁寧に説明する。指が非該当になった場合の保険として、頚椎捻挫の訴えも正確に記載していただく。結果、指と頚椎でダブル14級9号。面談叶わずともマメな手紙でこちらの誠意が医師に伝わったと思う。
ちなみに後の賠償交渉で逸失利益7年を勝ち取る。頚椎捻挫だけであれば、余程のことがない限り逸失利益は5年が限度。これも弁護士と気脈を通じた立証作業での好取組例と思う。 (平成25年1月)
たまに相続業務のご依頼を受けます。年に1回位ですが。 相続人間で争いとなる場合は弁護士の仕事です。しかし、とくに争いなく、法定相続分で決着がつく場合は、相続人の特定のために戸籍など書類集めと、相続分割協議書の作成で済みますので、行政書士で足りることになります。
たまにのご依頼ですが、時間と手間暇が膨大となるのは、兄弟への相続かつ代襲相続の件です。今現在、取組中です。また、行政書士登録をして、最初の相続のご依頼もこのケースでした。代襲相続とは、相続人(遺産を受け取る人)がすでに亡くなっており、その子が受け取ることです。多くの場合、相続人の配偶者や子が存在すれば、相続人の特定はそれで終わります。子供さえいれば、その子がすでに亡くなっていても、代襲で孫が受け取ることになります。ある意味、簡単な流れです。
しかし、奥さん&子供さんがいない、生涯独身かつ子なしの方は、まず親が相続人になりますが、亡くなった被相続人が高齢者の場合は、すでに親御さんも逝去していることが普通です。すると、今度は兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟達も健在ではない場合に、その子に代襲相続が発生するのです。つまり、甥や姪に財産が相続されることになります。よく会ったこともない叔父さんが亡くなって、遺産が転がり込んだケースです。
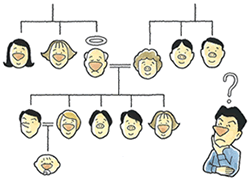 亡くなった方の甥や姪を全部調べるために、市役所に出生から死亡までの原戸籍を含む戸籍謄本の収集作業が延々と続きます。これだけでも数カ月はかかります。また、遺産を受け取る甥や姪さん達に分割協議書に実印を押してもらうまで、これも順調にいかないことが予想されます。まず連絡先を調べること(たまに遠方、海外もありました。行方不明もありそうです。)、そして、それぞれに事情の説明とご理解を得ること、実印と印鑑証明書をご用意頂くこと、その人数が多ければ、膨大な手間と時間がかかるのです。
現在は子供の数が減っていますので、昔のように兄弟が大勢いるケースは少なく、相続業務はスリムになると思います。一方、生涯独身の人が増加していますので、兄弟姉妹への相続やその子への代襲相続が予想されます。その点は面倒になるかもしれません。
亡くなった方の甥や姪を全部調べるために、市役所に出生から死亡までの原戸籍を含む戸籍謄本の収集作業が延々と続きます。これだけでも数カ月はかかります。また、遺産を受け取る甥や姪さん達に分割協議書に実印を押してもらうまで、これも順調にいかないことが予想されます。まず連絡先を調べること(たまに遠方、海外もありました。行方不明もありそうです。)、そして、それぞれに事情の説明とご理解を得ること、実印と印鑑証明書をご用意頂くこと、その人数が多ければ、膨大な手間と時間がかかるのです。
現在は子供の数が減っていますので、昔のように兄弟が大勢いるケースは少なく、相続業務はスリムになると思います。一方、生涯独身の人が増加していますので、兄弟姉妹への相続やその子への代襲相続が予想されます。その点は面倒になるかもしれません。
長年、弁護士先生と仕事をしてきましたが、言葉使いから態度まで、弁護士は非常に気を遣っていると感じます。
例えば、理不尽な要求する相談者さんや、わからず屋の依頼者さんであっても、腹を立てることなく、言葉に気を付けて丁寧に受け答えしています。私なら、すぐブチ切れますが、弁護士さんは我慢しているようです。何か、不適切な言葉や態度をした場合、弁護士会にそれがたれこまれると、懲戒などの処分を受けます。自律的に倫理機能を持つ団体と言えます。
弁護士は代理権というその強大な権利から、総じて責任が重く、行動すべてを律する必要があるようです。法律に関する説明はとりわけ責任が生じます。例えば、あってはならないことですが、行政書士が依頼者さんに間違った説明をした場合、それが依頼者に重大な損害とならない限り、処分にまで至りません。損害賠償も発生しないことが大多数です。謝って修正すれば済むことが普通です。しかし、弁護士は間違った事を言ってはいけない「専門家」とされています。法律問題は、後から「間違ってました。すみません」では済まない事が多く、経済的損害に直結するからです。
したがって、法律問題の回答に対して慎重にならざるを得ないのです。調べて裏付けを確認するまで、うかつに回答できません。じれったいことではありますが、言葉に対する責任の重さから致し方ないと思います。また、賠償金の見込みなどを質問されても、不確定な数字の明言は避ける傾向です。私などは、ズバズバ金額を言ってしまうので、それは気を付けるべきと思っています。 ご質問に対して、ズバリと明言、スピード感を持って回答を心がける秋葉事務所ですが・・それは、弁護士と比べて、行政書士の権利と責任に格段の違いがあるからなのかもしれません。
先月のセミナーからのテーマです。地方で活躍している保険代理店さん向けの内容です。題目は「弁護士の選び方」です。60人を超える弁護士と仕事をしてきた経験から語りました。
Zoomなど、通信手段が発達した現在、依頼者様との距離感はぐっと縮まった感があります。地元の先生を第一に考えることも捨てがたいと思いますが、弁護士を探す範囲を広げてはいかがでしょうかとの提案をしました。以下、レジュメから抜粋します。

日弁連設立当初の弁護士人口は5,800人、その後増加し、2024年9月1日現在で45,694人となっています。2001年の司法制度改革の影響から、この20年で2倍以上に急増しています。その内、東京都の弁護士は22,655人ですから、日本の弁護士のおよそ半分が東京にいることになります。
この統計から、専門性の高い弁護士は、東京に多く存在し、HPも豊富ですから選びやすいと言えます。もちろん、地域の法律事務所の存在こそ地元を支える、無くてはならないものです。ただし、地元先生は、ある分野に専門特化するより、幅広く地域の依頼・事件に当たる必要があります。何でも屋にならざるを得ない環境と言えます。一方、東京の弁護士は飽和気味、特徴のない何でも屋は埋もれてしまう傾向です。東京の弁護士は1~2つの分野に造詣深く、専門特化した事務所が切磋琢磨の状態なのです。
秋葉事務所でも、この数年、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬のような通勤圏はもちろん、山梨、静岡、長野、福島を超えて、全国から普通にご相談・ご依頼があります。弁護士を探している被害者さんも、相談内容によっては選択を広げる必要があります。例えば、地元の先生に頼みづらい相続や家族問題、その代表的な案件は離婚です。これも、奥様からの希望の多くは「女性弁護士」です。理由はよくわかります。地場産業や地元企業と戦う場合も、地元の弁護士より、完全なよそ者の方がやりやすいことが多いのです。もちろん、交通事故においても、弁護士の力量に差が出る案件が少なくありません。 求められる代理店の理想像は、事故や悩み事の中継センターです。各種の専門家のネットワークが、直ちに顧客様の利益につながるはずです。多くの専門家を確保することが代理店様の実力であり、持続的なテーマと思います。
誤解を恐れずに言いますと、多くの交通事故でそう感じます。
連携弁護士と過失相殺、過失割合の交渉について、事前に打合せしますと、たいていは、「判例タイムスの割合通り」、「これ以上の修正要素はない」、「紛争センターや裁判で争っても、結果は同じになる」・・このような結論になってしまうのです。

弁護士は法律や判例に則って、論理的に交渉します。したがって、裁判上でも幅を利かせている「判例タイムス」の相場に拘束されてしまう傾向なのです。法律や理屈を超えた主張は出来ないのです。したがって、「相手と過失割合で対立しているので、弁護士を入れて何とかしてほしい」との相談があっても、多くは保険会社同士で詰めた過失割合を激変させることは難しいのです。近い将来、過失割合の算定は定型化が進み、その行きつく先はAIが担うのでは?と思う次第です。
もちろん、事故状態から双方の言い分に疑義があり、ドライブレコーダーを検証し、刑事記録を取り寄せ、あるいは交通鑑定に付すことによって、新しい事実が浮上すれば、弁護士に依頼する価値はあります。しかし、多くは、片方、又は両者が納得しない事で交渉が難航しているに過ぎません。
この場合、弁護士以上に威力を発揮するのは、代理店さんの強交渉です。代理店さんによっては、積極的に契約者さまの主張を代弁してくれます。その主張は、必ずしも道路交通法の規定に縛られません。例えば、「この交差点は私も良く通るが、左角の見通しが悪く、皆注意している。相手はまったく確認していない。その点、5%でも修正できないか」。「この事故状態で相場通りの20:80では、被害者が可哀そうでしょう。ご近所同士なので、これ以上争いは避けたい。なんとか相手に譲歩してもらえるよう言ってもらえないか」。
法律家ではない代理店さんの人情交渉、又は理屈抜きの強引さが功を奏する事があるのです。この点、弁護士費用があるからと言って弁護士に頼るより、話が早く、むしろ効果的と思います。
プロ代理店さんは、人の機微を知り、交渉力の高い人がおります。私見では、弁護士以上に過失交渉をうまく進めている、頼れる兄貴分なのです。代理店さんは、日夜、弁護士以上に交通事故の解決に尽力していると思います。ただし、強交渉もやり過ぎると、相手担当者から「非弁ですよ(※)」と言われますので、その点は上手く交渉する必要があります。 ※ 非弁護士行為・・・簡単に言いますと、誰かの代理で交渉ができるのは、弁護士だけ、それ以外が有償(有償に準ずる)で代理交渉をしては、非弁護士行為となって違法となります。
事務所をほぼ1週間閉めましたが、休み中も電話やメールは一日一件程度ありました。
深刻な交通事故は無かったのですが、詐欺被害や暴力被害、離婚、その他諸々の相談です。多くは、弁護士が対象となる事件ですが、弁護士費用を払ってまで依頼するのか否かが最初の選択です。したがって、概要をお伺いして、簡単なアドバイスで終わることが多いようです。
お盆期間に限りませんが、詐欺被害の相談は多いようです。詐欺の多くは、「取られたら終わり」となります。相手から返してもらうことは至難の業です。たいていは、行方をくらまし、逃げます。仮に刑事事件となって、相手が捕まっても、相手のお財布にはお金はありません。裁判で判決を取って、さらに(もし、財産があれば)差し押さえの手続きが必要です。この間の弁護士費用は50万円を超えます。しかも、お金を取り戻す可能性は低い。したがって、費用対効果から泣き寝入りが少なくありません。
もはや、詐欺大国となった日本ですが、詐欺に気を付けると言うことは、安易に人を信用しない社会になることです。すぐ人を信用する、赤の他人でも信用する・・これらは日本人の美徳でもあります。治安がよく、安全が只と言われた美徳が失われていくように思います。
 自動車保険の世界も・・詐欺が多いのです。
自動車保険の世界も・・詐欺が多いのです。
弁護士先生に聞きますと、それ程珍しい現象ではないそうです。双方、判断の基準が異なるからです。民事の場合、一審(地裁)にて事件の事実を究明、認定します。証拠がすべてではありますが、完全な証拠が揃わずとも、裁判官が事実認定することがあります。解り易く言いますと、状況証拠からの判断でしょうか。
一方、刑事裁判は、人の罪を裁くのですから、証拠が不完全であれば、判断はより慎重になります。よく言う、「疑わしきは罰せず」でしょうか。 交通事故の裁判でも、双方、結果に強弱が生じます。刑事裁判では、加害者への罪は驚くほど軽いと感じます。まず、「わざとやったわけではない」こと、任意保険の加入があれば「損害賠償を実現できること」、さらに、被害者が「厳罰を求めない意向」の場合、相当に減刑されます。それでも、民事上では、ひき逃げや飲酒など、加害者の悪質性を追及して慰謝料増額を主張します。 かつての事故を紹介します。この加害者は、救護せずに現場から立ち去り(ひき逃げですね)、翌朝出頭(アルコールが抜ける時間を稼いだ?)でした。刑事記録の供述調書を閲覧しましたが、状況から明らかに飲酒運転と思います。ただし、直後のアルコール検査はなく、翌日では検査の意味がありません。したがって、刑事事件としては、「自動車運転過失致死傷罪」に救護義務違反が重なりますが、飲酒運転などの厳罰=「危険運転致死傷罪」までは至りませんでした。
一方、民事では、裁判まで至らず交渉解決となりましたが、(相場よりも)慰謝料の増額を飲んで頂きました。相手保険会社は、ひき逃げ+飲酒の疑いから折れ気味、強硬姿勢は取れなかったようです。
その事故 👉 7級4号:高次脳機能障害(40代男性・神奈川県)
 今回、引用する事件ですが、刑事事件では飲酒運転が認められず無罪、行政処分では飲酒運転に相応する処分となり、その処分の撤回を求めた民事裁判で結果が食い違いました。
<読売新聞オンラインさまより引用>
今回、引用する事件ですが、刑事事件では飲酒運転が認められず無罪、行政処分では飲酒運転に相応する処分となり、その処分の撤回を求めた民事裁判で結果が食い違いました。
<読売新聞オンラインさまより引用>
「酒気帯び運転」」刑事裁判は無罪だったが、民事は認定 ~ 免許許取り消し無効の請求を福岡地裁棄却 5/30(木) 福岡地方裁判所 酒気帯び運転を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の男性(40歳代)が、福岡県に対し、運転免許取り消し処分の無効などを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。林史高裁判長は男性が酒気帯び運転をしたと認定し、請求を棄却した。刑事裁判と正反対の認定となり、男性側は控訴する方針。
男性は2020年1月に同県筑紫野市の路上で酒気帯び運転をし、警察官の顔につばを吐いたとして道交法違反と公務執行妨害罪で起訴され、免許取り消しの処分を受けた。1審判決で懲役10月、執行猶予4年の判決を受けたが、21年の控訴審判決は「第三者が車を運転した可能性が認められる」として1審判決を破棄。道交法違反については無罪として罰金20万円を言い渡し、確定していた。
この日の判決では、男性が主張する車を運転した第三者について、車を映した防犯カメラ映像からも確認できないことや、誰であるか特定していないことから、裏付けを欠くと判断。男性自らが酒気帯び運転をしたと認められると判断し、処分は適法であると結論付けた。 簡単にまとめますと・・・本人が飲酒運転をしたという絶対的な証拠がなかったので、刑事上は無罪となりました。したがって、免許取り消しなどの行政処分も無効だと主張しました。この人の行いや状況をみれば、完全な証拠がなかろうと、「飲酒運転しただろう」と民事上の判断になったと思います。
民法改正案、参院で成立しました。夫婦別姓制(選択性)の導入比べ、異常なスピード感を感じます。子供の権利が絡む問題で、長らく議論されてきましたが、優先順位を高く考えたのでしょうか。
まず、基本的なことを簡単に。親権とは、未成年の子供の利益のために、監護や教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務の総称です。親権を持つとは、子供の意思決定権を親が持つことです。その親権を父母の双方が持っていることが、共同親権です。日本の法律では夫婦が離婚した場合、親権は父母のどちらかに帰属することになります。つまり、一方は親権を失います。欧米では離婚後も双方がともに親権を持つと認める国が多いようです。 本日は他コンテンツの参照ばかりで恐縮ですが、概要を抑えておきましょう。 <ちょっと専門的な解説 👉 ウィキペデアさまより> 共同親権(英:Joint custody)とは、両方の親に親権が与えられる親権形態である。共同親権は、共同身体的親権、共同法的親権、またはその両方を合わせたものを指す場合もある。
共同法的親権では、子どもの両親が、例えば教育、医療、宗教的な養育などに関する主要な意思決定を共有する。共同親権では、共有親権または共有居住権とも呼ばれ、子供は両方の親と同等または同等に近い時間を過ごす。
離婚や別居の後、両親が共同親権を持つだけでなく、子供の共同法的親権を持つこともあれば、一般的には、片方の親が単独で法的親権を持ちながら、共同法的親権を持つこともあり、まれに、片方の親が単独で法的親権を持ちながら、共同法的親権を持つこともある。
共同親権の反対は単独親権であり、子どもは主に一方の親と同居するが、もう一方の親は子どもに定期的に面会する面会交流権を有する場合がある。共同親権は、一部の兄弟姉妹が一方の親と同居し、他の兄弟姉妹が他方の親と同居する分割親権とは異なる。 <時事通信社さまより引用>
民法などの改正法成立により、父母双方が離婚後も子どもの親権を持つ「共同親権」導入への道が開かれた。新制度は2026年までに始まる見通しだが、離婚により子どもと離れて暮らす当事者らからは、導入を巡り賛否の声が聞かれた。
「感無量だ」。神奈川県の会社員男性(47)は18年に離婚し、元妻と暮らす子どもと会えない日々が続く。子どもは会えない間に18歳を迎え、成人した。男性は改正法成立を「長年の思いが実り安心した」と歓迎する一方、「家裁がDV(家庭内暴力)被害の訴えなどについて正しく判断できるのか疑問だ。新制度が始まっても、共同親権が適用されないケースも出てくるのでは」と懸念を示す。
続きを読む »
 道路交通法改正!
自転車による交通違反への反則金制度(青切符)の導入を柱とする道路交通法改正案が3月5日に閣議決定されました。成立すれば、青切符の反則金制度は公布から2年以内に施行され、今までくすぶっていた自転車の交通違反取締りが大きく変わると思います。
道路交通法改正!
自転車による交通違反への反則金制度(青切符)の導入を柱とする道路交通法改正案が3月5日に閣議決定されました。成立すれば、青切符の反則金制度は公布から2年以内に施行され、今までくすぶっていた自転車の交通違反取締りが大きく変わると思います。
今回提出された改正案では、青切符による自転車の取締りは16歳以上に適用され、112の違反行為が対象ですが、このうち重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まることになるようです。尚、反則金の額は今後、政令で決まりますが、原付バイクと同等にする方針のようです。 具体的には、 ・信号無視(6,000円) ・一時不停止(5,000円) ・右側通行などの通行区分違反(6,000円) ・自転車の通行が禁止されている場所を通ること(6,000円) 続きを読む »
ご存知と思いますが、ニュースで勝手に婚姻届けを出された男性の事件が流れました。なんとも珍妙な事件ですが、詳しい弁護士先生に聞くと、そこそこ起きる事件のようです。
何故このようなことが起こるのか・・・役所が「届出主義」と言って、法律の要件を満たす文章を提出された場合、必ず受理をしなければならない決まりとなっているからです。役所にしてみれば、不法に作成された婚姻届けを見抜くのは難しく、一々、窓口審査などしていられない事情もあります。そもそも、法は、故意に不実の婚姻届けをする悪意者など、想定できていないと思います。 (テレビ朝日Newsさまより)
被害者男性:「(婚姻の事実を)全く知らなくて。Xで(夫婦の記載が)見える戸籍情報を公開していて。本当にそうならヤバいと思って」、それで市役所に戸籍を取りに行くと、婚姻関係にされたことが事実だと判明。実際に提出された婚姻届を見せてもらいました。 被害者:「完璧に書かれた婚姻届ではなかったので、対策できなかったのかって、役所に怒りをぶつけてしまった」 当然、取り消してもらえるだろうと考えた男性。しかし、男性は思わぬ事態につきあたります。 被害者:「婚姻届で、僕が被害者じゃない扱いになる」 警察に相談すると、届け出が偽造されたとしても、被害者は市役所で、男性が被害届を出すことはできないというのです。 市役所に取り消しを申し入れると、家庭裁判所で夫婦関係にない証明をする必要があると言われてしまいました。 被害者:「家庭裁判で婚姻無効になるまで半年はかかる。だいたい1年は覚悟してと、弁護士に言われた・・・」
結婚するには、戸籍法で定める婚姻届を役所に提出しなければなりません(民法739条1項)。民法は「届出なければ結婚なし」という届出婚主義を採用しています。
法律では、「結婚」のことを「婚姻」といいます。届出がなければ、いくら事実上の夫婦生活が続いていても、法的な婚姻にはなりません。法律の根拠がない=「事実婚」と区別します。
また、届出は、当事者双方および成年の証人2人以上から、口頭または署名した書面でしなければなりません(民法739条2項)。 条文は以下の通りです。 民法739条(婚姻の届出)
続きを読む »
webにて受講です。日本行政書士会、所属する東京会と、2つの受講が義務付けられています。毎度、職務上請求書の適正利用が最重要課題となっています。それだけ、行政書士による不正使用が、他士業よりダントツに目立つそうなのです。
職務上請求書とは、相続手続きなどで、ご依頼者の戸籍謄本などを代理で取り寄せできる書類なのですが、別の目的で使用する書士が存在するそうなのです。「目的外利用はダメ」と言う簡単なルールなのですが、一部の心無い書士のおかげで、注意喚起と言うべき研修を、何度も繰り返し受講しなければなりません。
とは言え、行政書士法や関連規則を復習、見直す契機となり、ルール順守のチェックになります。ただ、その中で毎度難しく感じる部分は、倫理綱領です。法律の条文であれば、明確な規定が定められていますが、こと、「倫理的であれ」は、具体性がなく、また、解釈も人それぞれ違いますので、やっかいです。例えるなら、不倫です。これは民事上の問題、当事者同士の問題でありますが、字義通り倫理的ではないこと=道徳から外れる行為とすれば、「行政書士が不倫をするなど、もっての他!」となります。<行政書士倫理第25条乃至第31条:行政書士としての品位を保持しなければならない>は、そこまで要求しているとは思いませんが・・。
 一応、研修では、場面に応じて様々な事例を示しています。もちろん、それらは常識的です。ただし、対依頼者さまの事例の中で、弊所が迷う部分は以下の3つです。
① 正当な事由なく依頼を拒んではならない
② 依頼を拒むときは説明義務がある
③ 不正の疑いがあるときは事件を受任してはならない
業務の性質上、ご依頼に対して、お断りすることは少なくありません。そこで、その理由が正当であるか否かが、問われます。②の説明義務は当然で、理由の説明は避けられません。その理由が正当か否か、意見が分かれるところです。模範回答には無難に「依頼者の希望する期限に業務を完了できないから」とありましたが、単なる断り文句=ウソかもしれません。嘘は倫理的ではなく、品位にもとるかもしれません。
一応、研修では、場面に応じて様々な事例を示しています。もちろん、それらは常識的です。ただし、対依頼者さまの事例の中で、弊所が迷う部分は以下の3つです。
① 正当な事由なく依頼を拒んではならない
② 依頼を拒むときは説明義務がある
③ 不正の疑いがあるときは事件を受任してはならない
業務の性質上、ご依頼に対して、お断りすることは少なくありません。そこで、その理由が正当であるか否かが、問われます。②の説明義務は当然で、理由の説明は避けられません。その理由が正当か否か、意見が分かれるところです。模範回答には無難に「依頼者の希望する期限に業務を完了できないから」とありましたが、単なる断り文句=ウソかもしれません。嘘は倫理的ではなく、品位にもとるかもしれません。
③は疑いだけで(証拠がなくても)良いのであれば、ある意味、依頼者さんの正邪を勝手に判断することになります。ご依頼者を信じるのか疑うのか、倫理感に揺れることになります。 各士業でも、ほぼ①~③は同じく規定があるようです。どの先生も、ご依頼者によっては「性格的に合わないかな」と感じることはあります。士業と言えども民間企業、企業の都合でお客さんを選ぶ権利はあると思いますが・・。そこは簡単にご依頼を断れないジレンマがあるのです。


 ハラスメントの定義から、事例、対策まで・・やはり、旬のテーマです。質問が多く、盛況な勉強会となりました。
ハラスメントの定義から、事例、対策まで・・やはり、旬のテーマです。質問が多く、盛況な勉強会となりました。




