反面教師となる事例をいくつか紹介します。
まさに、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の例です。 1、自身の過失が50%!、弁護士に依頼したものの・・
バイクと自動車、交差点で出会頭の衝突事故で重傷、後遺障害も5級が認定されました。ただし、バイク側の不注意も大きく、過失割合の相場は50:50の事故です。
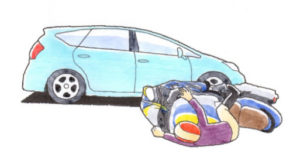
この件ですが、依頼した弁護士は相手保険会社(以後、賠償社)と交渉を担って頂けたものの、自身加入の人身傷害へは及び腰、「まずは、相手保険会社への賠償請求を先に」と進めました。本件で契約している人身傷害の保険会社(以後、人傷社)は東京海上日動ですから、自身の過失が何割であろうと、先に人身傷害への請求がセオリーです。
しかし、この弁護士さんは人身傷害保険の約款をよくご存じないのでしょう。具体的な戦略なしに、賠償社とだらだら交渉しています。交渉と言えばかっこいいのですが、単に相手保険会社の提示をのんびり待つだけです。催促も実にやわらかで、1年半でたった2度の賠償金額の提示を受けたに過ぎません。症状固定日から無為に1年半が経とうとしています。つまり、なめられています。
依頼者さんへも、「(東海日動から)こんな提示(額)が来ましたが、どうしますか?」とお伺いしてくるだけです。まるで相手保険会社のメッセンジャーの役割です。業を煮やした依頼者さんは、「では、相手の提示に対する先生の考える最良の策は何ですか?」と聞いたところ、「まず、交渉で賠償金を受け取り、次いで、人身傷害に請求です。」とのこと。 不安に駆られたこの依頼者さん、ネットで検索、「自身の過失分を裁判基準で回収する方法」を目にしました。↓
人身傷害特約 支払い基準の変遷 ⑭ 訴訟基準をゲットするための3策(1) 本件における裁判基準での全額回収は、人傷先行か裁判です(両方がベスト)。人身傷害で先に(少ない人身傷害基準とはいえ)過失減額のない100%を先取しておく、できれば、裁判で損害総額を決定させることが大事です。元の弁護士の方法ではダメです。いくら賠償社から交渉で裁判基準に近い額を勝ち取ろうと、過失分50%分に対する人身傷害からの(人傷基準での)支払い額は半分以下です。その回収に責任をもってくれるのでしょうか?
本件の裁判基準での総損害額は8000万円ほどです。自身の過失分が50%なら4000万円を人身傷害に請求する必要があります。しかし、人傷基準での回収では半分程度です。つまり、2000万円の取りそびれとなります。
本件は、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の典型例なのです。賠償社との交渉で裁判基準に近づけることなど、弁護士バッチさえあれば、むしろ簡単な作業と言えます。
 続きを読む »
続きを読む »


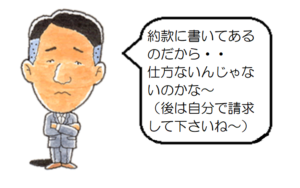

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。
秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。
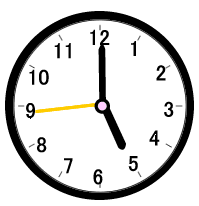
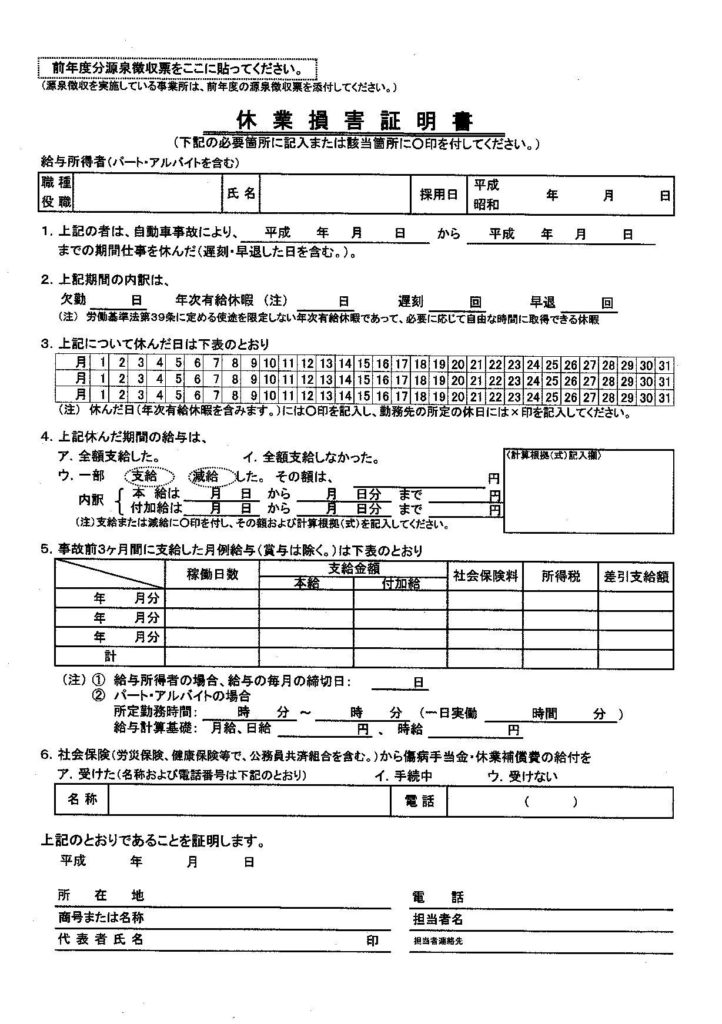
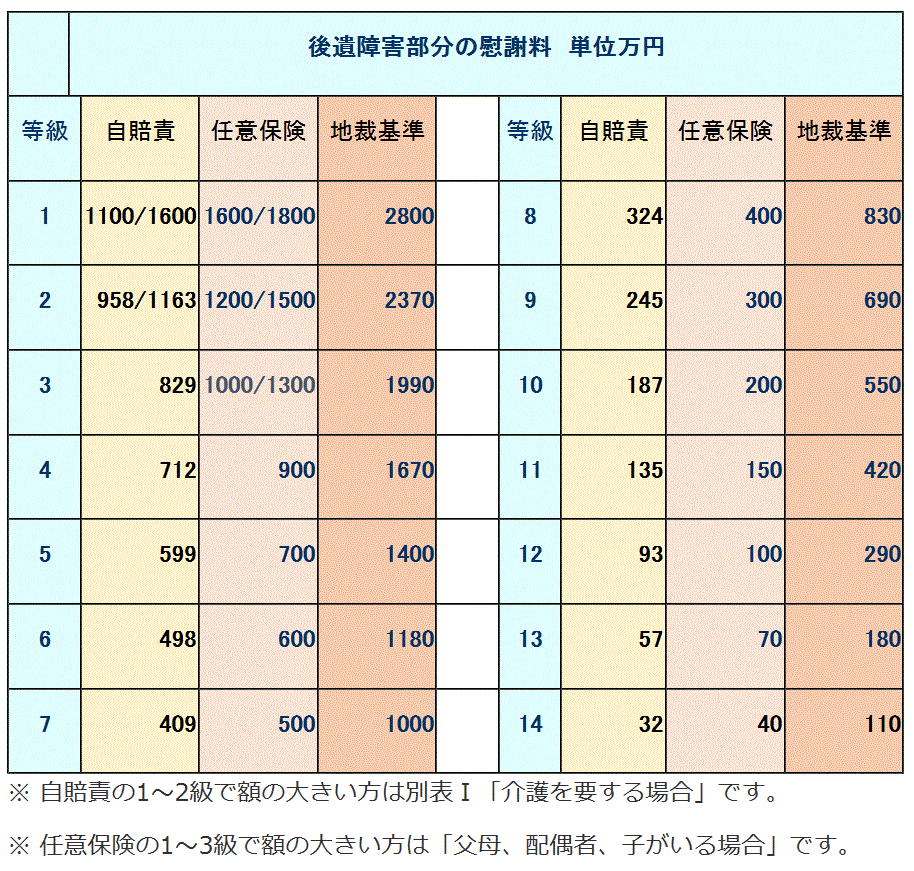 この差を見れば、保険会社との相対交渉するなど愚の骨頂に思えます。それでは、タイトルの質問に戻ります。
この差を見れば、保険会社との相対交渉するなど愚の骨頂に思えます。それでは、タイトルの質問に戻ります。
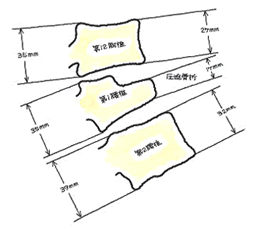


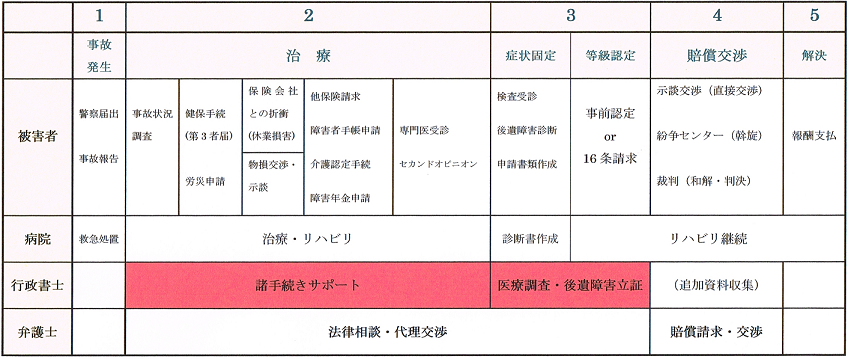
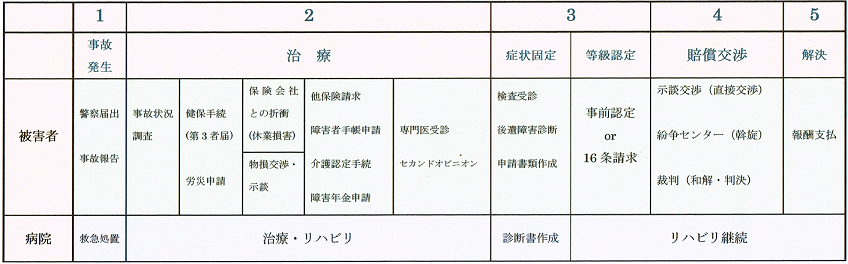

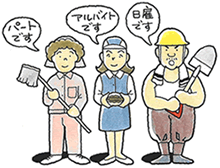


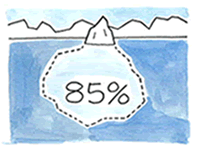
 万能の先生はいません。依頼前に、その先生が交通事故に精通しているか見極める必要があります。HPの宣伝をまんま信じないことです。(多くのHPはその弁護士先生が書いているのではなく、業者から買ったコンテンツです)
万能の先生はいません。依頼前に、その先生が交通事故に精通しているか見極める必要があります。HPの宣伝をまんま信じないことです。(多くのHPはその弁護士先生が書いているのではなく、業者から買ったコンテンツです)






