今年のNHK大河ドラマ「軍師 官兵衛」を続けて観ています。
 さて、黒田官兵衛については詳しい方も多いと思いますので人物説明は割愛します。一言で言いますと、戦国時代に信長、秀吉、家康の3天下人に仕えた軍師です。様々な逸話が残っていますが、私にとって注目すべきことが一つあります。それは、後遺障害の観点から「関節硬縮」です。
さて、黒田官兵衛については詳しい方も多いと思いますので人物説明は割愛します。一言で言いますと、戦国時代に信長、秀吉、家康の3天下人に仕えた軍師です。様々な逸話が残っていますが、私にとって注目すべきことが一つあります。それは、後遺障害の観点から「関節硬縮」です。
まず背景から・・・
官兵衛が主君 織田信長に謀反を起こした荒木村重のもとへ、「謀反を思いとどまるよう」説得のために単身、有岡城へ出向きます。しかし、村重は説得に応じるどころか、官兵衛を牢に幽閉してしまいます。この牢は天井低く、官兵衛は座ったままの状態を強いられ、1年間も陽の当たらない牢に閉じ込められました。その後、村重の謀反は失敗し、官兵衛は救出されます。1年も座ったままですから、左脚が不自由になり、しばらく自力で歩くことができなくなりました。戦国時代にどのようなリハビリをしたのか、また装具はどうしたのか記録にありませんが、有馬温泉で療養したとの記録があり、杖を使って歩けるまでに回復はしたようです。ドラマの冒頭、小田原城への使者のシーンで足を引きずってましたね。
ここで官兵衛の病態を分析します。考えられる傷病名は2つ・・
1、くる病
おそらく陽も当たらない不衛生な環境と栄養不足から、ビタミンD欠乏を原因とする「くる病」が考えられます。大腿骨、脛骨や半月板が石灰化を起こし、ひどいと骨の変形となります。当然脚が曲がったままで伸びず、歩行不能が考えられます。現代では、栄養状態の回復と運動療法から回復する病気でもあります。「アルプスの少女ハイジ」のクララも、この病気ではないかと思います。
2、廃用性症候群
人間の関節は一か月も動かさなければ、誰でも固まって曲がらなくなります。これを廃用性関節硬縮と呼びます。狭い牢で一年も歩かず座ったままであれば、当然に関節は固まってしまい、元通り動くまでの回復は困難となります。
現代の整形外科では下肢の骨折などに対し、関節のギブス固定を敬遠しています。骨癒合までは安静、不動を確保したいのですが、結果として関節硬縮となり、その後のリハビリで大変苦労するからです。そこで観血的手術(≒メスを入れる)を行い、骨折部をプレート(鉄の板)やスクリュー(ねじ)で固定することが一般的となりました。脚全体を石膏ギブスで固めてベットに宙づり、しかも、見舞いの友人がギブスに卑猥な落書き・・もはや昭和の風景です。
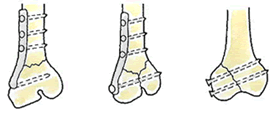
 また、関節部(大腿骨遠位端、脛骨近位端)の骨折やそれに伴う靭帯、半月板損傷など複合損傷の場合、痛みや手術後の安静から動かすことができません。関節の動きが制限されることが宿命です。後のリハビリにて硬縮を防ぐ、もしくは回復するためのCPMが活躍中です。これは膝の曲げ伸ばしを補助してくれるリハビリ機器(右写真)です。
また、関節部(大腿骨遠位端、脛骨近位端)の骨折やそれに伴う靭帯、半月板損傷など複合損傷の場合、痛みや手術後の安静から動かすことができません。関節の動きが制限されることが宿命です。後のリハビリにて硬縮を防ぐ、もしくは回復するためのCPMが活躍中です。これは膝の曲げ伸ばしを補助してくれるリハビリ機器(右写真)です。
話を官兵衛に戻します。官兵衛はおそらく、くる病と関節硬縮の両方を患ったと思います。とくに左膝は外反もしくは内反変形を伴い、さらに伸展(膝を伸ばす)もしくは屈曲(膝を曲げる)に可動域制限を残すような、ひどい状態と想像します。その後、有馬温泉での療養を経て自力歩行まで回復しますが、終生、脚が不自由でした。
官兵衛が身体障害者手帳を姫路市に申請すれば、5級の判断となりそうです。そして、本件は村重による加害行為(第三者傷害)ですが、業務災害でもあります。労災の基準では8級7号(一下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの)、もしくは10級11号(一下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの)の選択となるかと思います(慣れた自賠責等級に置き換えました)。装具なしで歩行できれば10級ですが、昔の人は根性があったので、実際は8級の用廃レベル(膝が全く曲がらない)であったかもしれません。
もっとも現代においては、自賠責保険の後遺障害は骨折後の関節硬縮に対し、厳しい目を向けています。前述の通り、現代の医療技術・リハビリ設備があれば関節硬縮は回復することができるからです。「リハビリをサボった」可動域制限であれば、後遺障害の認定は厳しくなります。骨の変形、転位、偽関節など、癒合に異常が残らなければ、大幅な可動域制限は説得力を失うのです。
大河ドラマの中盤にて、この脚のエピソードがでてきそうです。きっと脚を注目して観てしまうでしょう。







