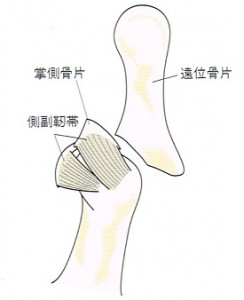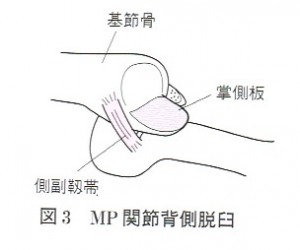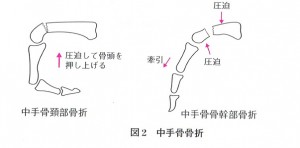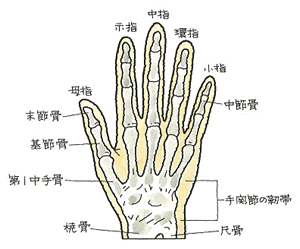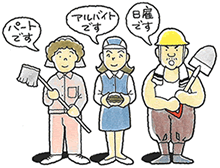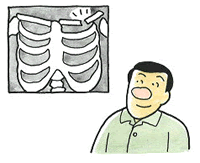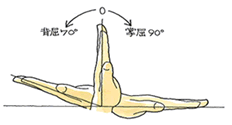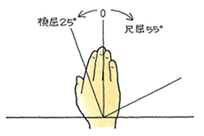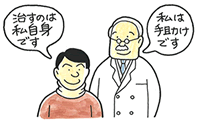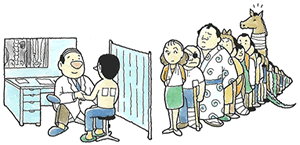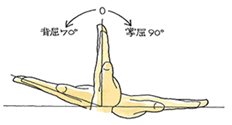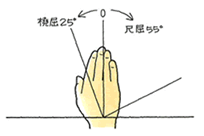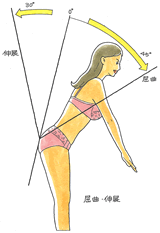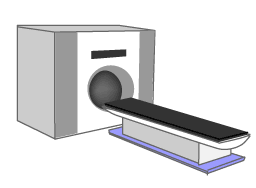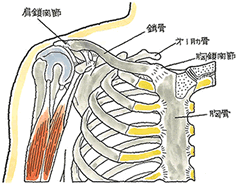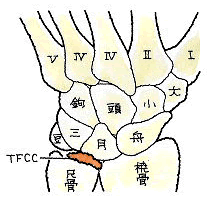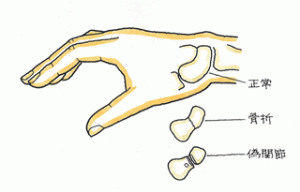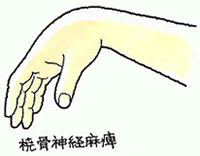大阪研修会でも「鎖骨骨折」にしっかり時間を割きました。交通事故外傷ではむち打ち、腰椎捻挫の次に障害認定が多いのではないかと思います。
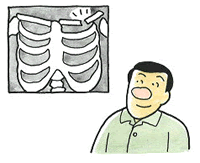 講義では主に変形の12級5号、遠位端骨折であれば肩関節・可動域制限の12級6号、10級10号の説明に終始しましたが、ある弁護士先生から・・
講義では主に変形の12級5号、遠位端骨折であれば肩関節・可動域制限の12級6号、10級10号の説明に終始しましたが、ある弁護士先生から・・
「先日、鎖骨骨折の相談があったのですが、よく治って変形も可動域制限もなく、後遺障害はあきらめました。この場合は仕方ないですよね?」
この質問には「実績」から回答しましょう。
併合14級:鎖骨骨折(10代女性・群馬県)
【事案】
自転車交差点を通過のところ自動車と出合頭衝突。意識を失うも幸い脳には受傷なく、鎖骨骨折に留まり、骨幹部にプレート固定を施す。
【問題点】
鎖骨は幸い外見上の変形はなく、2cm程度の手術痕を残すのみ。その後経過も良く、後遺障害の認定基準である12級5号の鎖骨変形は無理。また外貌醜条痕14級4号も鎖骨部分では顔や手足と違い該当しない部位であり、大きさも障害の基準外。
そして完全な回復を願う両親は相手保険会社の示談の提示について応じず、そのまま2年間放置状態に。
【立証ポイント】
こうなったら、努力賞・お土産とも言うべき14級9号を目指すのが我々の仕事。
まず無駄と分かっていながら、事故当初の意識障害に注目し「頭部外傷後の意識障害の所見について」の記載を主治医に依頼する。これは事故の深刻度を理解いただくことはもちろん、脳障害の残存を心配し、長い治療期間を必要とした根拠とする。
そして無駄と分かっていながら、外貌写真を添付。なんといっても18歳の女子です。1mmの傷でも許せないのです。
さらに無駄と分かっていながら腰痛の訴えを含めた父親による切々とした気持ち、一連の経過を書面にして添付する。
申請後、なぜか自賠責から腰部のXPの提出依頼がきたので取り寄せて提出する。
そして結果として鎖骨部の疼痛で14級9号、腰痛で14級9号のダブル認定で併合14級に。こちらの主張を好意的に受け止めてくれたよう。
自賠責も人の子、娘を思う親の気持ちに応えてくれたのかな?
とにかく私は骨折した方には全件等級をつけて解決しています。骨折までしてお土産(後遺障害慰謝料110万+逸失利益)なしで解決なんて納得できないでしょう?
続きを読む »