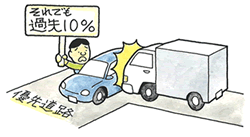秋葉事務所では交通事故の解決にあたり、今まで50人を超える弁護士さんと一緒に仕事をしてきました。もちろん、特定の弁護士さんとの提携は不健全との考えから、常に複数の法律事務所と連携しています。 よくあるご相談に「弁護士を紹介して下さい」、「交通事故に強い弁護士を選ぶにはどうしたら良いでしょうか?」があります。これだけ、HPに情報が氾濫していますと、誰もが自称専門家、選ぶ側も大変です。それと、いまだ弁護士は敷居が高く、相談しづらい雰囲気が残っているのかもしれません。
これらの相談に対し、連携弁護士を紹介する事はあまりにも簡単です。秋葉事務所では、できるだけ納得できる選択をしていただくべく、丁寧な説明を心がけています。具体的には、弁護士を選択する上でHPの派手な宣伝に迷わされること無く、実際に会って、いくつかの質問をするようにアドバイスしています。それでは、まず、入り口とも言うべき最初の質問について意見を述べます。
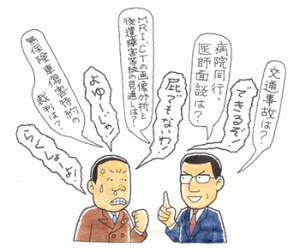
相談会に参加される被害者さんで既に弁護士に委任契約しながら、いわゆるセカンドオピニオンとしての相談がここ数年、目立ちます。不安や疑問があるなら、何故、契約している弁護士さんに相談しないのでしょうか? その疑問の答えは色々ですが、その弁護士さんを選んだ動機はかなり一致しています。それは、 保険会社に紹介された弁護士です 保険会社は顧問弁護士とは別に、複数の協力弁護士を抱えています。保険会社から仕事を貰っている弁護士は、通常、加害者側の利益を代表しています。つまり、加害者側保険会社の支払いを少なくするべく、被害者と対峙します。保険会社側からみれば、不当な請求をする、無理な要求をする不届きな被害者を押さえ込むために、保険会社側の弁護士が必要です。その仕事自体を否定するものではありません。むしろ、交通事故の公平な交渉・解決に大事な役割を担っています。
そして、この協力弁護士は、まだ仕事の少ない若手弁護士の大事な収入源となります。保険会社から多くの紹介案件を受けて修業していますが、やがて収入も安定し、(安い?)保険会社側の仕事を敬遠しだします。その頃が卒業でしょうか、また別の新人弁護士にかわっていきます。
肝心の実力ですが、加害者側弁護士はお金を払う側の味方で、多くは問題のある被害者への対応がほとんどです。したがって、「お金が欲しくば、証拠をだして」との対応で足りてしまう事件が多く、交通事故でもっとも困難であり、弁護士の腕の見せ所である「損害の立証」を経験、奮闘する機会がどうしても少なくなります。加害者側の弁護はある意味、楽なのです。当然ですが、被害者側の事務として大きな負担となる労災や健保、障害手帳・介護保険の各手続きなど守備範囲の外です。これでは、被害者に有効なアドバイスも代行処理もできません。
対して、被害者側の弁護士は治療費の継続や休業損害の算定、慰謝料・逸失利益の増額のために、証拠を集めて交渉を重ね、相手からお金をもぎ取らねばなりません。その苦労、経験、実績が弁護士の能力を引き上げると思っています。その点、いつまでも保険会社の協力弁護士をしている先生は、頼りなく思います。いつまでもしがみついているのは経営方針?、それとも仕事がないからでしょうか? 前置きが長くなりました。交通事故弁護士には、まず前提として2種類が存在します。 保険会社の協力弁護士 か 被害者専門の弁護士 か 被害者として選ぶべきはどちらか、自明の理ではないでしょうか。これが正に最初の質問ではないかと思います。
さらにもう一つの懸念を。日本は資本主義社会です。平素、保険会社から仕事を貰っている先生が、被害者側から依頼を受けたとして、徹底的に保険会社と戦ってくれるのでしょうか? 例えは違いますが、下請け会社が御店(おたな)に逆らうわけないでしょう。また、仮に仕事を貰っている保険会社と違う保険会社相手だから大丈夫でしょうか? これも護送船団方式の名残りか、保険会社は割りと一体的です。さらに保険会社の数が少なくなった現在の事情からか・・どうも心配です。
つまり、”Show the flag” 弁護士として加害者・被害者どっちの側なのかが問われると思います。刑事裁判でも弁護士と検事に分かれるように、立場の明確性が消費者にとって選択の助けになるはずです。実際に秋葉事務所でも、保険会社の顧問・協力弁護士事務所には仕事をお願いしていません。やはり、被害者のためだけに戦ってくれる弁護士が頼もしく思います。彼らは利害関係なく戦い、常に厳しい賠償交渉で鍛えられている先生なのです。どうしても保険会社の協力弁護士は、実力面・信用面、そして”加害者救済?のポリシー”からも敬遠してしまうのです。 続きはこちら 👉 弁護士の選び方 ② 専門を見極める 👉 弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性




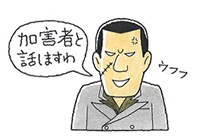
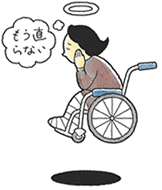 続きを読む »
続きを読む »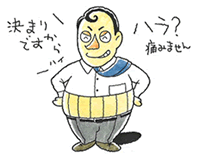

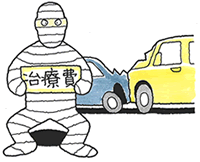
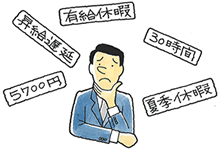
![jinnsinnjiko ][](https://www.jiko110-akb.com/wp-content/uploads/2014/05/jinnsinnjiko--300x188.jpg)