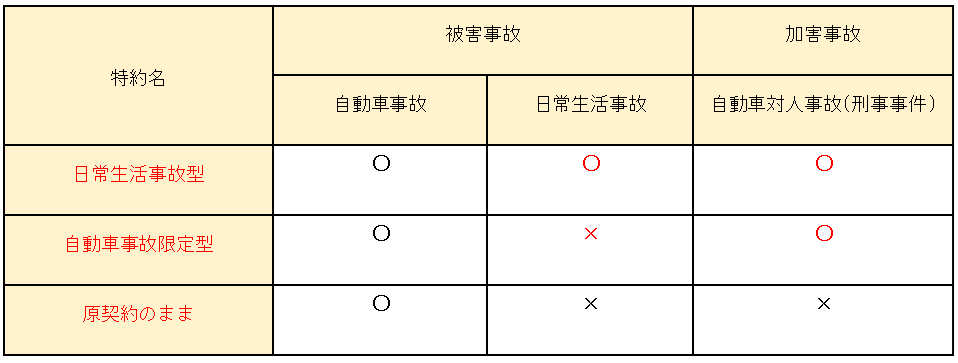交通事故被害者さまのご相談を頂く中で、もっともご回答に窮することは、被害者感情の持っていきどころです。
車の修理費など物損の場合、被害者さんにとって、その修理費を相手から取ることで全てOKとはいきません。純粋に修理費は直接損害と呼ばれ、まともな見積もりを突きつければ、大抵の損保は支払いに応じます。しかしながら、細かいことになりますが、車の修理に出す手間や様々な書類や交渉ごとに割く時間、これらの損害・対価は法律上、認められません。また、買って間もない新車などは「修理ではなく、取り替えてくれ!」と言いたくなります。高級車となれば、「格落ち」も発生しているかもしれません。これらは間接損害と呼ばれ、これを相手保険会社に請求しても、すんなり支払いを受ける事は困難です。それこそ、裁判などで白黒をつけない限り取れないものです。もっとも、裁判でも負ければ取れません。

つまり、自動的にすべての損害を回収することなど、そもそも無理なのです。手間暇・金銭をかけて、苦労を重ね、自ら戦わなければ実現できません。この原則をすんなり理解できるか?一般的に欧米人と日本人の意識の違いを感じるところです。とくにアメリカ人の場合、歴史やメンタリティから、他人に対する信頼は大変に薄いものです。交通事故の相手があっさり「すみません」と非を認めて、即座に賠償してくれる期待など持っていないのです。明らかに自分が悪い追突事故でさえ、加害者は「I’m sorry」とは言わないことが普通です。また、お金がなく、任意保険に加入していないかもしれません。一方の被害者も、相手の誠意と賠償資力を期待していませんから、しっかり車両保険・人身傷害保険に加入、あるいは弁護士を雇うのです。言葉さえ通じない多種多様の民族の合衆国ですから、自分が受けた被害は自助努力や戦いで回復することが身に染みているのです。
その点、日本はほぼ単一民族、全国的に日本語が通じ法律も統一、島国ならではのご近所関係・相互扶助もあり、他人に対する信頼は世界一のレベルではないでしょうか。その証拠に、落とした財布が届く率は63%との統計があります。ちなみに他国の統計は目にしたことがありません。他国にとって、ほとんど0%のことなど数えないからだと思います。これは世界に誇るべき日本人と美徳と同時に、被害者感情に大きく作用しているのではないかと私は考えるのです。交通事故の被害にあったのだから、「(信用すべき他人が)すべて弁償してくれるはず・・これって普通でしょ!」と。
残念ながら、こと交通事故の争いとなれば日本人の美徳は薄れます。相手保険会社はさながらアメリカ人になります。グローバルスタンダードを高圧的に押し付ける存在ですから、法律に従って決して甘くない対応となります。基本、被害者側が証拠を集めて突きつけなければ払いません。間接損害の請求など、端から拒否します。
それでも、直接損害の支払ならかなり信頼できる存在です。また、ケガをすれば、治療費の一括払い(病院に直接、治療費支払い)など、アメリカ人のくせに、似合わないサービスをしてくれます。また、強制保険(自賠責保険)により、任意保険以前に被害者に多少の過失があっても、一定額まで100%の治療費が確保できます。ヨーロッパの福祉国家さながら、健保・労災・自賠責と、社会保障制度が確立しています。これらは、発展途上国が目標としている社会保障制度:3種の神器で、世界的にあたり前に実現しているものでありません。国民国家としての努力の賜物です。実に、世界の半分以上の国は自賠責保険がないのです。そして、任意保険の会社があっても、肝心の加入率は30%程度が普通なのです。日本は80%のようです。すると、5台に1台は無保険になりますが、80%以上は世界的に優秀な加入率なのです。これらの比較から、いかに他人から被った被害の回復は大変なことで、当たり前に助けてもらえる事ではない世界基準を知ることになります。
落ちていた財布を拾って届ける優しく気高い精神の人が、ある日交通事故被害にあったとして、対する他人(加害者側)が決して優しくも道徳的でもないことに直面します。当然、感情的にすんなり受け入れられるものではありません。連携弁護士を含む私達はその意を汲み、できるだけ損害を回復するように働くことになります。それには、被害者さんの自助努力や費用負担も当然に必要です。そして、私達は被害者の皆様の怒りや失望を、戦いへ切り替えさせることから着手します。損害回復は当たり前のことではない、戦いであると理解することからのスタートなのです。
ちなみに、私は過去4度財布を拾い、届け出て無事に持ち主に届きましたが ・・・ 逆に、自身2度財布を落とすも、まったく届きませんでした。日本も信用できませんわ(怒)!
続きを読む »
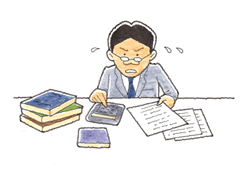


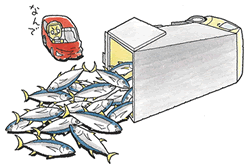 物損事故に関するご相談で、「道路の落下物にぶつかった場合は?」・・過去にいくつかの事例を経験しています。
物損事故に関するご相談で、「道路の落下物にぶつかった場合は?」・・過去にいくつかの事例を経験しています。
 ここまで説明すればお判りと思います。交通事故被害者さんが弁護士を選ぶ場合、最初に解決方針をしっかり聞く事です。「先生、裁判基準満額が取れない場合はどうしますか?」この質問に対し、妥協なき方針、確固たる戦略を提示できない先生は、竹光を差した効率先生と思って下さい。
(闘いの記録 ~ 秋葉事務所と弁護士の連携記事)
👉
ここまで説明すればお判りと思います。交通事故被害者さんが弁護士を選ぶ場合、最初に解決方針をしっかり聞く事です。「先生、裁判基準満額が取れない場合はどうしますか?」この質問に対し、妥協なき方針、確固たる戦略を提示できない先生は、竹光を差した効率先生と思って下さい。
(闘いの記録 ~ 秋葉事務所と弁護士の連携記事)
👉 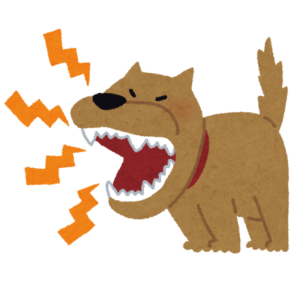



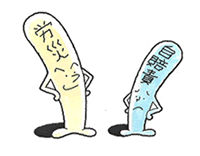

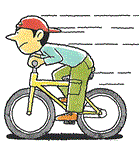


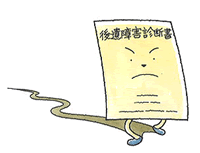
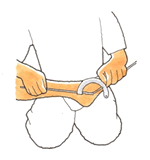


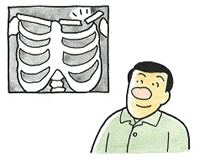 かつて、自賠責保険・調査事務所の職員がブログで嘆いていました。「いくつかの事務所からの被害者請求で、毎度まったく画像を添付していないケースがあります。これは、自賠責側に収集させようと意図しているのか、あるいは、費用負担を自賠責に課す目的か・・非常に困っています(略)」。被害者請求のルールはあくまで、書類収集は被害者(側の代理人)が行い、自らの責任で提出することです。明らかなルール違反ですから厳重注意です。確信犯的な事務所は懲戒ものとまで思います。
かつて、自賠責保険・調査事務所の職員がブログで嘆いていました。「いくつかの事務所からの被害者請求で、毎度まったく画像を添付していないケースがあります。これは、自賠責側に収集させようと意図しているのか、あるいは、費用負担を自賠責に課す目的か・・非常に困っています(略)」。被害者請求のルールはあくまで、書類収集は被害者(側の代理人)が行い、自らの責任で提出することです。明らかなルール違反ですから厳重注意です。確信犯的な事務所は懲戒ものとまで思います。
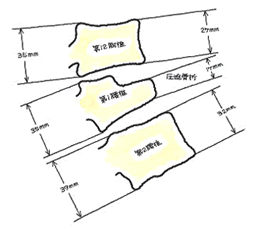
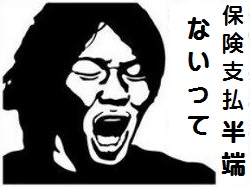
 続きを読む »
続きを読む »