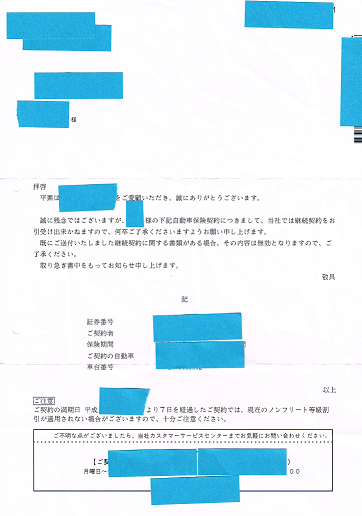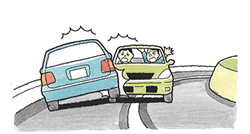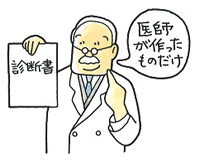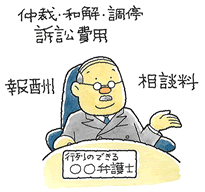よくある質問の一つに完璧にお答えしましょう。
Q:「後遺障害の申請をするのですが、相手の保険会社に診断書を出して任せてしまう方がよいのでしょうか?ネットで検索すると、被害者請求の方がいいと聞きますが・・・」
事前認定とは、後遺障害診断書を相手の任意保険会社の担当者に提出し、審査機関である自賠責調査事務所へ送達してもらうことです。被害者請求とは直接、自賠責保険に被害者が診断書等、必要書類を提出することです。
どちらがいいのか?これに対して、有利・不利などの単純な優劣ではなく、論理的に回答しなければなりません。被害者が客観的な情報から選択すべきと思うからです。まずは以下の表をみて下さい。
事前認定
被害者請求
手続き面
どちらが簡単?
楽です。相手の保険会社が書類を集積して審査先である調査事務所に送ります。
ご自身で、診断書、画像他、収集する必要があります。
審査面
全件必須ではないですが、「一括社意見書」が添付されるケースがあります。被害者にとって有利・不利な情報となるかは担当者次第ですが、被害者に審査に必要な情報、とくに後遺障害の否定する情報は漏らさず伝えるでしょう。
また、何か検査が不足していても、立ち止まって親切に教えてくれません。形式上の書類さえ揃えばさっさと提出します。任意保険・担当者の業務範囲では、後遺障害の申請内容など吟味する必要ないからです。
ご自身で積極的に検査や画像を集めることになります。立証上、足りない検査があれば追加します。
また、熟知した専門家に依頼すれば、間違いのない立証作業が望めます。逆を言えば、低レベルの先生に任せると、単に書類を右から左へ、わざわざ被害者請求する意味などない申請となります。
保険金
自賠責保険金は?
自賠責の保険金は任意会社が提示する賠償額に合意、つまり示談するまで、手にできません。
相手と示談する前に、自賠責保険金を先に手にできる。結果として、その後余裕をもって賠償交渉に臨めます。つまり、長期戦も可能となります。
費用面
経費は?
かかりません。相手保険会社が無料でやってくれます。
ご自身で動く場合は最低限の経費で済みますが、代理人(弁護士、行政書士)に依頼する費用がかかります。
この表を示すと、被害者の80%以上が被害者請求を希望します。ご自身に弁護士費用特約がついていれば、ほぼ100%が被害者請求を希望されます。問題は費用対効果(業者に依頼するか否か、業者の選定)でしょうか。ちょっと考えればわかりますよね、被害者に保険金をなるべく払いたくない相手(保険会社)にその保険金が増えるかもしれない作業を任す?・・やはり、気持ちの良いものではありません。相手任意社は露骨な妨害や不正などはしないでしょうが、少なくとも被害者の利益の為には頑張らないでしょう。あくまで事務的です。
誤解のないように言いますが、どちらの手続きかで勝負が決まるわけではありません。提出・審査先は同じ自賠責調査事務所です。審査結果は提出する書類の内容および、必要書類の完備次第です。それらが同一ならば結果は同じです。
正しい等級は「間違いや遺漏のない診断書の記載内容と、必要な検査資料の完備」にて決定します。しかし、現実は・・完璧に正しい診断書、不足のない検査資料が自動的に揃うことの方が少ないのです。協力してくれるであろうお医者さんは治すことが仕事、後遺障害の立証など興味ないからです。そして、審査上、定型書類以外の情報がまったく検討されないわけではありません。意見書の存在も気になるところでしょう。
ならば、自らの主張を徹底すべく、自ら書類集積・申請をしたいのが人情です。もしくは、精通した先生にお願いしたいのです。
連携先の弁護士事務所はどちらかの派に分かれていますが、経験を積むと被害者請求中心になっていくようです。なぜなら書類を集める立証過程でいち早く認定後の交渉戦略を構想しているからです。申請前から障害の全容を把握したいのでしょう。このような先生は「等級認定が最初の勝負!」と石橋を叩くように慎重になります。そして、自ら書類を精査・集積する過程を通して、自然と被害者請求中心になっていくようです。
経済的な面も無視できません。症状固定後、被害者は治療費を絶たれます。仕事に復帰できなければ休業補償もなくなります。被害者さんは賠償金を得るまで長い交渉期間を待つ身なのです。先に自賠責保険金を確保する、このような権利を使わない手はありません。
やはり、被害者は自らの窮状を明らかにする作業を人任せにするのは心配なのです。実際、被害者請求すれば調査事務所から追加調査や不足書類の打診が直接、自分もしくは依頼している弁護士事務所に届きます。調査内容にもよりますが、事前認定では多くの場合、任意社や病院に打診されて、追加調査の内容・進行が不明となります。この医療照会で勝負が決まることが往々にしてあるのです。
加害者側の保険会社任せ、不透明な手続き、それで認定結果に納得できますか?
一方、「どちらを選択しても結果は同じですよ、被害者請求は面倒なだけです。」と依頼者を説得している弁護士も少なくありません。
私はなぜこのように考える弁護士が多いか考えてみました。そこで思い当たるのが、このような考えの弁護士は、保険会社の顧問弁護士、もしくは協力弁護士の経験者に多くないか? です。
![f_c_035]() 続きを読む »
続きを読む »
![]() だったことです。このままでは飲酒運転に???
だったことです。このままでは飲酒運転に???