先週末、判決がでました。生活保護費の減額は違法か適法かが争われた注目の裁判でしたが、最高裁は27日午後、減額は違法とする判決を下し、国側の敗訴が確定しました。
これまでも、全国で31件、原告の数およそ1000人に上る生活保護引き下げの取り消しを求める訴訟となっていました。高等裁判所の判決が言い渡されたのは12件。「違法」が7件、「違法ではない」が5件と判断が分かれるなか、最高裁は27日「違法」とする統一的な判断を示しました。今後、類似の裁判において、指標になると思います。 憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
日本国憲法第25条の「生存権」とは・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした法律です。 この精神から、国の財政(の悪化)に関わらず、一旦決まった金額は下げてはいけない・・ことになります。 憲法25条から、優しい日本が実現できていると思います。しかしながら一方で、ろくに納税していない外国人にまで支給するケースは問題視されています。私もネパールの方で、生活保護の支給を目当てに一族が続々と来日しているケースを目にしました。また、計画的に離婚してシングルマザーとなり、生活保護を受けている方もいました。実態としては、分かれた夫と夫婦同然の生活をしているのです。
このような、制度の悪用を防ぐ手立てを強化する必要があると思います。また、度々議論される、「国民年金との逆転現象」は喫緊の問題です。真面目に年金を払ってきた人への年金支給額に、生活保護の支給額が接近しています。これは、年金など払わずに老後は生活保護を受給した方が得である・・とんでもない不公平を構成するのです。現在、年金を支払っていない層が、次々と老後になって生活保護を受給することになれば・・もう、支給額の減額は避けられない事態になります。財源には限度があります。結果として、”途中から下げられないのであれば、最初から下げる” 運用になりかねません。 将来の支給額はどうなるのか、対して憲法の精神をどこまで守るのか・・・実は、この問題は始まったばかりと思っています。


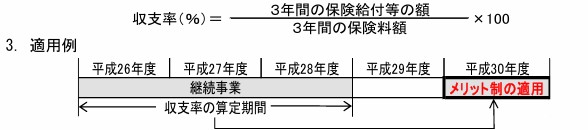 続きを読む »
続きを読む »
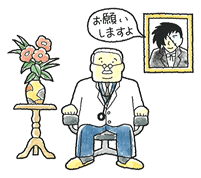

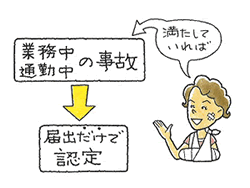 その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。
(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)
その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。
(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖) 自分の保険への請求依頼・・増えています。
PS.
自分の保険への請求依頼・・増えています。
PS.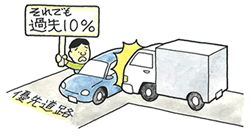
 一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。
三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか!
一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。
三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか! 対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。
二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。
対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。
二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。 続きを読む »
続きを読む » 「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。
「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。 さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。
一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。
三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。
二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。
さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。
一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。
三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。
二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。 あらゆる保険請求、ご相談下さい
あらゆる保険請求、ご相談下さい





