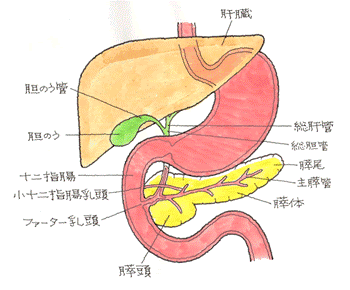これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。
交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです
被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。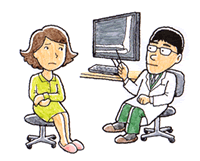
秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。 その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県) その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都) その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県) 「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。
画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。
、


 審査員に恵まれたのかな? 運が良かった?
審査員に恵まれたのかな? 運が良かった?
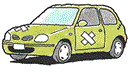
 継続治療のついでに膝の等級も上げときました
継続治療のついでに膝の等級も上げときました
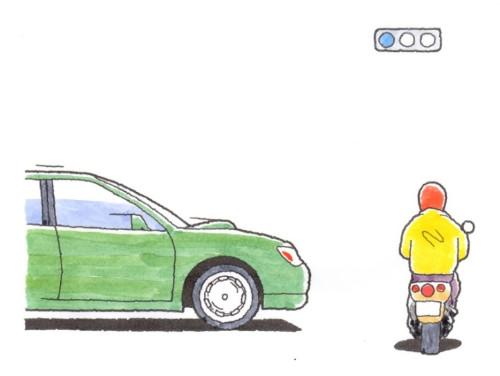 続きを読む »
続きを読む »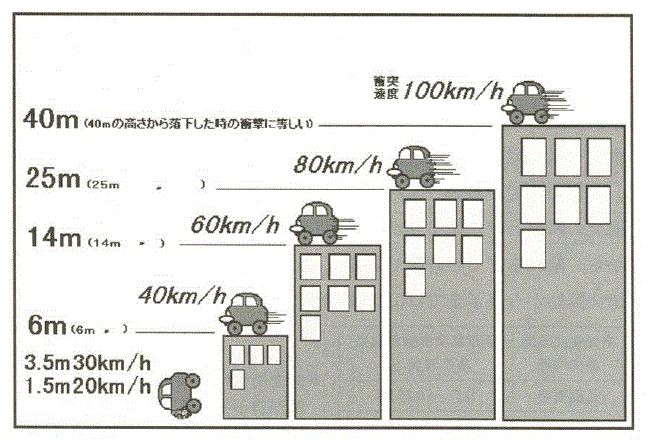
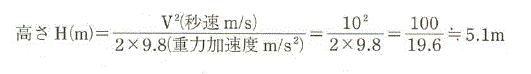
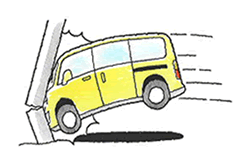
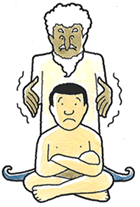
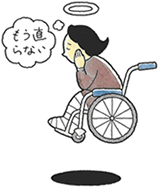

 こんにちは、金澤です。
こんにちは、金澤です。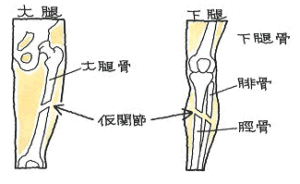 これらの判定は当然、医師が主にレントゲンやCT画像を観て判断するものです。治療を行った医師が臨床上の判断を下す場合、医師によって癒合状態の判断が分かれることがあります。例えば膝関節の「変形癒合」を判断する場合、関節機能としても通常の可動域に回復し、何より生活上問題ない場合、多少の変形があっても、直ちに「変形癒合」と断じないものです。それが微妙な変形であれば、医師の判断に違いがあって当然です。
これらの判定は当然、医師が主にレントゲンやCT画像を観て判断するものです。治療を行った医師が臨床上の判断を下す場合、医師によって癒合状態の判断が分かれることがあります。例えば膝関節の「変形癒合」を判断する場合、関節機能としても通常の可動域に回復し、何より生活上問題ない場合、多少の変形があっても、直ちに「変形癒合」と断じないものです。それが微妙な変形であれば、医師の判断に違いがあって当然です。 膝の後遺障害立証こそ、その事務所の力量を示すと言っても過言ではないと思います
膝の後遺障害立証こそ、その事務所の力量を示すと言っても過言ではないと思います
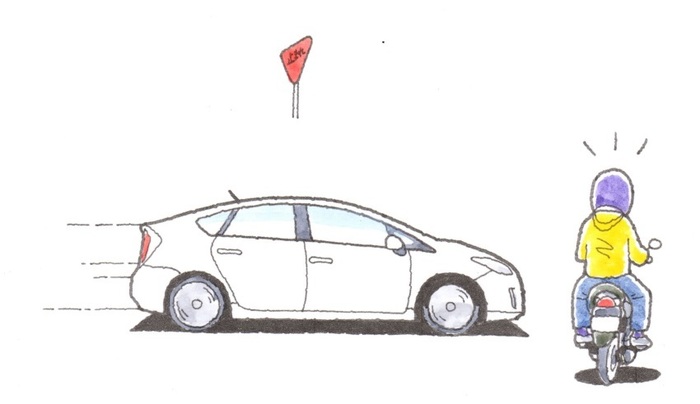 続きを読む »
続きを読む »
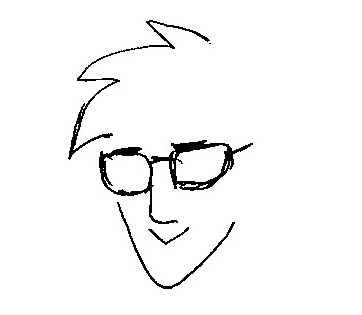
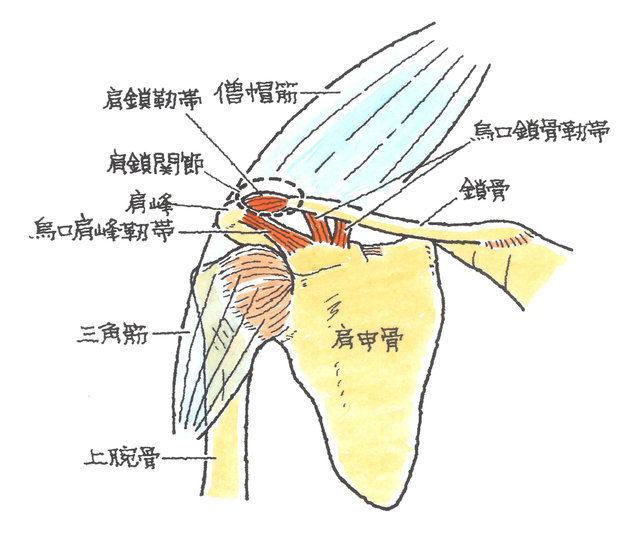

 佐藤、今日はバッターです。
佐藤、今日はバッターです。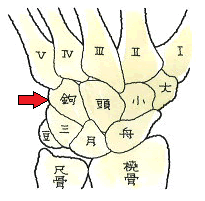
 動揺性、それが5mm前後であれば、多くは保存療法を選択します。リハビリでは、大腿四等筋を鍛えて弱くなった靱帯を助け、膝の安定性を確保することが目標となります。また、靱帯の完全断裂、又は1~2cmを越える高度な動揺性を示す場合、このレベルでは歩行に支障をきたすので手術(靱帯の再建術・・・膝蓋腱等から移植することもあります)の判断となります。
動揺性、それが5mm前後であれば、多くは保存療法を選択します。リハビリでは、大腿四等筋を鍛えて弱くなった靱帯を助け、膝の安定性を確保することが目標となります。また、靱帯の完全断裂、又は1~2cmを越える高度な動揺性を示す場合、このレベルでは歩行に支障をきたすので手術(靱帯の再建術・・・膝蓋腱等から移植することもあります)の判断となります。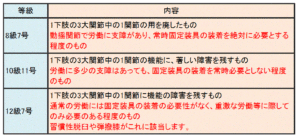 よく言えば「総合判断」、悪く言えば「曖昧」です。したがって、賠償上の判断基準と臨床上の計測・判断が繋がらない、または食い違うことが起きてしまいます。本例もその代表例です。これでは、明確な基準から正確な判断を求める、ある意味真面目な医師は記載に迷うと思います。一方、手で関節を引っ張って、なんとなく「前方1cm」と賠償上の目安に乗って記載して頂ける医師もおります。
よく言えば「総合判断」、悪く言えば「曖昧」です。したがって、賠償上の判断基準と臨床上の計測・判断が繋がらない、または食い違うことが起きてしまいます。本例もその代表例です。これでは、明確な基準から正確な判断を求める、ある意味真面目な医師は記載に迷うと思います。一方、手で関節を引っ張って、なんとなく「前方1cm」と賠償上の目安に乗って記載して頂ける医師もおります。 そこで、性格変化の症状を必要になってくるのは、家族、特に同居している家族からの報告です。事故前と事故後の性格の違いを判断でき、さらに、医師や病院関係者、近所等の他人に対しては症状が出ないことがあるため、性格変化の症状を一番認識できるのは家族だけなのです。
高次脳機能障害によって性格が変わってしまった場合、これに対する治療方法は、投薬方法があげられますが、効き目は人によってバラバラです。また、投薬以外にできることはあまりありません。このことから、一部の医師は、性格変化について、日常生活に大きく影響しない場合は重く受け止めて頂けないことがあります。この点、性格変化が加齢等によるものであれば、やむを得ないこともあるかもしれません。
そこで、性格変化の症状を必要になってくるのは、家族、特に同居している家族からの報告です。事故前と事故後の性格の違いを判断でき、さらに、医師や病院関係者、近所等の他人に対しては症状が出ないことがあるため、性格変化の症状を一番認識できるのは家族だけなのです。
高次脳機能障害によって性格が変わってしまった場合、これに対する治療方法は、投薬方法があげられますが、効き目は人によってバラバラです。また、投薬以外にできることはあまりありません。このことから、一部の医師は、性格変化について、日常生活に大きく影響しない場合は重く受け止めて頂けないことがあります。この点、性格変化が加齢等によるものであれば、やむを得ないこともあるかもしれません。
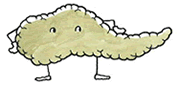 (4)外分泌機能と内分泌機能の両方に障害が認められる場合
(4)外分泌機能と内分泌機能の両方に障害が認められる場合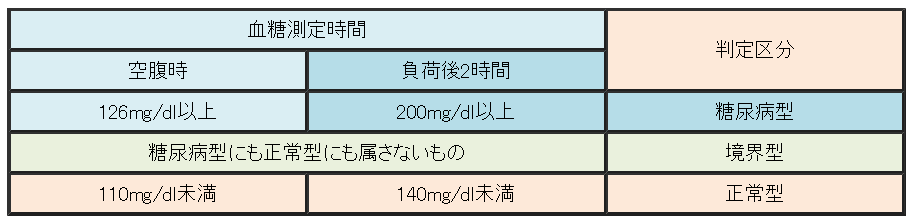 続きを読む »
続きを読む »