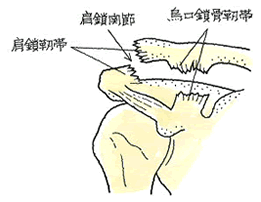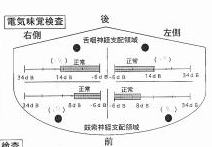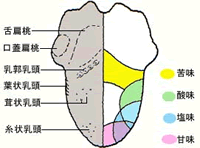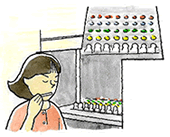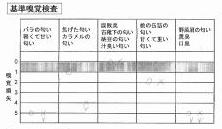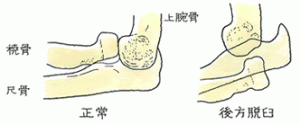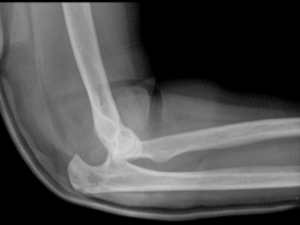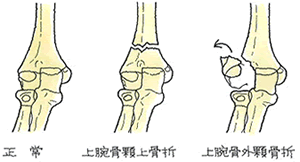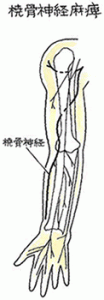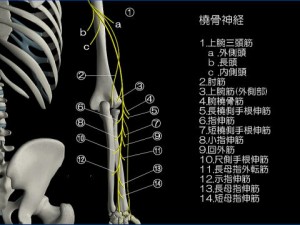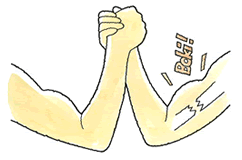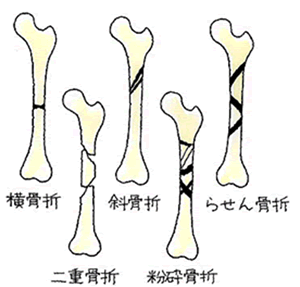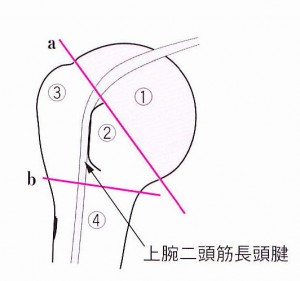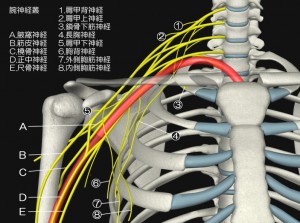では昨日の解答から。Aさんの認定結果の全文を掲載します。
<結論>
自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。
<理由>
頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。
しかしながら、治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。
Aさんは14級9号が認められました。赤字の部分は先日の<理由>に続く後段です。画像や診断がはっきりしなくても、「局部に神経症状を残すもの」と推定された結果です。つまり症状を信じてもらえた?ということです。ではもう一つのケースを。
ある被害者Bさん(40才 男性 会社員)のケース
 この方も同じく停車中、追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいのでその日のうちに病院へ。そこで頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。翌日から職場に出社しています。やはり首の痛み、腰の痛みがひどく、市内の総合病院でXP(レントゲン)を撮っていただきましたが、骨には異常ないそうです。この総合病院へは月に1回通院し、あとは土日も開いている近所の接骨院で治療を進めました。
この方も同じく停車中、追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいのでその日のうちに病院へ。そこで頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。翌日から職場に出社しています。やはり首の痛み、腰の痛みがひどく、市内の総合病院でXP(レントゲン)を撮っていただきましたが、骨には異常ないそうです。この総合病院へは月に1回通院し、あとは土日も開いている近所の接骨院で治療を進めました。
・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。Aさんに同じく、仕方がないので症状固定とし、腰に比べてよりひどい頚部痛の残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらいました。通院日数は40日を超えた位でした。そして同じように後遺障害等級の申請を行いました。
待つこと40日、「結果」が文章で届きました。今度は最初から全文を読んでみましょう。
<結論>
続きを読む »