 山本の出番! 今日もシュールです
山本の出番! 今日もシュールです
前回で述べさせていただいた通り、他覚的所見の無いムチウチの後遺障害を信じてもらう要素として、およそ90~100回以上(1週間に3~4回)の通院を述べさせていただきました。
しかし、これまで様々なムチウチの患者にお話を聞かせていただいたところ、ほとんどの方にとある共通の悩みがありました。
では、皆様に質問です。
とある、他覚的所見の無い、ムチウチの被害者が、
「仕事が忙しくてそんなに通えないよ!」
「仕事を休んだら生活がままなりませんよ!」
「日曜日は病院休みだけど、土曜日だけなら何とか通えるから週に1回は必ず病院で治療してきました。」と言っております。
その後、保険会社は事故から6ヶ月目で治療費を打ち切り、Drも症状固定をしました。
それでも首や手に痺れが残ったので後遺障害があると主張しております。
言い方がひどいかもしれませんが、保険会社(自賠責・調査事務所)にこの言い訳は通用すると思いますか。
通常、保険会社(自賠責・調査事務所)はこう考えるでしょう。
「後遺障害とは、通常、生涯にわたって治らない症状をいうのであって、そんなに重いのであれば、なにがあっても治療のために通院するはずである」と。
よって、保険会社(自賠責・調査事務所)には、このような言い訳は通用しません。
※さらに、ムチウチの多くは他覚的所見の無い場合が多く、このような被害者は症状が辛いことを証明できる客観的な証拠が無いわけですから、特に通院回数しか判断基準がない可能性があります。
→ 通院回数が多ければ後遺障害が確実に認められるわけではありませんが、少ない方よりも多い方が信用されやすいといえるので、幾つかあるうちの一つの要素として重要な位置にあるといえます。
しかし、被害者の中には本当に仕事が忙しくて、通院するのが難しい者も存在します。
そこで、このような被害者の皆様には、ご自身の環境と照らし合わせて頂く必要があります。
(1)まず、病院が開いている時間帯に通えるようにできるかを考えてみてください。
自宅から少し離れている場所に病院があるのであれば、より自宅により近く、かつリハビリ施設が整っている病院を探してみてはいかがですか。
(2)それでも自宅近くの病院に通い続けるのが厳しいというのであれば、最寄り駅の近くで探してみてください。
最寄り駅であれば、仕事から帰る途中等で通いやすいはずです。
(3)そこでも無理があるのであれば、職場近くの病院を探してみてください。
職場近くであれば、通勤途中に通いやすく、最悪、休み時間中にリハビリだけでもすることは可能のはずです。
病院にもよりますが、リハビリは10分から20分位です。待ち時間で昼休みが終わってしまう恐れがありますので、医者としっかり相談してみてください。病院によっては融通が利くところもございます。
※ それでも、通院できず、しかも仕事をしないと生活が苦しいという場合には、最悪、仕事をお休みしてください。休んで通院した場合、仕事を休んで収入が減ってしまった分については、「休業損害証明書」を会社に書いてもらい、保険会社にその損害分を支払ってもらうようにしてみましょう。
たくさん通院してしまい、後遺障害が残らないのではないかという不安を抱く方がいらっしゃるという噂を耳にします。本当に辛い交通事故被害者は、何よりも、完治することを願っております。私達は、そのような被害者の救済を手助けすることを生業としております。
後遺障害が残るように治療をします?
そのような依頼者がいないことを願っておりますが、仮に本当にいたとしても、保険会社(自賠責・調査事務所)はすぐに見抜きます。
敢えて解答しませんが、最後に皆様に質問です。
全国レベルで展開しており、何千・何万もの交通事故案件を見てきており、かつ全国の病院のデータをも押えている組織を欺くことが出来るでしょうか?
続きを読む »
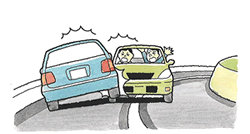

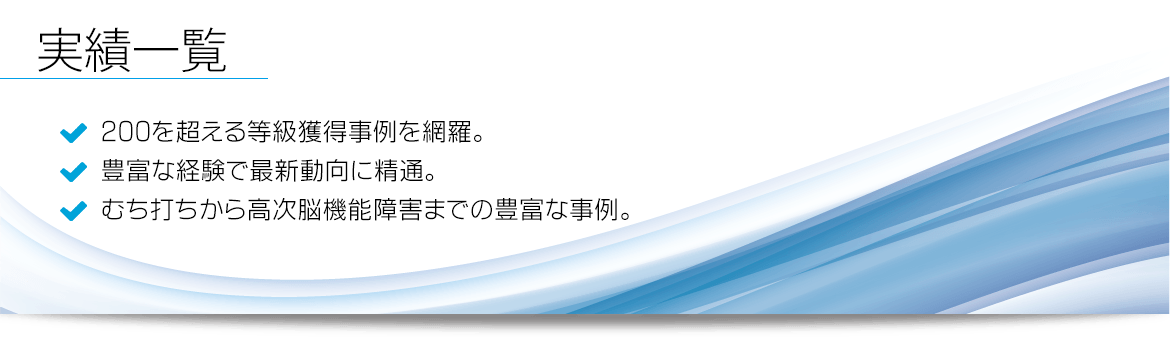

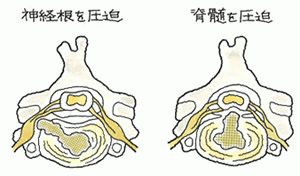


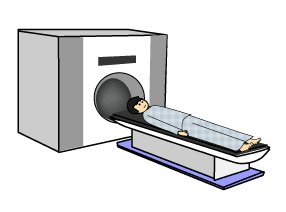

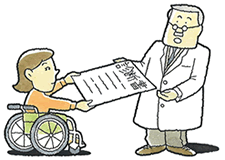


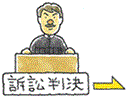
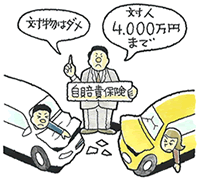
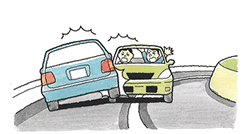
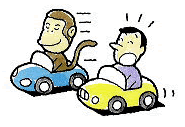
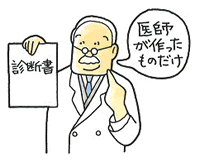



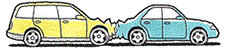


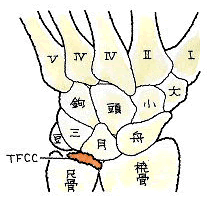 【問題点】
【問題点】




