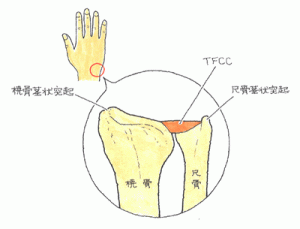神経系統の障害は諸々の症状を包括的に判断します。例えば脳損傷となり、記憶障害が9級程度、めまいが12級程度、排尿障害が11級程度・・これらを併合せず、ひっくるめて総合判断で7級とするような・・。これは自賠責が労災認定基準の「神経系統の障害を労働能力の喪失程度から判定する」ことを基にしているからです。
さて、本件盛りだくさんの障害を明らかにしましたが、高次脳機能障害まで立証し切れませんでした。まず、自覚症状(高次脳の場合、家族の観察)がどの程度なのかが出発点です。初回の本人面談で私は高次脳を予断しました。しかし、続く家族の観察から障害の表出が乏しく、最後まで疑問のままでした。つまり、本件は予断をはずしたようです。こうして高次脳未満は「高次脳崩れ」の12級13号確保が目標になります。 本件、提出書類から状態を見極めた自賠責・高次脳審査会の慧眼には恐れ入りました。
12級13号:脳挫傷・14級9号:頬骨骨折・12級相当:味覚障害・13級5号:歯牙欠損・14級相当:嗅覚障害(50代男性・神奈川県)
【事案】
自転車で直進走行中、前走バイクが急転回し、衝突したもの。頬骨骨折により、顔面に神経性疼痛、嗅覚・味覚の異常も生じた。また、脳挫傷があり頭痛やめまいに悩まされる。その他、歯を数本折った。 リハビリ後も完全回復とならず、現場の仕事から内勤に転任を余儀なくされていた。
【問題点】
相談会で高次脳機能障害の精査を必要と感じた。早速、主治医に面談し各種検査を行ったが、家族からの観察に比して整合性のある結果とならかった。果たして脳障害はあるのか?迷いの中、作業が進んだ。
高次脳機能障害で一くくりにできれば良いのだが・・・高次脳が否定された場合、はっきりと数値に出る検査のない頭痛、めまい・ふらつき、顔面の痛み、これらを神経系統の障害としてまとめる作業となる。
【立証ポイント】
味覚・嗅覚はおなじみの検査を実施するのみ。歯については既存障害歯と事故で欠損した歯を分けて把握する必要がある。歯科医と打合せし、XP画像を預かり、専用診断書に記載頂く。
結果、味覚喪失で12級相当、嗅覚減退で14級相当とした。歯については事故前からの障害歯と新たに折れた歯を合計、現存障害として13級5号(本件の場合、併合ルールの優位により加重障害とならず)。
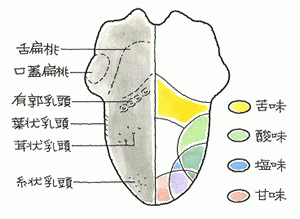
続きを読む »


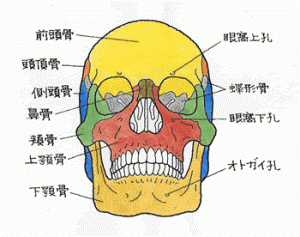
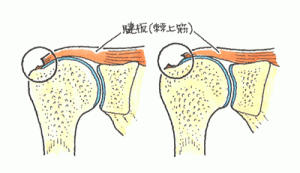
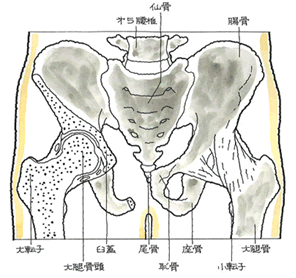

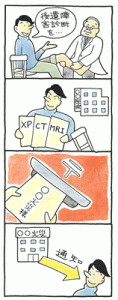
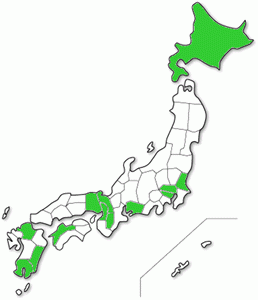

 明日の東京相談会が終わると、シルバーウィークに突入です。しかしながら、相変わらず書類仕事が山積、完全に休むことは不可能です。それでも合間を縫ってリフレッシュを図りたいところです。水曜から北海道出張がありますが、今度はレンタカーを借りてドライブ気分を画策しています。
明日の東京相談会が終わると、シルバーウィークに突入です。しかしながら、相変わらず書類仕事が山積、完全に休むことは不可能です。それでも合間を縫ってリフレッシュを図りたいところです。水曜から北海道出張がありますが、今度はレンタカーを借りてドライブ気分を画策しています。 続きを読む »
続きを読む » この所見から14級9号を目指して異議申立てを行った。これなら自賠責も認めてくれた。そして、症状固定から1年あまり、可動域はほぼ回復した。調査事務所の(可動域制限はないという)判定は正しかったと言わざるを得ない。私達も経験を重ねるごとに謙虚になります。
この所見から14級9号を目指して異議申立てを行った。これなら自賠責も認めてくれた。そして、症状固定から1年あまり、可動域はほぼ回復した。調査事務所の(可動域制限はないという)判定は正しかったと言わざるを得ない。私達も経験を重ねるごとに謙虚になります。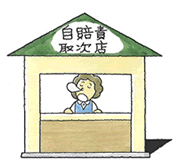
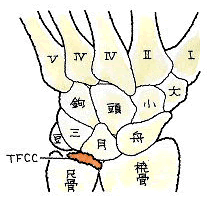 【問題点】
【問題点】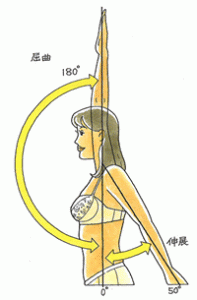 【問題点】
【問題点】